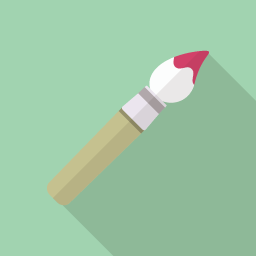遍歴の歌人
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は学校では取り上げることのない作品について書きます。
『都のつと』は1367年に成立した紀行文です。
筆者は宗久という南北朝時代を生きた歌人です。
おそらく聞いたことがないんじゃないでしょうか。
タイトルの「つと」という言葉が気になりますね。
「つと」とはお土産のことです。
つまり道中の名所の印象を次々と書きしるし、それを土産がわりにしますよということなのです。
昔は旅をするなどということはまずできない相談でした。

街道も十分に整備されていない上に、宿泊をする場所も満足にありません。
一生の間、生まれた土地で静かに暮らす以外に方法はありませんでした。
旅はまさに命がけの行動だったのです。
少しは動けるようになった江戸時代でも、水杯を交わしてから旅立ちました。
もう2度と会えないかもしれないという覚悟です。
『都のつと』は、14世紀の中頃、九州を出て諸国を放浪した歌人が書いた本です。
修行のため東国への旅を思い立ち、東海道を下りました。
歌枕を訪ねながら鎌倉まで辿り着いたのです。
しかしここで旧知の人が亡くなったことを知り常陸(茨城県)や甲斐の国(山梨県)などを巡って秩父まで来ました。
村人から「ひげ僧」と呼ばれた武蔵国の高徳の隠者の元に冬の間、滞在したのです。
春になってから上野国(群馬県)に行脚した際、一夜を世話になった主人との忘れがたい思い出を残した一節をご紹介しましょう。
原文
春になりしかば、上野国へ越え侍りしに、思はざるに一夜の宿を貸す人あり。
三月の初めのほどなりしに、軒端の梅のやうやう散り過ぎたる木の間に霞める月の影も、雅びやかなる心地して、所のさまも、松の柱、竹編める垣し渡して田舎びたる、さる方に住みなしたるも、よしありて見えしに、
家主出で合ひて、心あるさまに旅の愁へをとぶらひつつ、世を厭ひそめける心ざしのほどなど、細かに問ひ聞きて、
「我も常なき世のありさまを思ひ知らぬにはあらねども、背かれぬ身の絆のみ多くてかかづらひ侍るほどに、あらましのみにて今日まで過ぐし侍りつるに、今宵の物語になむ、捨てかねける心の怠りも今更驚かれて。」

など言ひて、「しばしはここに留まりて道の疲れをも休めよ。」と語らひしかど、末に急ぐことありしほどに、秋のころ必ず立ち帰るべきよし契りおきて出でぬ。
その秋八月ばかりに、かの行方もおぼつかなくて、わざと立ち寄りて訪ひ侍りしかば、その人は亡くなりて、今日七日の法事行ふよし答へしに、あへなさも言ふ限りなき心地して、などか今少し急ぎて訪ねざりけん
さしもねんごろに頼めしに、偽りのある世ながらも、いかに空頼めと思はれけんと、心憂くぞ侍りし。
さて、つひのありさまなど尋ね聞きしかば、「今はの時までも申し出でしものを。」とて、あとの人々泣き合へり。
有待の身、初めて驚くべきにはあらねども、無常迅速なるほども、今更思ひ知られ侍りし。
さてもこの人は、よろずに好ける心のありし中にも、和歌の浦波に心を寄せ侍りしと、人々語りしかば、昔の素意を尋ねて、心ざしの行くところを、いささか宿の壁に書きつけて、出で侍りぬ。
現代語訳
その所(秩父)に冬の間は滞在して、春になったので、上野国へ越えて行ったところ、思いがけなく、一夜の宿を貸してくれる人がおりました。
3月の初めの頃でしたが、軒端の梅がようやく散り果てた木の間に霞んだ月の光も風雅な気持ちがして、この場所の様子も、松の柱も、竹を編んだ垣根をめぐらせて、田舎風です。
住む家を整えているのも由緒ありそうに見えましたが、この家のあるじが出て来て、思いやり深く旅の辛さをねぎらいながら、私が出家を思い立った心情のことなど、細かく尋ね聞ききます。
「私も無常の世の有様を思い知らないわけではありませんが、簡単には出家できないような絆ばかりが多くて俗事にかかずらっております。
出家の予定だけが先にあって今日まで過ごして参りましたが、今夜のあなたとのお話で、俗世を捨てかねていた私のなまけ心にも、今さら気づかされまして」などと言います。
「しばらくここに滞在なさって、どうぞ疲れをお休め下さい」と誘ってくれましたが、まだ先に急ぐ用があったので、秋の頃、必ず帰って来ることを、約束しておいて旅立ちました。
3月の初めに、上野国で宿を貸してくれた人と、秋のころ、必ずまた来るからと約束して別れたのです。

その年の秋8月ばかりに、あの人のその後も気にかかって、かの人の家に立ち寄って訪問したところ、既に亡くなっていて、ちょうど今日、初7日の法事を行うということでした。
人の命ははかないともなんとも言いようもない心地がして、どうしてもう少し急いで訪ねなかったのだろう、あのように心をこめて再会を約束したのに、人のことばに偽りのある世の中とはいえ、私はどんなにあてにならないやつと思われただろうと、悲しかったことです。
そして臨終の様子などを尋ね聞いたところ、「今はもう死ぬという時までもあなたとの再会のことを口にしておりました」と言います。
遺された人々は互いに泣いておりました。
有待の身(死をつねに孕む運命))であることは今さら驚くほどのことではありません。
しかし無常迅速(死が突然襲ってくること)ということを、今更のように思い知らされました。
そのうえかの人は、万事風流を好む心があった中でも、和歌の方面に心を寄せていたと、遺族の方々が語りましたので、故人の遺志を慮って気持ちのおもむくままを、いささか家の壁に書きつけて、出発したのです。
無常迅速
この文章を読んでいると、主題の1つとして「無常迅速」という言葉が頭に思い浮かんできます。
「無常」(死)が突然のように訪れるという考え方は中世をはじめ、いつの時代にもあったようです。
『徒然草』第59段には「無常の来たることは、水火の攻むるよりも速やかに逃れがたきものを」という表現まで出てきます。
一方で作者が心にとどめて記録した家主と作者のエピソードにそって考えてみると、また別の感想も浮かんできます。
約束がいとも簡単に消されてしまう時代であればあるほど、約束を守ることの信義も問題になるのでしょう。
約束の秋に訪れた作者、臨終の時まで作者を待った家主、結果として約束を守れなかったことを悔やむ作者の姿から日本人の心の中に宿っている「信義」の意味をつい考えてしまいます。
特に内容が難しい文章ではありません。
しかしつい引き込まれてしまいますね。
一夜、泊めてくれた主が心をこめてもてなしをしてくれ、さらに旅の難儀を1つ1つ聞いてくれたことがよほど心に沁みたのでしょう。

あるじ自身も出家を希望していたようです。
しかし「背かれぬ身の絆のみ多くて」と語っています。
「絆」という表現は「ほだし」と読みます。
元々は馬の足をつなぎとめるための縄のことを言いました。
そこから人の心や行動の自由を縛るものとか、自由をさまたげるものの意味になったのです。
つまりあちらに気を使い、こちらの用事もなんとかしなくてはならないという条件が次々と出てきたというワケです。
浮世のしがらみというもののことです。
だからこそ、歌人の自由な境遇に一層の共感を覚えたのでしょう。
死ぬという時まで約束のことを気にしていたという言葉に嘘はないと思います。
心から再会を果したいと考えていたに違いありません。
それもかなわないまま、遠い世界へ旅立ってしまいました。
無常迅速という言葉が実感をもって感じられます。
人の一生とは何なのでしようか。
あまりにもあっけない幕切れに不思議な感覚すら覚える今日この頃です。
それにしても日本人は漂泊の詩人が本当に好きですね。
後世、明らかに芭蕉の『奥の細道』に影響を与えた思われるところもあります。
興味があったら是非目を通してみてください。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。