好きな噺
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家でブロガーのすい喬です。
今までに隋分とあちこちで噺をさせてもらいました。
レパートリーもかなりの数があります。
お稽古をしてもしばらくすると、よく高座にかける噺とそうでないものに分かれていきますね。
好きな噺というのが自然にでてくるのです。
自分にあっているというのでしょうか。
なぜか喋りたいのです。
その1つが「井戸の茶碗」です。
なぜ好きなのか。
理由はよくわかりません。
あえていえば、善人しか出てこないからでしょうか。
落語には基本的に悪人はあまり出てきません。
しかしこれだけ善人ばかりが集まると、本当かなとつい思ってしまいます。
それでもやっぱり一席話し終えると、いい気分なんですね。
最後がおめでたいということもあるんでしょう。
正直の頭に神宿るということわざがあります。
まさにあれです。
なぜタイトルが「井戸の茶碗」というのかといえば、小道具としてこの茶碗が大きな意味を持っているからです。
あらすじ
登場人物は正直者の清兵衛さん。
商売は屑屋さんです。
今の廃品回収業ですね。
ある日、千代田卜斎という人物から仏像を200文で買い取って欲しいと頼まれます。
始めは断りますが、どうしてもお金が必要という頼みに負けて200文で仏像を預かり、売れたら儲けは折半という約束にします。
仏像を持ち町を歩いていると芝のあたりで細川の家臣、高木佐久左衛門という若い侍に声をかけられます。
仏像を売って欲しいとのことなのです。
朝夕、手をあわせるものが欲しいといいます。
300文で仏像が売れました。
ところが煤けている仏像を磨いていると、仏像の台座がはがれて50両もの大金が出てきたのです。
慌てて持ち主に返そうと屑屋の清兵衛を探し回ります。
やっとの思いで屑屋を見つけ50両を返すと、屑屋は仏像を買った千代田卜斎の元へそのお金を持っていくのです。
しかし千代田卜斎は、売ったものだから私のものではないと頑固に受け取りません。
両者の間を屑屋さんは行ったり来たりするものの、一向に目途がたたないのです。
そこで仕方なく家主に相談しました。
家主は「千代田卜斎に20両、高木佐久左衛門に20両、清兵衛に10両でどうだ」と案を出します。

千代田卜斎は20両のかたに毎朝湯茶を飲んでいた茶碗を高木佐久左衛門に譲ることでしぶしぶ納得したのです。
しばらくして、この話を聞いた細川の殿様がその茶碗を見たいと言い出しました。
茶碗を見るや、これが知る人ぞ知る名器、井戸の茶碗でした。
殿様はそれを300両で買い取ったのです。
困った末、屑屋の清兵衛に間に入ってもらいお金を返しに向かいます。
しかしまたも頑固に受け取りません。
最後は千代田卜斎が半分の150両を娘の婚礼支度金としてくれるというなら受け取るということになりました。
母親のいない娘だが、一通りのことは教えてある。
高木殿ならば間違いはない。
娘をもらっていただけるなら、このお金は頂戴します。
高木作左衛門との結婚がその条件だったのです。
楚々とした実に美しい女性として娘さんの様子が描かれていています。
「今は裏長屋でくすんでいますが、磨けば立派なお嬢さまになりますよ」と屑屋さんが高木作左衛門にいいます。
「いやあ、磨くのはよそう。また小判が出てくるといけない」というのがこの噺のオチです。
骨董市
この落語を覚えた頃、骨董に興味を持ちました。
上野の博物館へ「井戸の茶碗」を見学にいったりもしたのです。
時には骨董市へも寄りました。
あちこちの店をひやかしているうちに、なんだか訳のわからない陶器を売っているところにでっくわしたのです。
大きな板の上に並べられているのは、みな割れた茶碗ばかりです。
こんなもの何に使うのかと思って値段を見て驚きました。
みんな、1万円以上もするのです。
わずか5センチ四方のもあれば、3分の1ぐらいは原型を保ったものもあります。
しばらくその茶碗のかけらに見入ってしまいました。
素人の目から見れば、本当にどうということはない、ただの瀬戸物のかけらです。
そのままゴミ箱へもっていって、一巻の終わりというところでしょう。
しかしそんなものを売りに出そうという人がいて、また買おうという人がいるのだから、やはり世の中というのは面白いですね。
あんまりぼくがしげしげと眺めているものですから、店の主人が向こうから声をかけてくれました。
「どうしてこんなに高いんですか?」
我ながらまことにドジな質問です
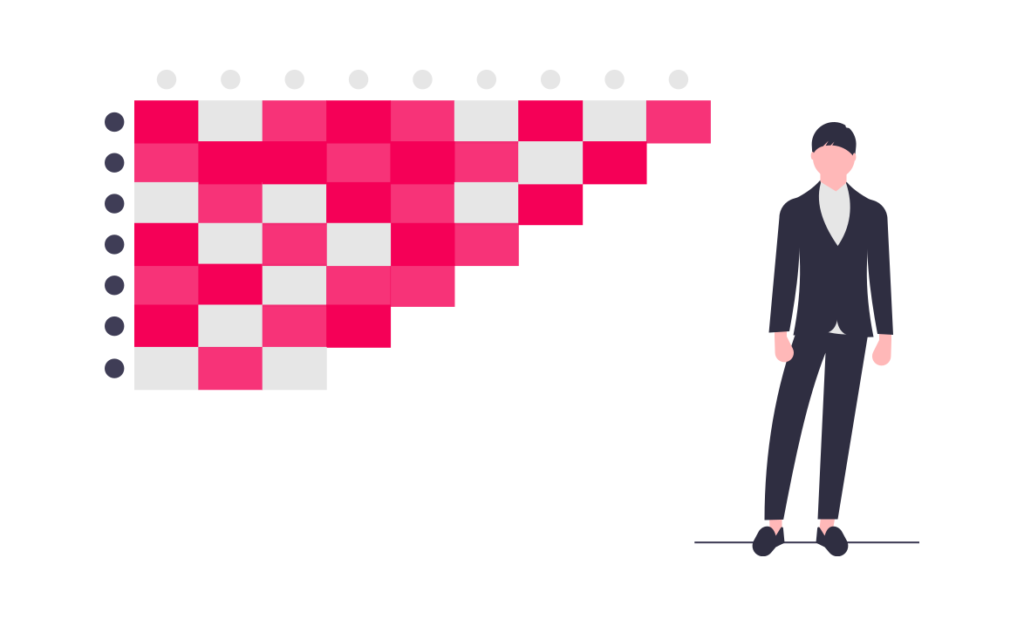
素人だということが、一目瞭然です。
「それは唐津ですよ。ほら裏をみて、この厚みを感じれば、すぐにわかる。いいもんです、これは。こんなのはそんなにないんだから」
主人はしきりに手でかけらの厚みを強調します。
ぼくは眉に唾し、こんなものでは騙されないという顔をしなくてはいけないと思いました。
「これは割れてなかったらどれくらいするんですか?」
またまたドジな質問です。
いい加減にしてくれという顔の主人は、「ゼロが2つはつくなあ」とこともなげに呟きました。
「きちんとした箱に入れて、上から一筆書いてもらえれば100万だね。これは江戸初期だから。唐津はなかなかちゃんとしたのがなくてね」
最後はご主人の述懐です。
そういうものかと思わず、ため息が出ました。
奥の深さ
どうみてもぼくにはただのかけらにしか見えません。
最近はこういうのに苔玉などをのせて楽しむ人が多いのだといいます。
骨董の世界は奥が深いです。
何十年も騙されて、やっと目が肥えてくるのです
海千山千の中に入って、商いをするのはそんなに簡単なものではないに違いありません。
ぼくはご主人に礼を言ってから、その場を立ち去ることにしました。
帰りの電車の中で、いったい破片になったぼくは幾らで売れるのだろうかと考えました。
隣で居眠りをしている奥様にそう問うと、
「ばかね、そんなこと言ってるから、あなたには価値がないのよ」
一言の元に夫を切り捨てたのです。
落語には骨董を扱った噺がいくつもあります。
好きなのは「はてなの茶碗」「猫の皿」あたりですかね。
どちらもしみじみとしていて、つい引き込まれてしまいます。

はてなの茶碗は上方の噺です。
亡くなった桂米朝の十八番でした。
「猫の皿」はぼくもやります。
古今亭の噺なのでしょうか。
志ん生は好んでよくやりました。
古いものにはやはり味があります。
歳月は嘘をつきませんね。
長い時間を経ても価値があるというものこそが本当なんでしょう。
是非、そうなりたいものです。
真贋を見抜く目というのはどうすれば磨かれるのでしょうか。
本物を見続ける以外にはないんでしょうか。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。


