哲学の現在
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は「機械論的身体観」を軸に人間の存在について、論点を整理してみます。
筆者の中村雄二郎氏は早くからフランス人文主義に関心をもち、パスカルやデカルトを研究した哲学者です。
著書『パスカルとその時代』がよく知られています。
その後、人間総体を根源から回復させる方法として、共通感覚を重視する『共通感覚論』を発表しました。
今回、紹介する文章は岩波新書版『哲学の現在』に収められたものです。
題名にある「現在」とは「過去」に対する「現在」ではなく「不在」に対する「現在」をさします。
考えることを離れて、よく生きることはできないという彼の考え方の基本がここには示されています。
ポイントは二元論的な科学の考え方によって、人間を分析の対象にしすぎたという反省から、書き始められていることです。
人間を有機的なものとして、全体的に捉え直していくことの大切さを再認識するということが、ここでの主題なのです。
その論点の中で述べられているのが、ここに示された「機械論的身体観」です。
人間を肉体と精神に分離し、もっぱら肉体を科学の対象にしてきたことが大きな問題だと指摘しているのです。
生きることの確実性がゆらいでいる時代の中で、どうすれば人はしなやかになれるのか。
そのことをあらためて考えなおそうとした文章です。
ここでは、二項対立の中心に位置しているのが「機械論的身体観」です。
「機械論的身体観」とは、わかりやすくいえば、人間を機械のように捉える考え方、すなわち「人間機械論」のことです。

そもそも機械論とはなんのことなのでしょうか。
わかりやすくいえば、自然や社会、生物を扱う際に、内的目的や霊魂を排除して、物質的な諸要素の集合とその運動を取り扱う態度です。
機械論的世界観とは、世界は原因と結果の連鎖によって動いている、つまり時計のようなものだという考え方なのです。
ある意味、非常にわかりやすく単純化した世界観です。
誰にでも理解しやすいともいえるでしょう。
それを人間にまで敷衍したのがいわゆる「人間機械論」なのです。
人間を一種のメカニカルな部品の集積であると考える立場です。
普通、人間は心と身体をもち、このうち身体は生理的、物理的分析を受け入れると考えられています。
しかし栄養をとったり、運動するといった生理的な働きではなく、ものを考えるなどのいわゆる理性的働きは、一見して、物理学的に分析し尽くされないものを含みます。
本文
近代生理学や近代医学を生み出し発展させてきたのは、なんといっても身体に対する機械論的な考え方である。
そして、近年では次第にそれへの批判と反省が高まってきてはいるものの、今なおその支配力は失われてはいない。
現在、医学の最先端で行われている内臓器官の切除や移植のようなものは言うまでもない。
しかし、そこまでいかなくとも、多くの合成された薬の投薬、注射、輸血などのようなごく一般的な医療方法を考えてみてもわかる。
もちろん、今言ったような意味での機械論的な身体観は、それだけ独立してあるのではない。
思考する精神と広がりを持った物体という存在の二元論は、その展開として、観察し認識する主観(主体)と、観察され認識される対象(客観)という認識の二元論をもたらし、全てこの世の中のものは、ここに主観(見るもの)と対象(見られるもの)に二分されるようになった。
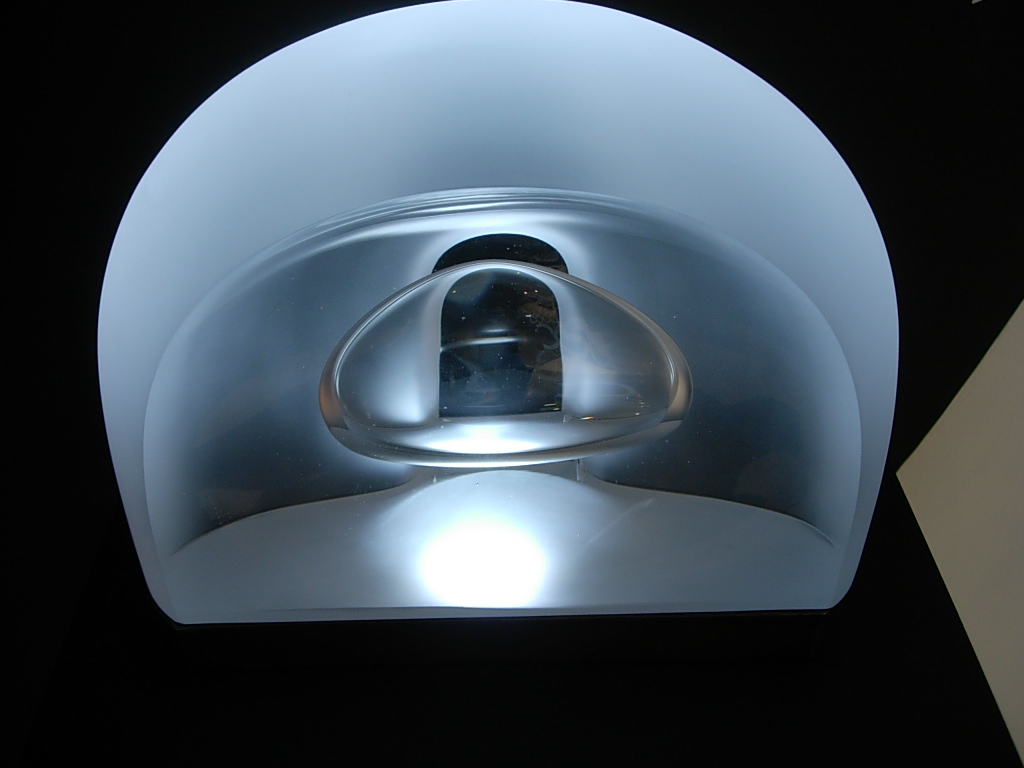
そのような全体の枠組みの中では、当然のことながら、物体そのものとして身体は対象(見られるもの)の側に入れられ、もっぱら見られる対象として扱われる。
医学の、医者の立場がそうであるだけでなく、私たち一人一人が、自分の躰を、身体をそのようなものとして見るまなざしを、知らず知らずに身につけてしまう。
しかしながら、私にとって自分の身体はそのようなものとして収まりきるであろうか。
ただ見られるものにとどまるであろうか。
我が身を振り返ればすぐ分かるように、むろんそんなことはありえない。
ありうるはずもない。
観察と認識の中で中心をなす見ることを例にとってみても、見ることは意識の働きだけによるのではなく、目に、つまり身体によらなければならないからである。
同じことは、聞くことと耳、触ることと手についても、更に知覚の全体と躰の全体についても言える。
私にとって自分の身体は、決して自分と別のもの、偶然的なものではない。
それは何よりも、意識の働きの、つまり主観の、意志の働きの、つまり主体の基盤をなしているのである。
機械論的身体観
ここで中村雄二郎が述べている「機械論的身体観」をもう一度整理してみましょう。
要約すると、身体を機械のように捉える考え方であり、身体の各部分が機能的に働くシステムとして理解することです。
単純にいえば、人間を各器官に分割するのです。
心臓をはじめとした内臓器官も、病んだ部分を取り換えていけば、再生は可能だとする考え方です。
ロボット型のサイボーグをイメージしてください。
病気にかかった個所をなおしていけば、個体としての復活が可能だという認識です。
この観点の延長線上をたどると、現代の分業化された医学にもその傾向がみてとれます。
病気に侵された患部が生理学的に治癒すれば、それで人間総体が完治するという考え方です。

身体は生理学的なメカニズムや物理的な構造に基づいて分析され、人間の行動や意識もこのメカニズムの延長として扱われます。
もちろん、これが医学の全てではありません。
まったく正反対の立場から人間総体を見ようという考え方もあります。
しかし主要な流れは解体と分析と治療です。
身体は物理的に対象化され、部位に分けられる傾向が強いのです。
哲学的思考
ところが、哲学者、中村雄二郎はこの考え方をとりませんでした。
機械論的身体観に対して真正面から批判的な立場を取っています。
彼は、身体を単なる物理的な存在としてではなく、意識や感情、社会文化的な文脈と密接に関連した存在として捉えるべきだと主張したのです。
身体が持つ主観的な経験や意味を重視し、機械論的な視点では十分に理解できない人間の豊かな体験を強調しました。
中村は身体を「生きた存在」として捉えるべきだとしています。
彼の考え方は、身体性を通じて人間の存在を再評価し、より包括的な理解を目指すものです。
ここに大切な論点のポイントがあります。
この対立が最後まで大きな意味を持つのです。
彼の考え方が現代の身体論にどのような影響を与えているかを考えてみましょう。
中村のアプローチの方向は明確です。
身体を単なる物質的な存在としてではなく、文化的、社会的、心理的な側面を持つ複雑な存在として捉えることに重点を置いています。
主観的な経験を重視し、身体が持つ感覚や動きがどのように個人の認識や世に影響を与えるかを探求しました。
この考え方は、現代の身体論においても、身体的経験が認知や社会的関係にどのように結びつくかを理解する上で重要な視点となっています。
さらに言えば、身体が権力や社会的構造とどのように関連しているかを考察する際にも重要です。
現代の身体論では、身体がどのように規範やアイデンティティに影響を与えるかを探る議論が盛んであり、彼の思想がその基盤となっているのです。
中村は身体を「生の哲学」と結び付けています。
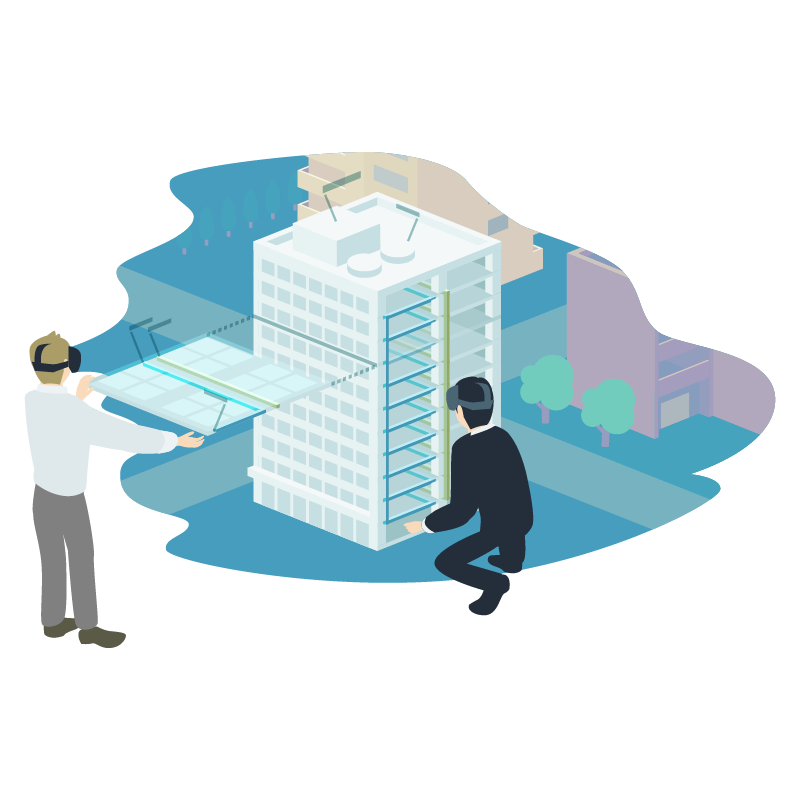
身体が持つ生き生きとした側面や、生命の力を重視したのです。
この視点は、現代の身体論における「生きること」や「存在」についての考察に大きな影響を与えています。
文化的、社会的、心理的な文脈の中で理解するためには、圧倒的な想像力を必要とするものです。
人文、自然科学的な理性だけでなく、芸術的な感性も大切なのです。
その意味で、この文章を小論文の課題にする大学もいくつかありました。
評価のポイントは、どの程度自分の理解を具体的な経験とあわせて論述するかによるでしょう。
キーワードをうまく使いながら、800字程度でまとめるためには、身体と精神の関係がどれほど密接であるかを示さなければなりません。
機械論的な身体観の持つ限界を自分の経験からまとめることができれば、必ず成功します。
キーセンテンスは次の通念の後にくる考え方です。
身体は主体によって見られる対象として扱われるが、実際は主体の基盤をなしているという構図なのです。
ここからどの程度、書き込めるかで評価が分かれます。
ぜひ挑戦してみてください。
その際、どちらの立場をとるのかをまず明確にすることが大切です。
それにあわせて自分の経験や、見聞を含めて理由づけをしてください。
難しいテーマではありますが、二項対立の図式にのせて立論を進めるべきです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


