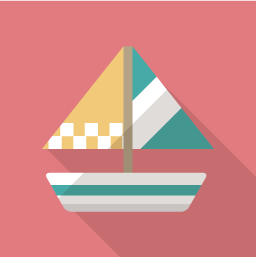対話の言葉
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は劇作家、平田オリザ氏の文章を読みましょう。
タイトルは『わかりあえないことから』です。

彼の代表作は岸田國士戯曲賞を受賞した『東京ノート』でしょう。
会話が折り重なるようにして発せられる戯曲は、大変新鮮なものでした。
それまでのスタニスラフスキーシステムの演劇にはない、同時発声が大変ユニークだったのをはっきりと覚えています。
芝居では、誰かが台詞を発する時、他の俳優たちは黙って見ているのが普通です。
そうでないと、セリフが重なって聞き取りずらくなり、進行を妨げると考えられてきました。
それを彼は否定したのです。
どの戯曲にも同時に台詞を呟くシーンが出てきます。
さらにいえば、ほとんどこれといった山場のないまま、劇は終わるのです。
平田オリザ氏の考え方によれば、日常がそのままゆったりと流れるのが、本来の芝居であり、ことさらにクライマックスがあるのはおかしいというのです。
そこから彼の芝居は「静かな演劇」と呼ばれてきました。
芝居の前に別の場所で、ワークショップが開かれることもよくありました。
高校で演劇部の顧問をしていたぼくは、いろいろな意味で刺激を受けましたね。
彼が高校時代、自転車で世界一周を試みたという本も、実にユニークで面白かったのが記憶にあります。
駒場にあったアゴラ劇場を訪れたこともありました。
その後は本を読むだけになってしまいましたが、いい意味でのインスパイアーは今も続いています。
対話と会話
ここで取り上げる評論は、人間が話す言葉には、いろいろなカテゴリーがあるという話です。
厳密にいうと、「対話」と「会話」は違います。
日本語ではその使い方がかなり曖昧ですね。
その差はいったいどこにあるのか。
日本人は基本的に相手と意見を戦わせるということが、あまり得意ではありません。
いわゆる議論下手なのです。
ディベートの授業などをしても、そのことがはっきりとわかります。
1つの島に住んでいる、同じ民族だということもあるのでしょう。
農耕社会がそこに住む人の人格をある程度、規定したという面もあるにちがいありません。
会話というのは一般的に親しい人同士のおしゃべりなどをさすことが多いです。
会話が弾むという表現には、楽しいイメージが先行しますね。
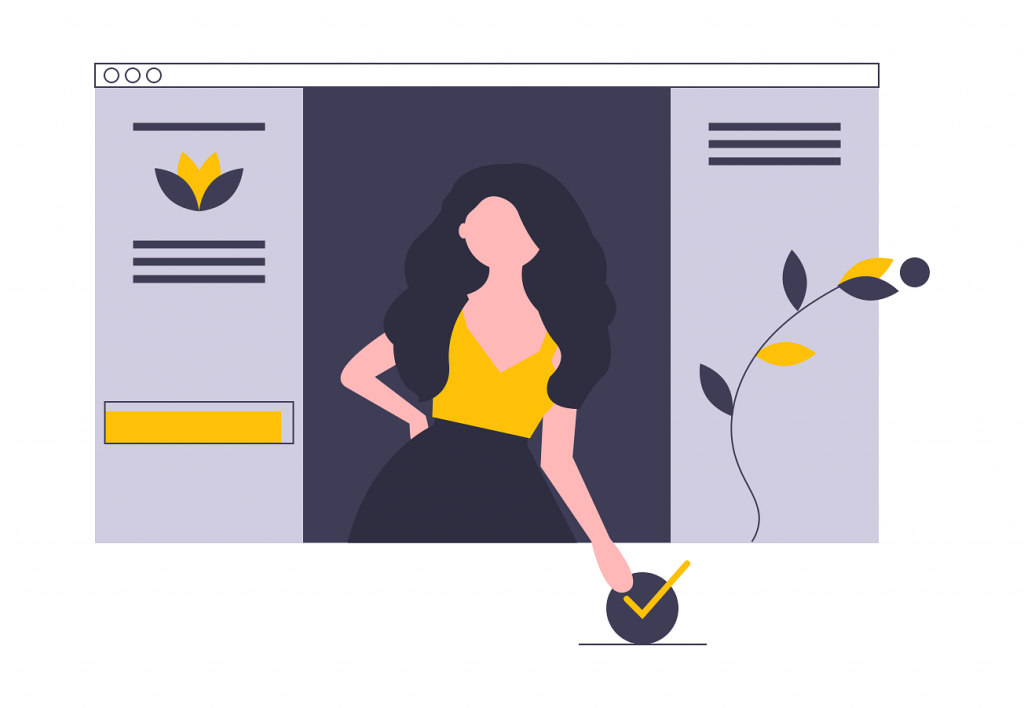
しかし対話となると、少し様相が違います。
異なる価値観や背景を持った人とのやりとりをさすのです。
当然、価値観が異なれば、その背景についての分析や検討が行われます。
その結果、両者の関係がこじれたりすることもありえます。
日本人は対話をうまくできない民族なのかもしれません。
欧米人は激しい議論をした後でも、それが終われば、すぐに関係が元に戻るといいます。
しかし日本人はそう簡単に物事が運びません。
その背景には何があるのか。
日本人特有の忖度などという表現を聞いていると、「対話」というものをするための言葉がないのかもしれないという疑問を持つこともあります。
ことに男女の間などでは、感情を抜きにした対話が成立するのかどうか。
今は、ジェンダー論全盛の時代です。
ここで彼の評論を読んでみましょう。
面白い視点で、非常に新鮮です。
本文
私たちは、今話されている話し言葉一般を空気のように自明のものとして使っているが、その多くは、先人によってつくられた言葉だということを忘れてはならない。
さまざまな話し言葉のカテゴリー、「演説」「スピーチ」「教授」「対論」などはいずれも、明治の人々が、血のにじむような努力で作り出した言葉だ。
旧帝国大学は、最初の10年、ほとんどの授業は、英語か、あるいはドイツ語、フランス語で行われていた。
ただ、しかしここが日本人のすごいところで、たった10年から20年で、多くの授業を教科書も含めて 日本語で行えるようにしてしまった。
今大学生たちは当たり前のように 日本語で授業を受けてノホホンとしているけれど、これは先人の努力のたまものである。(中略)
論理的な事柄を自国語で話せるようにするのには、ある種の知的操作や、それを支える語彙が必要で、自然言語のままでできるものではない。(中略)
ただ、日本語は、英語やフランス語が150年から200年かけて行った、この言語の近代化を、たった30年ほどでほぼ完成してしまった。
その先人の努力に私は深く頭を垂れるが、しかし、その性急な過程では、当然積み残してきてしまったものがあるだろう。
その大きな積み残しの1つが「対話」の言葉ではなかったかと私は考えてきた。
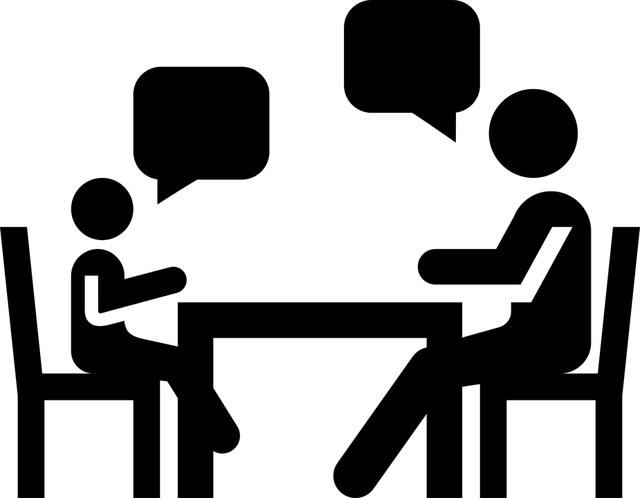
例えば一般によく言われることだが、日本語には対等な関係で褒める語彙が極端に少ない。
上に向かって尊敬の念を示すか、下に向かって褒めてつかわすような言葉は豊富にあっても、対等な関係の褒め言葉があまり見つからないのだ。(中略)
他にも対話の言葉が作られてこなかったために、近代日本語に欠落している要素はいくつもある。
例えば今は女性の上司、男性の部下という関係は珍しくなくなったが、女性の上司が男性の部下に命令する、きちんとした日本語というものはいまだ定着していない。(中略)
新しい時代の新しい女性の話し言葉は今、確実に過渡期にある。
もちろん、言語は常に変化していくものだから、どんな時代でも過渡期と名付けてしまえばそれまでなのだが、それがどこからどこへ向かっての変化なのかを意識することには、多少なりとも意味がある。
この点に関して言えば、現代社会は、ジェンダーや年齢といった区別なく、対等な関係で対話を行うための言葉を生成していく過渡期だと言っていいだろう。(中略)
また言語は、合理性だけで変化するわけでもなく、美の観点もつきまとう。
だからこれを急速に変化させようとすると衝突が起こるし、その変化を人為的に起こそうとするのは危険なことである。(中略)
このように 言語の変化はとても厄介だが、しかし、言語的弱者の立場を考えれば、変革をためらうことも罪悪であろう。
対等な関係で褒める
日本人論の代表的な評論に文化人類学者、中根千枝氏の『タテ社会の人間関係』があります。
どうしても日本人はタテの関係から抜けきれないのですね。
教員になる前、サラリーマンをしていたので、このあたりの感覚はよくわかります。
全く職階のわからない会社を訪問しても、社員同士の呼び方を聞いていれば、どちらが偉いのかはすぐにわかります。
「〇〇君」といえば、そう呼んだ方が目上です。
女性の場合、目下の男性を「○○君」と呼ぶのかどうか。
ぼくの観察では50%くらいでしたね。
まして、対等の関係で褒める言葉というのはあまり耳にしたことがありません。
男女と年齢、職階の差での呼び方が、圧倒的にメインだった記憶があります。
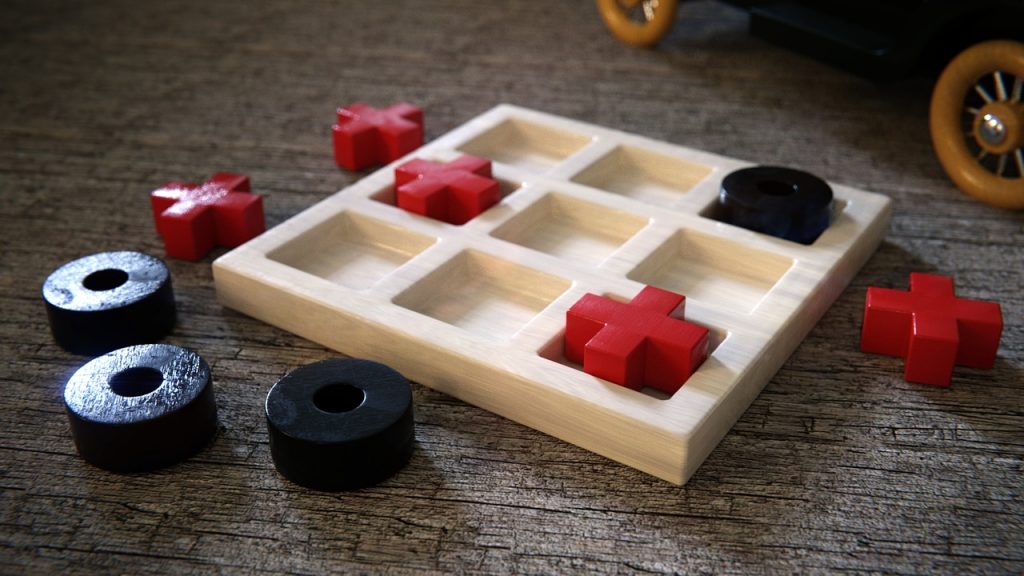
きっとこれからの時代は、そうした関係だけでない呼び方も増えるのでしょう。
差別語も減少するに違いありません。
しかし差別語が消えれば、事実がなくなるというほど、単純ではないです。
マスコミなどはコンプライアンスを前面に出して、駆逐することにエネルギーを注いでいます。
全ての言葉が過渡期だといわれれば、確かにその通りなのかもしれません。
劇作家は舞台上で使われる、たった1つの表現に可能性を託す仕事です。
その意味で、これからの日本語がどう変化していくのか、注視していかなければならないでしょう。
言葉に関するこの視点は、当然小論文のテーマになり得ます。
ぜひ自分の言葉でまとめてみてください。
いい練習になると思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。