俊成の自讃歌
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は鴨長明の歌論書『無名抄』を読みます。
成立は鎌倉時代(1211~1216)と言われています。
中世に歌論書はいくつもありますが、その代表といえるものです。
この段はいくつかのタイトルを持っています。
その中で「おもて歌のこと」をここでは選びました。
他にも「深草の里」「俊成自讃歌のこと」などという表現もあります。
この時代、貴族にとって和歌は命でした。
歌にはあらゆるところにその人の学識があらわれます。
感性の豊かさも垣間見えるのです。
それだけに、学びを深め、感受性を鋭くすることが、強く求められました。
歌論書というのは、たくさんの歌を批評し、どこが最も優れているのか。
その反対に劣っているのはどこかを指摘していく類いの書物です。

さらには歌をつくる時の歌の心得などについても記されています。
いってみれば、どこに主眼をおけばいいのかということです。
たくさんの歌を詠み、そのたびに批評をしてもらうことの大切さを説いています。
しかしそれだけで、誰でもがうまくなるワケではありません。
意外な視点や、新しい言葉など、あらゆるところに目を配っていかなければならないのです。
一朝一夕にできるようなものではなかったのです。
「おもて歌のこと」は、鴨長明とその歌の師匠である俊恵が会話している場面で、前半と後半のニ段落に分けられます。
前半は、俊恵が俊成(五条三位入道)のもとを訪れた時のやりとりの回想です。
誰が何を話しているかがわかりにくい文章です。
後半は、この回想を踏まえて、俊恵がどう思っているかを鴨長明に述べている場面です。
読解は敬語をたよりにしていくしかありません。
古典の最も難しいところですね。
ここに登場する五条三位入道は、藤原俊成(1114~1204)のことです。
百人一首の撰者、藤原定家の父です。
百人一首の83番に彼の代表歌がありますね。
「世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる」がそれです。
原文
俊恵いはく、「五条三位入道のもとに詣でたりしついでに、
『御詠の中には、いづれをか優れたりと思す。よその人さまざまに定め侍れど、それをば用ゐ侍るべからず。まさしく承らんと思ふ。』
と聞こえしかば、
『夕されば野辺の秋風身にしみてうづら鳴くなり深草の里。これをなん、身にとりてはおもて歌と思い給ふる。』
と言はれしを、俊恵またいはく、
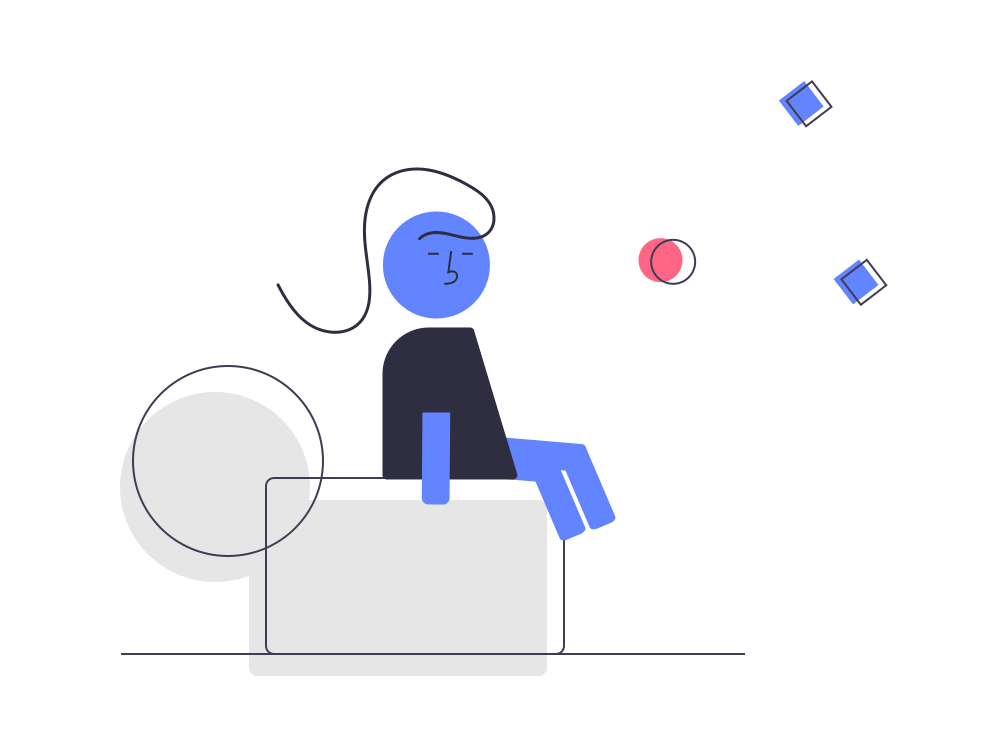
『世にあまねく人の申し侍るは、面影に花の姿を先立てて幾重越え来ぬ峰の白雲。これを優れたるように申し侍るはいかに。』
と聞こゆれば、
『いさ。よそにはさもや定め侍るらん。知り給へず。なほみづからは、先の歌には言ひ比ぶべからず。』とぞ侍りし。」
と語りて、これをうちうちに申ししは、
「かの歌は、『身にしみて』という腰の句いみじう無念におぼゆるなり。
これほどになりぬる歌は、景気を言ひ流して、ただ空に身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくくも優にも侍れ。
いみじう言ひもてゆきて、歌の詮とすべきふしを、さはと言ひ表したれば、むげにこと浅くなりぬる。」
とて、そのついでに、
「わが歌の中には、み吉野の山かき曇り雪降れば麓の里はうち時雨つつ。これをなん、かのたぐひにせんと思う給ふる。
もし世の末に、おぼつかなく言ふ人もあらば、『かくこそ言ひしか。』と語り給へ。」とぞ。
現代語訳
俊恵が言うことには、「(私が)五条三位入道のところに参上した機会に、
『あなたがお詠みになったお歌の中では、どの歌が優れているとお思いになりますか。
他の人はいろいろ論じておりますが、私自身はそれを取り上げようとは思いません。
あなたからじかにうかがいたいと思います」
と申しあげると、
『夕暮れがくると、野原を渡る秋風がしみじみと身にしみて、うずらが鳴いているようだよ、この深草の里では。
この歌を、私としては代表的な和歌と思っております。』
と三位入道殿がおっしゃいましたので、俊恵がまた言うことには、
「世間で広く人が申しておりますことは、

桜花の姿を目の前に思い描き追い求め、幾つの山々を越えて来たことだろう。しかしその度に、花と見まがう白雲が、むこうの峰にかかるのを見るばかりです。
この歌こそが優れているように世間では申しておりますが、どうでしょうか。』
と申しあげると、
『さあ。他の人はそのように論じているのでしょうか。
やはり私としては、先の「夕されば」の歌には言い比べることはできません。』
とご返事がございました。」
と俊恵は語って、これを私に内密に申したことには、
「あの歌は、『身にしみて』という第三句がとても残念に思われるのです。
これほどに完成した歌は、具体的な景色をさらりと詠み表わして、ただ余情として身にしみただろうなと読み手に感じさせるほうが、奥ゆかしく優美です。
『身にしみて』とはっきりと言葉で表現して、歌の主題となるはずのことを、そうであると表現しているので、ひどく情趣が浅くなってしまいました。」
と言って、その機会に、「私(俊恵)の歌の中では、
吉野の山が雲で覆われて雪が降ると、麓の里は冷たい時雨が降っていることです。
この歌を、私の代表的な和歌にしようと思っています。
もし後世、不審なことだと言う人があったならば、私本人が『このように言った。』とお話ください。」と言われたのです。
余情こそが命
俊恵の言おうとしたことが理解できるでしょうか。
非常に大切なことを呟いていますね。
世阿弥の言葉にも通じるような気がします。
「秘せずは花なるべからず」ということです。
全ての感興を書ききってしまうと、そこには余白がありません。
読み手は何も描いていない場に、自分の感情をこめたいものなのです。
そこではじめて、息をつき、感覚を取り戻します。
それを最初に歌の中で、こんな感情をいだきましたと呟いてしまったのでは、本来の味わいから遠ざかってしまうことになります。
正岡子規がなぜ写生句にこだわったのかといえば、ありのままの自然を朗詠することの裏側に、それを読み取る心がみえると信じたからです。
この時にこんな感情だったと言い切ってしまったのでは、読み手の心のゆとりを全て奪ってしまうことになります。
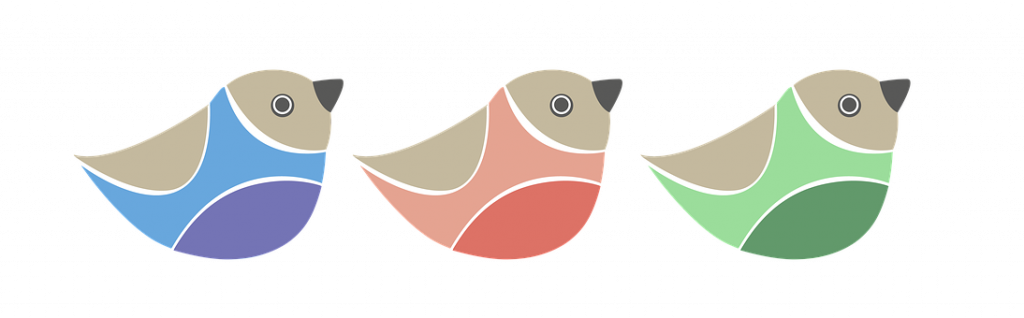
それは絶対に避けるべきだと主張したワケです。
「身にしみて」という言葉があることで、どれほど読み手の感情を損ねてしまうことか。
世阿弥と同じように、やはり秘すことの大切さを同様に論じていますね。
この書物を読んだ貴族たちも、そのことは大切に胸に刻んだことと思います。
しかしそれが実際にすぐ実践できるのかとなると、これは全く別の話です。
やはり感情をついそこに吐露してしまうものなのです。
だからこそ、歌の道は厳しいと言わざるを得ません。
ここで論じられていることは、今日でも同じように通用します。
道を究めることの難しさを、鴨長明はよく知っていた人ですね。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
。


