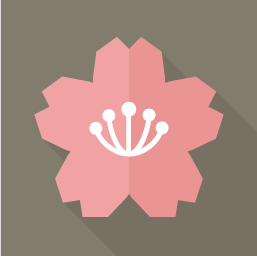木曽の最期
みなさん、こんにちは。
今回も『平家物語』を取り上げます。
教科書にはたくさんの合戦の場面が所収されています。
軍記物語のハイライトは戦さのシーンですからね。
『木曽の最期』『忠度都落ち』『能登殿最期』『先帝入水』。
さまざまな場面が取り上げられています。
合戦のシーンを美しいという言い方には語弊があるでしょう。
凄惨な殺し合いの場面です。
しかし現代のロケット砲を打ち込む戦争とは明らかに違います。
それぞれが名前を名乗りあい、誰と誰が戦うのかということがはっきりしています。
それだけに戦さの様子が目に浮かぶのです。
あたかも講談を聞いているような心地よさにひたってしまいます。
5音と7音のつらなり。

和漢混交文のみごとな構成。
登場人物の名前のみごとさにくわえて、衣装の卓抜さ。
どれもが、スペクタクルの魅力に満ちています。
もちろん、現実は過酷なものでした。
木曽義仲は1183年、平維盛ら10万の大軍を倶利伽羅峠の戦いで破ります。
その後、家来を率い、沿道の勢力を加えて軍勢を増やしつつ京を目指したのです。
入京を果たした後、朝日将軍とよばれ、改めて平家討伐を命じられました。
同時に京都の警備も担当したのです。
しかし都の治安を沈静化させることに失敗してしまいました。
飢餓が続き、京都は荒れていました。
政治を仕切れる部下がいなかったことが致命傷でした。
戦い方は知っていても、戦さが終われば卓抜した行政官が必要になるのです。
信頼回復
義仲は、西国へと平家討伐に向かったものの、いい戦績は残せませんでした。
そこへ現れたのが頼朝の弟、源義経です。
鎌倉から数万の大軍を率いて京にのぼってきました。
後白河法皇は、機を見るに敏な政治家です。
ここで一気に方針転換をしました。
源義経らの鎌倉勢を頼りにすることにしたため、追い詰められた木曽義仲は後白河法皇を捕らえて幽閉してしまいます。
その後は有名な、宇治川の合戦で源範頼、源義経と戦うのです。
しかし時すでに遅し。
北陸へ逃れようとし、寵愛する巴御前をつれて琵琶湖畔まで逃げました。
その時の最後の戦いの様子が、ここに示されています。
巴御前への愛情の示し方も見事です。
さらに壮絶な討ち死にの様子を読むだけで、軍記ものの世界が、身近に感じられます。

表現の美しさが、軍記物語の命ですね。
わずか31年の生涯でした。
残された巴御前はのちに尼となり、越中福光城近くに住んだと言われています。
大原寂光院でその生を終えたと言われている安徳天皇の母、建礼門院などと並べて読むと、中世の女性たちの生きざまにも、思いが広がっていきます。
全文は長いので、代表的なところだけを載せました。
チャンスがあったら、是非すべてを読んでみてください。
『平家物語』は声を出して読まなければダメです。
そのリズムに酔いしれてみましょう。
本文
木曾左馬頭、その日の装束には、赤地の錦の直垂(ひれたれ)に唐綾威(からあやおどし)の鎧着て、鍬形(くわがた)打つたる甲の緒締め、厳物(いかもの)作りの大太刀はき、石打ちの矢の、その日のいくさに射て少々残つたるを、頭高に負ひなし、滋籐(しげどう)の弓もつて、聞こゆる木曾の鬼葦毛(おにあしげ)といふ馬の、きはめて太うたくましいに、金覆輪(きんぷくりん)の鞍置いてぞ乗つたりける。
鐙(あぶみ)踏んばり立ちあがり、大音声(だいおんじょう)をあげて名のりけるは、
「昔は聞きけん物を、木曾の冠者、今は見るらむ、左馬頭兼伊予守、朝日の将軍源義仲ぞや。甲斐の一条次郎とこそ聞け。互ひによい敵ぞ。義仲討つて、兵衛佐に見せよや。」
とて、をめいて駆く。
一条の次郎、
「ただ今名のるのは大将軍ぞ。あますな者ども、もらすな若党、討てや。」
とて、大勢の中に取りこめて、われ討つ取らんとぞ進みける。
木曾三百余騎、六千余騎が中を縦様・横様・蜘蛛手・十文字に駆け割つて、後ろへつつと出でたれば、五十騎ばかりになりにけり。
そこを破つて行くほどに、土肥次郎実平、二千余騎でささへたり。
それをも破つて行くほどに、あそこでは四、五百騎、ここでは二、三百騎、百四、五十騎、百騎ばかりが中を駆け割り駆け割り行くほどに、主従五騎ほどにぞなりにける。
五騎がうちまで巴(ともえ)は討たれざれけり。
木曾殿、
「おのれは、疾う疾う(とうとう)、女なれば、いづちへも行け。われは討ち死にせんと思ふなり。もし人手にかからば自害をせんずれば、木曾殿の最後のいくさに、女を具せられたりけりなんど、いはれん事も、しかるべからず。」
とのたまひけれども、なほ落ちも行かざりけるが、あまりに言はれ奉つて、
「あつぱれ、よからう敵がな。最後のいくさして見せ奉らん。」
とて、控へたるところに、武蔵の国に聞こえたる大力、御田八郎師重、三十騎ばかりで出で来たり。
巴、その中へ駆け入り、御田八郎に押し並べて、むずと取つて引き落とし、わが乗つたる鞍の前輪に押し付けて、ちつともはたらかさず、首ねぢ切つて捨ててんげり。
そののち、物脱ぎ捨て、東国の方へ落ちぞ行く。
手塚太郎討ち死にす。
手塚別当落ちにけり。
今井四郎、木曾殿、主従二騎になつてのたまひけるは、
「日ごろは何とも覚えぬ鎧が今日は重うなつたるぞや。」(中略)

木曽殿はただ一騎、粟津の松原へ駆け給ふが、正月二十一日、入相(いりあい)ばかりのことなるに、薄氷は張つたりけり、深田ありとも知らずして、馬をざつと打ち入れたれば、馬の頭も見えざりけり。
あふれどもあふれども、打てども打てども働かず。
今井が行方のおぼつかなさに、ふり仰ぎ給へる内甲(うちかぶと)を、三浦の石田次郎為久、追つかかつてよつ引いて、ひやうふつと射る。
痛手なれば、真っ向を馬の頭に当ててうつ伏し給へるところに、石田が郎等二人落ち合うて、遂に木曽殿の首をば取つてんげり。
太刀の先に貫き、高く差し上げ、大音声(だいおんじょう)を挙げて、
「この日ごろ日本国に聞こえさせ給ひつる木曽殿をば、三浦の石田次郎為久が討ち奉つたるぞや。」
と名乗りければ、今井四郎いくさしけるが、これを聞き、
「今は誰をかばはんとてか、いくさをもすべき。これを見給へ、東国の殿ばら、日本一の剛の者の自害する手本。」
とて、太刀の先を口に含み、馬より逆さまに飛び落ち、貫かつてぞ失せにける。
さてこそ粟津のいくさはなかりけれ。
現代語訳
木曾左馬頭、その日の装束としては、赤池の錦の直垂に唐綾威の鎧を着て、鍬形を打ちつけた甲の緒を締め、いかめしく立派に見えるように造った太刀を腰につけ、石打ちの矢で、その日の合戦に射て少々残ったのを、頭より高く突き出るように背負い、滋籐の弓を持って、有名な木曾の鬼葦毛という馬で、非常に太くたくましいのに、金で縁取りした鞍を置いて乗っていた。
木曾殿は今井がどうなったかが気がかりで、振り向いて顔をおあげなさった甲の内側を、三浦の石田次郎為久が、追いついて弓を十分に引き絞って、ひょうふっと射る。
義仲は重傷なので、甲の鉢の前面を馬の頭に当ててうつ伏しなさった所に、石田の家来二人が駆けつけて、とうとう木曾殿の首を取ってしまった。

首を太刀の先に貫いて、高く差し上げ、大声をあげて、
「近頃日本国に有名でいらっしゃった木曾殿を、三浦の石田次郎為久がお討ち申しあげたぞ。」
と名乗ったので、今井四郎は敵と戦っていたが、これを聞き、
「今となっては誰かをかばおうとして、戦いをする必要があろうか。これをご覧なされ、東国の方々よ、日本一の剛毅な者が自害する手本だ。」
と言って、太刀の先を口に含み、馬から逆さまに飛び落ち、太刀に貫かれて死んでしまった。
無常の世界
壮絶なシーンですね。
乳母子(めのとご)というのは、幼い時から同じ乳母の乳を飲んで育った子という意味です。
兄弟同然に育ったのです。
今井四郎という幼い頃からの義兄弟と討ち死にできて、義仲は幸せだったのかもしれません。

しかし同じ源氏同士がこのように戦いをしなくてはならないという非情さは最後まで残ります。
政争の持つ厳しい現実かもしれません。
やがて頼朝と義経の兄弟も争い、天下をとった頼朝も3代しか続きませんでした。
まさに無常を絵に描いたような世界が、この本には縦横に示されているのです。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。