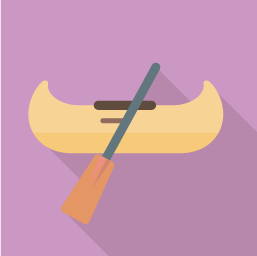わかりあい察する文化
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は「わかりあう文化」というタイトルで平田オリザの評論を取り上げたいと思います。
平田オリザという人をご存知でしょうか。
1962年生まれの劇作家であり演出家でもあります。
彼の芝居は静かな演劇と呼ばれています。
ほとんど動きがないのです。
そして山がありません。
演劇には必ずクライマックスシーンというのがあるものです。
しかし平田オリザの芝居にはそれがないのです。
最初から最後まで日常の風景が続きます。
よく言われることですが、セリフが重なります。
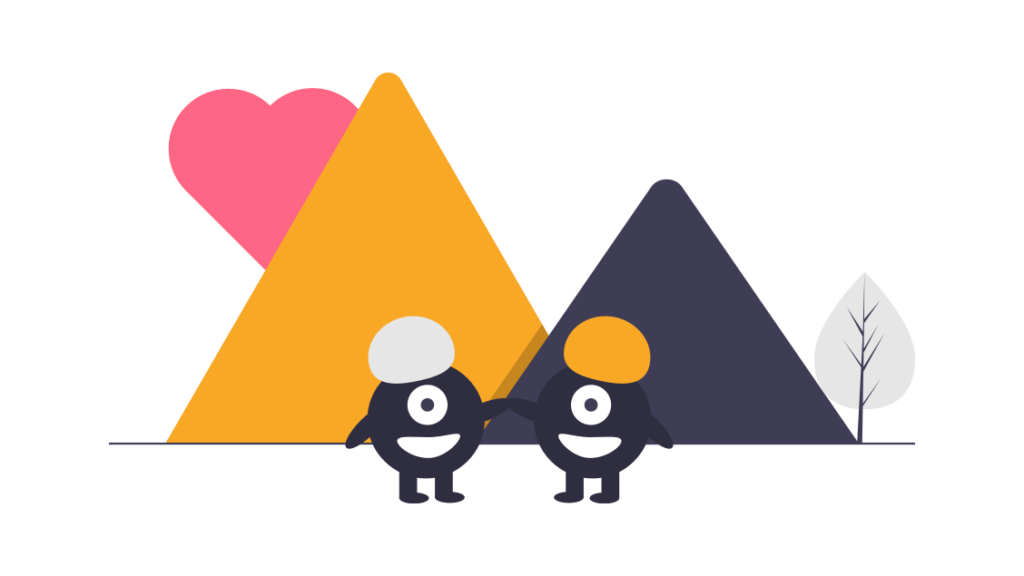
普通、芝居の場合は1人が喋ると他の人は黙るのです。
ところが彼の創り出す演劇は同時に何人もの人が口を開くシーンが象徴的に出てきます。
それはつまり私たちの日常がいつも片方が喋ると片方が黙るというものではないと言う彼の基本的な考え方から成り立っています。
今回はコミュニケーションの能力とは何かということが問題です。
最初の部分を読んでみましょう。
————————–
日本社会には「対話」という概念が希薄である。
いや、それがほとんどなかったと言ってもいいかもしれない。
これは仕方のない側面もある。
一般に、日本社会はほぼ等質の価値観や生活習慣を持った者同士の集合体=ムラ社会を基本として構成され、その中で独自の文化を培ってきたと言われてきた。(中略)
私はこのような日本社会独特のコミュニケーション文化を、「わかりあう文化」「察しあう文化」と呼んできた。
ヨーロッパとの対比
日本文化の特徴をみごとに述べていますね。
当然のことながら比較するべきものがこの後に登場します。
それがヨーロッパの文化です。
その部分を少しだけ読んでみましょう。
————————–
一方、ヨーロッパは、異なる宗教や価値観が、陸続きに隣り合わせているために、自分が何を愛し、何を憎み、どんな能力を持って社会に貢献できるかを、きちんと他者に言葉で説明できなければ無能の烙印を押されるような社会を形成してきた。
これを私は「説明しあう文化」と呼んでいる。
両者はそれぞれが独立した文化体系であるから、どちらが正しいとかどちらが優れているということはない。
—————————
これが彼の基本的な彼の考え方ですね。
日本はここにもある通り「わかりあう文化」「察し合う文化」というのが基本です。
ですから、逆にこれをうまく使って日本は近代国家に這い上がってきたということは言えます。
戦前の日本の発展もそうですし、戦後の経済復興もそうです。

とにかく余計なことを言わずに察し合い、口には出さずに前へ進むというコミュニケーションの形をとってきました。
これは日本特有の形です。
悪いとか良いとかいうレベルではないでしょう。
以心伝心という言葉があります。
まさに相手の気持ちを理解し、察し合ってコミュニケーションを取ってきました。
しかしこれからの時代はどうでしょうか。
グローバル社会を生きていくために、すべてを阿吽の呼吸で乗り切るなどということはもう考えられません。
逆に言うとこれからの社会は全く違う価値観の人たちと対等に理解しあい、それぞれの能力を示しながら進む必要があるのです。
互いの文化の特徴を誇りを持って語り合える人材が必要です。
そういう能力を身につけた人間だけが生き残れるということになるのではないでしょうか。
味気なさの覚悟
これからは分かり合う文化という日本の烙印をかなぐり捨てる覚悟も必要です。
論理できちんと説明しあう。
言葉を正確に使いこなす。
そういったスキルを持った人だけが、活躍する時代が来るに違いありません。
同じような価値観を持ち、同じような生活習慣を持った日本文化のような均質性は世界的にはもうかなりの少数派です。
これからの若者たちはそういう意味で、非常に難しい時代を生き抜かなければなりません。
説明すればするほど味気なくなくなることも当然あるでしょうね。
例えば俳句などはそのいい例です。
わずか17文字の中に全ての感情を織り込まなければいけません。
「古池や蛙飛び込む水の音」という芭蕉の句があります。
この蛙は一体何匹なのか。

どういう古池なのか。
飛び込み方はどんなだったのか。
そんなこといちいち説明していたのでは、歌の味わいがなくなってしまいます。
しかしそれでもこれからの時代は説明しなくてはなりません。
味気なさを少々味わうという犠牲を払ってでも、他者とコミュニケーションを取り続けなくてはならないのです。
平田オリザの芝居は「東京ノート」「S高原から」などさまざまな作品があります。
特にドラマとしての盛り上がりがあるワケではありません。
シェイクスピアやチェーホフの時代ではないのです。
特別に殺人がおこることもありません。
桜の園が切り倒されるワケでもないのです。
日常の空虚さ
それぞれの人がどのように他者とつながり合うのかということについて、私たちは新しいフェーズに差しかかっているのかもしれません。
そのための身体表現も必要でしょう。
見方によっては退屈な日常でもあります。
しかしリアリティを共有するというのは、そういう長い時間の空虚に耐えることなのかもしれません。
何を待っても、何もやってこない。
それでも人は生き続けなくてはならないのです。
つねに論理を片手に持ち、言葉をきちんと使いこなし、他者と共有する。
かつては互いに目をみれば、何がいいたいのかわかったのでしょう。
しかし今は発言しなければなりません。
必ず相手が理解できる文脈まで下りて行って説明するのです。

どんなに退屈であっても、興覚めしても、それを行わなければなりません。
それがグローバルな時代を生きるということなのです。
平田オリザの評論を読んでいて、これだけの覚悟をもって芝居を演出していたのだということがよくわかりました。
『演劇入門』(講談社)などの新書もあります。
これを機会に手にとってみてください。
陸続きの国同士でさえ、互いの理解には言葉が必要でした。
今の日本にとって言葉の価値は増すばかりです。
論理の組み立てを明確にできなければ生き残れません。
難しい時代に入りました。
今回も最後までおつきあいいただきありがとうございました。