男こそ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は男と女について考えます。
これはある意味、永遠の話ですね。
1000年前の『枕草子』にも男女の関係を書いた一節があります。
ちょっと読んでみましょう。
国語の授業で習った人がいるかもしれません。
教師の側からいえば、この内容を教室で取り扱うのはかなり難しいかもしれません。
—————————–
本文
男こそ、なほいとありがたくあやしきここちしたるものはあれ。
いと清げなる人を捨てて、憎げなる人を持たるもあやしかし。
公(おほやけ)所に入り立ちする男、家の子などは、あるが中によからむをこそは、選(え)りて思ひたまはめ。

及ぶまじからむきはをだに、めでたしと思はむを、死ぬばかりも思ひかかれかし。
人の娘、まだ見ぬ人などをも、よしと聞くをこそは、いかでとも思ふなれ。
かつ女の目にもわろしと思ふを思ふは、いかなることにかあらむ。
かたちいとよく、心もをかしき人の、手もよう書き、歌もあはれによみて、恨みおこせなどするを、返りごとはさかしらにうちするものから、寄りつかず、らうたげにうち嘆きてゐたるを、見捨てて行きなどするは、あさましう、公腹(おほやけばら)立ちて、見証(けんそ)のここちも心憂く見ゆべけれど、身の上にては、つゆ心苦しさを思ひ知らぬよ。
現代語訳
男という生き物は、何とも奇妙な心を持っているものですね。
たいそう美しい女性を捨てて、醜い女を妻としているのもおかしなことです。
朝廷に出入りする男やその一族などは、数多くある女性の中からとくに美しい人を選んで愛したらよいのに、そうでもないのです。
相手が自分には及びもつかない高貴な身分の女性であっても、すばらしいと思うのなら命を懸けてでも自分のものにすればいいのにね。
そんな話はほとんどありません。
そのくせ、誰かの娘とか、まだ見たこともない未婚の女性などで、美しいと聞けば、どうにかしてわがものにしたいと思うもののようです。
そこまで熱心に言い寄ろうとするのに、女であるわたしの目から見てもたいしたことのない女性を愛するのは、どういうわけなのでしょうか。
顔かたちがとてもよく、気立てもいいし、字もきれいに書き、歌も趣き豊かに詠む人が、手紙などで恨み言を言ってきたとしましょう。
そういう時も、多くの男性は返事だけしかしません。

女性のもとへは寄りつきもしないのです。
女性がいじらしく嘆いていても、見捨てて他の人のところへ行ったりするのは、あまりのひどさにあきれてしまいます。
人ごとながら腹が立ちますね。
傍目にもわびしく見えるのに、男の人は自分自身のふるまいについて、少しも相手の女性の辛さなど意識していないものなのです。
いい女性の条件
清少納言の考えていたいい女性というのはどういう人のことなんでしょうか。
彼女の価値観がよく出たこの段落からさぐってみます。
やっぱり第1は容姿ですね。
現在とは随分違います。

お雛様の人形をイメージすればいいのかもしれません。
近頃のは目がパッチリしていますけど、ああいうのじゃありません。
切れ長ですっと横に長い目です。
俗に引目と呼ばれていました。
さらに小さな鼻と口
ふっくらした頬
もっと大切なのは長い艶やかな黒髪ですね。
これは必須条件でした。
教養は大切
その次がやさしい心遣い、性格の良さですね。
さらに言えば、文字の美しさ、和歌の巧みさなどです。
いずれも学ばなければ身につかないことばかりです。
今ならばなんでしょうか。
生活力のあるなしが前面にでてくるのかもしれません。
清少納言はしきりにいい女を選ばないで、男たちはどこかおかしいのではないかとなじっています。
美しい女性に好かれているのに、その人を棄てて、別の女性に行くというのがわからないと呟いているのです。

まさか彼女が自分のことを言っていたとも思えません。
しかし案外ホンネはそのあたりにあったのかもしれません。
もっと深読みをすれば、仕えていた中宮定子をイメージして書いたとも考えられます。
あとから宮中に乗り込んできた藤原道長の娘、彰子とも天皇は結婚しています。
清少納言からみれば、定子の方が数段女性としてはすぐれているのは明らかなのです。
それなのに帝はその良さがわからないのか。
彼女に寂しい思いをさせる天皇の存在がイヤだったのかもしれません。
清少納言自身のことでないとしたら、そういう考えがあってもおかしくはありません。
美徳のよろめき
ところでこの男女の様子をみていて、つい三島由紀夫の小説を思いだしてしまいました。
『美徳のよろめき』がそれです。
タイトルからしてものすごいですね。
お読みになったことがありますか。
1957年に出版された小説です。
一言でいえば人妻の姦通を描いた作品です。
フランスの心理小説の影響を強く受けているといわれています。
28歳の節子は、親の決めた男性と結婚し男の子も1人います。
しかしそれだけでは人生に満足が得られませんでした。
その結果、別の男性との恋に落ちます。
土屋という男と密会を重ねていくうちに、彼女は肉体的にも深い快楽を覚えていきます。
それと同時に夫の子、土屋の子を次々と中絶するという心身の傷まで負うのです。
その手術をうける日、たまたま土屋が別の女性と会っていたことを知り、深い嫉妬を覚えます。
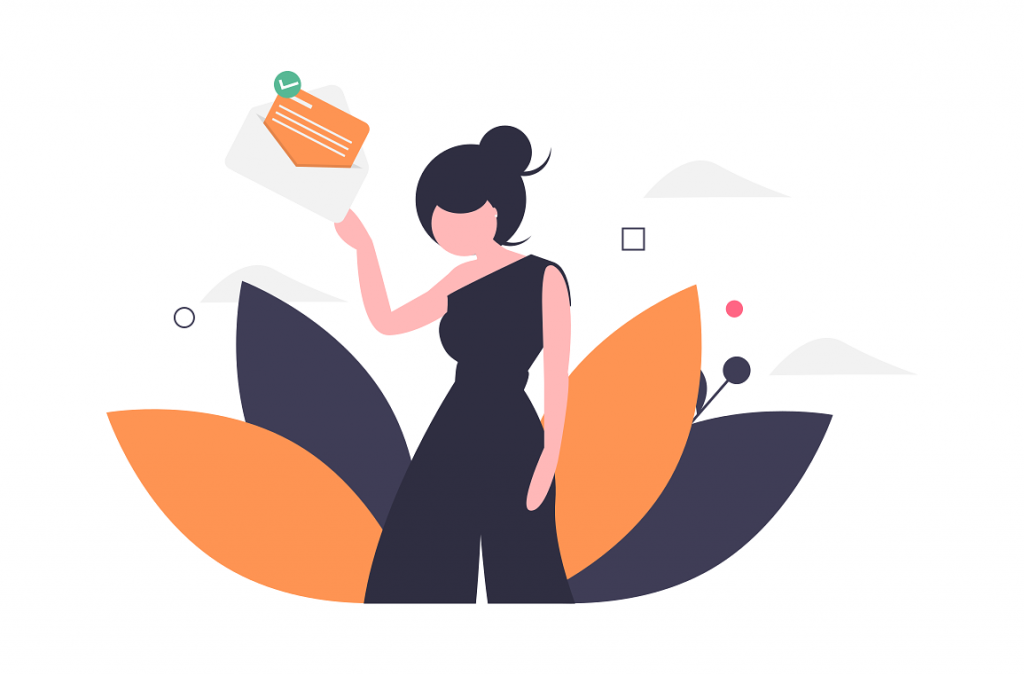
結局、節子は土屋に今までの苦しみを話し、別れを切り出すことにしました。
土屋は別れを待っていたかのような態度をとります。
その様子を見て、彼女の苦しさは再び増すのです。
身分を隠して、何人かの人生経験者に相談してみたものの、なんの解決にも至りません。
つまりは自分で解決する以外に道はないことを知るのです。
土屋宛ての手紙を書き、翌朝、それを破り捨ててしまいます。
どれほど愛していたのかを知った時はもう遅かったということを綴り、破って捨てるという行為は何を意味しているのでしょうか。
男と女は解決のつかない道をたどったにしても、結局は不可能をその内側に秘めた存在なのかもしれません。
これを男性の側からみれば、『枕草子』の世界そのものですね。
女性の側からみれば、道綱の母が書いた『蜻蛉日記』になってしまうかもしれません。
つまり男女の関係は永遠に解決しない無限ループの中にあるのです。
『枕草子』のこの段を読んだ時、すぐに三島由紀夫を連想したのはなぜでしょうか。
自分でも不思議です。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。


