人・本・旅
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は無意識のうちに宿ってしまう偏見について考えます。
アンコンシャス・バイアスと呼ばれるものです。
意識しているのなら、学びを続けることで排除することも可能でしょう。
しかし無意識下で行われるは排除は厄介です。
人間はどのようなプロセスを経て成長していくものなのでしょうか。
誰でもが多くの悩み、苦しみを抜け、やがて明るい未来にたどりつければ幸いだと考えます。
若い時の苦難は宝の山にたとえられることもあるくらいです。
しかし挫折があまりにも深ければ、立ち直るのは容易ではありません。
その間、長い人生の中で意識しないうちに偏見を持ってしまうこともあります。

環境による格差も大きいですしね。
今回は立命館アジア太平洋大学元学長・出口治明氏の文章を参考にします。
「自分の頭で自由に考えられる人」になるためには、自分の中にある「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見)を克服しなければならないというのがその文章の中核です。
そのためには、「人・本・旅」を通して学ぶことが大切だというのが彼の主張なのです。
非常にわかりやすい文章ですが、内容は深く、それぞれの領域について考えをまとめていくのは、なかなか大変です。
自分の体験や感想などを含めて書けば、制限字数にすぐ達してしまうでしょう。
それだけに構成が難しいです。
3つのポイントの割合をどのようにするのかを考えなくてはなりません。
1つの領域を拡大し、残りをさりげなくまとめるという方法もあります。
課題文を読んで、自分なりに最善の方法を探ってみてください。
本文
「人」
たくさんの人と出会い、多くの考え方や価値観、文化に触れることです。
多様性に触れることで、自分の幅も広がっていきます。
人間は、他人から学ぶ生き物です。
自分とはちがうタイプの人と触れあい、考えを吸収することで、多くの刺激と学びを得られます。
その中できっと、自分で思ってもいなかったアンコンシャス・バイアスにも気づくでしょう。
反省することも、膝を打つこともあるでしょう。
そうした経験があなたを、より知的でより豊かな人間にしていくはずです。
人から学び、影響を受け、世界を広げることができるのです。
似たような考え方、価値観、経済力を持った人々が集まっている場(同質集団)は、たのしく快適ではありますが、刺激や学びはあまり多くありません。
こうした集団では、アンコンシャス・バイアスがより強化されてしまう傾向にあります。
「よい」と思うもの、「悪い」と思うものといったさまざまな価値観が似通ってくるからです。
だからこそバイアスを外し、考える力をつけるためには、意識して「いつもと違う人」と会う必要があるのです。
学校や会社を飛び出し、「自分とは違う『当たり前』を持っている人」とコミュニケーションを取る努力をする、その姿勢が大切です。
「本」

ぼくがこれまでの75年間で学んだことの総量を100とすると、50は本から得てきたと自負しています(残りは「人」「旅」で25ずつです)。
物心ついてから本を開かなかった日は一日たりともありませんし、いままで1万冊以上の本に親しんできました。
本は、先人の知恵の結晶です。
本に触れてさえいれば、仮にいま生きている社会でアンコンシャス・バイアスを植え付けられたとしても、ひどく凝り固まった人間にはならないと僕は思っています。
だって、本を開けば、たとえば古代ギリシャの考え方に触れ、中世の宗教観を学び遠い異国の歴史や制度を知り、異なる文化で暮らす人の機微に触れることができるわけでしょう。
知らなかったことを知り、新しい考えに触れ、世界が広がっていく感覚を得られる。
自分がいかにものを知らなかったか、狭い世界で生きているのか、思い知らされるのです。
「旅」
僕が考える「旅」は、「自分の足で現場に行くこと」全般を意味します。
自分の足で移動して、自分の目でものごとを見て、経験する。
これが旅の本質です。
たとえばみなさんがテレビを見ていて、家から少し離れた街においしいパン屋さんがあることを知りました。
このときどれだけレポーターが詳しく説明しても、おいしそうな断面図がズームアップされても、味の想像には限界があります。
足を運び、店に入り、香りを吸い込み、おいしさを体験しなければその真髄は理解できません。
でも足を運べば、それが体験になり、知識となり、血肉となる。
つまり、隣町のパン屋さんに足を運ぶことも、立派な旅なのです。
いまはインターネットで、世界中の情報をいくらでも仕入れることができます。
「YouTubeでリアルな映像を見ることができるから、海外に行く必要はない」と考える人も少なくないと聞きました。
しかし、その意見に僕は反対です。
万里の長城をテレビで見るのと実際にその上に立つのでは、得られる情報量は段違いです。
自分を揺るがし、成長させる刺激は、現場でしか体験できないのです。
問題
次の文章を読み、「自分の頭で自由に考えられる人」になるために、3つの要素はどのような意味を持つと考えますか。
あなたの体験とからめて800字以内で書きなさい。
3つの視点についてどうまとめればいいのか、しばらく考えてみましょう。
➀「人」人との交流を通じて多様性に触れ、似た集団から意識して離れること
②「本」本を読むことで古今の賢人の知恵や異文化の考え方を学び視野を広げること
③「旅」旅を通して現場に足を運び、実体験を得ること

これらの要素はすべて、自己を成長させ、固定観念から解放されるための刺激と学びを与える行為であると説かれています。
この問いに対して、3つの柱からどれをメインにするのか考えてみます。
大切なポイントは自分の体験を中心に論述することです。
その記述がなければ、著しく減点されるのは明らかです。
3つのテーマと自己の体験との関係をどう制限字数内にまとめるか。
かなりの構成力が必要なことはいうまでもありません。
見ることは知ること
じっくり読めば読むほど、どの要素も必要なものだということがよくわかります。
それだけに3つをうまく配分して書かなければなりません。
しかしそれだけではやや、単調な論文になってしまうような気がしますね。
ここが一番のネックです。
この中で1つだけピックアップするとすれば、あなたは何をとりますか。
ここでは1つの例として「旅」をあげてみましょう。
多くの経験をしていない人にとって、とにかく見ることが最大の栄養源であることは間違いないと考えられます。
見ることは知ることに通じるというのは誰もが知っている諺です。
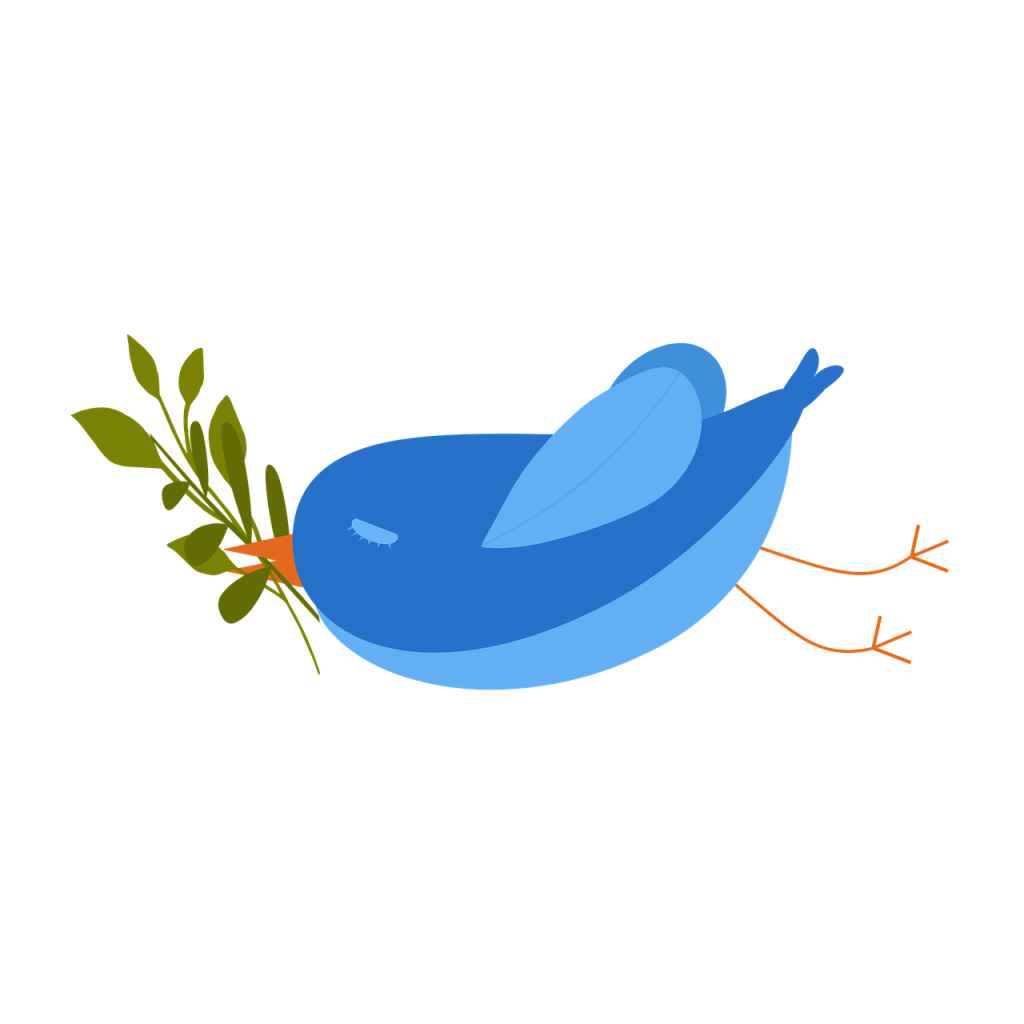
「百聞は一見に如かず」とはよくいったものです。
かつて作家の小田実は『なんでも見てみてやろう』という本を書きました。
彼はとにかく見ること、体験することに最大の重点を置いたのです。
考えるのは後でいい。
整理し、認識する以前にまず見ることを最大の眼目にしました。
小田実は世界中を旅し、自分の目で見ました。
何を見たのか。
経験の深化
彼は地球上にうごめく多くの人びとに出会いました。
困った時にはフルブライト留学生の立場を縦横に使い切り、各国の大使館などにも駆け込みました。
そのあとで、起こった事象を考え整理し、認識を深めたのです。
世界の構図を自分なりに見て取りました。
出口氏の考える「旅」と小田実の体験は深いところで合致しているのではないでしょうか。
別の表現でいえば、「経験」そのものの深化です。
できたらあなたも自分の体験を200字程度でまとめてください。
読書についてでもかまいません。

もちろん、人との出会いで劇的に人生が変化したという体験も意味があります。
そこで何を得たのか。
それを書くことで評価が高くなるはずです。
3つの要素を全て同じ重さでまとめるのは難しいので、バランスをとることを勧めます。
構成力が命です。
内容が書きやすいだけに、経験と内容との齟齬がなければ、いい評価になると思われます。
ぜひトライしてみてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。


