夢応の鯉魚
みなさん、こんにちは
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は上田秋成の『雨月物語』を扱います。
この本には怪異な話が9作載っています。
この「夢応の鯉魚」もその中の1つです。
「夢応」とは夢の中で感じ応じる行動をさします。
外からの刺激によって心が深く感じた後の様子を示しているのです。
主人公は魚の絵を得意とし、時には画を描きながら眠ってしまうこともありました。
琵琶湖に小舟を出して、漁師から買った魚をすぐに水に放して、その泳ぐさまを絵に描いたりもしました。
興義はその後、病気で急死してしまいます。
その三日後に蘇生して、檀家の一人にある話を始めます。
自分が死んでからの話です。
彼は夢を見ていたというのです。
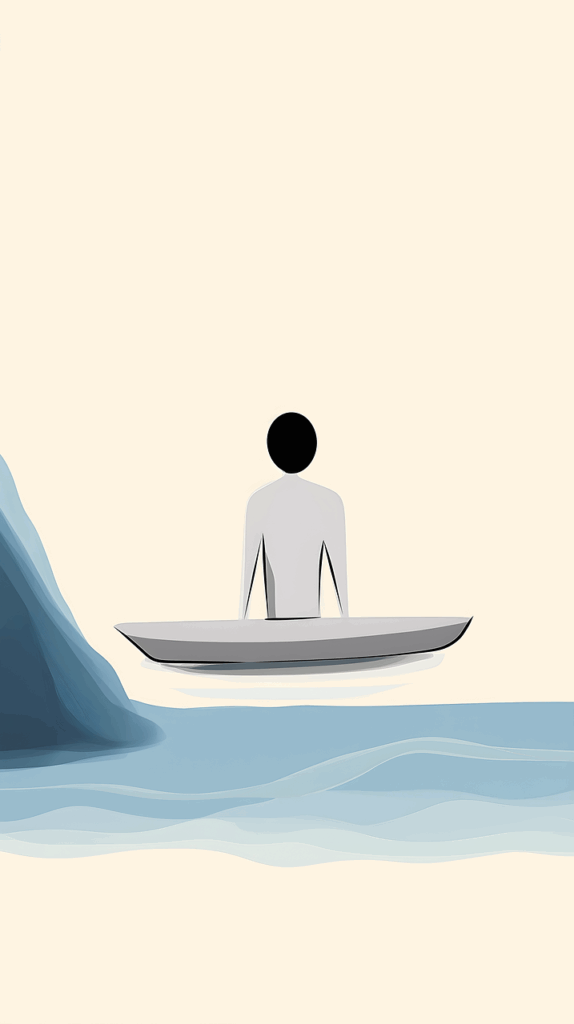
興義は一匹の鯉に生まれ変わっていました。
やがて漁師に釣り上げられ、その檀家の家で膾(なます)にするために料理されることになってしまいます。
ところが命を取られるまさに寸前で、目が覚めたのだというのです。
最も印象的なのは、欲望に負けて釣り針にかかり、殺される恐怖が描かれるくだりではないでしょうか。
「魚になって悠々と泳ぎたい」という望みをかなえてもらったところまではいいことばかりでした。
しかし釣り糸にかかって身を滅ぼしてしまいそうになるところからは悲劇そのものです。
ひどい空腹を感じたその瞬間、知り合いの漁師が釣りをしているのに出会うのです。
釣り上げられてしまった興義は慌てふためき、漁師に向かって叫びます。
しかし声が届くはずもありません。
とうとうまな板の上に乗せられたとき、キラリと光る刀の先が目に入ります。
とうとう切られると思ったその瞬間、目が覚めたのです。
江戸時代の小説としてはかなり特異な創作ではないでしょうか。
中国の『魚服記』を題材として書き上げた作品です。
なぜこのような小話を発表したのでしょうか
経歴をみてみると、この人が実にユニークだったということがよくわかります。
40才近くまでは俳諧にひたり、その後医者になり、さらに国学者として研究を始めました。
当時の文化人だったということがわかります。
本居宣長と論争したことなどでも有名です。
本文
急にも飢ゑて食(もの)ほしげなるに、彼此(をちこち)に求食(あさ)り得ずして狂ひゆくほどに、忽ち文四が釣りを垂(たる)るにあふ。
其の餌(ゑ)ははなはだ香(かんば)し。
心又河伯(かはのかみ)の戒(いまし)めを守りて思ふ。
我は仏の御弟子なり。
しばし食を求め得ずとも、なぞもあさましく魚の餌(ゑ)を飲むべきとてそこを去る。
しばしありて飢ゑますます甚(はなはだ)しければ、かさねて思ふに、今は堪へがたし。
たとへこの餌を飲むとも鳴呼(をこ)に捕られんやは。
もとより他(かれ)は相識る)ものなれば、何のはばかりやあらんとて遂ひに餌をのむ。
文四はやく糸を収めて我を捕ふ。
『こはいかにするぞ』と叫びぬれども、他(かれ)かって聞かず顔にもてなして縄をもて我が腮(あぎと)を貫ぬき、芦間に船を繋ぎ、我を籠に押し入れて、君が門に進み入る。
君は賢弟と南面の間に奕(えき)して遊ばせ給ふ。

掃守(かもり)傍に侍りて菓(このみ)を啗(くら)ふ。
文四が持て来し大魚を見て人々大ひに感でさせ給ふ。
我、其のとき人々にむかひ、声をはり上げて、『旁(かたがた)等は興義(こうぎ)を忘れ給ふか。宥(ゆる)させ給へ寺に帰させ給へ』と連(しき)りに叫びぬれど人々しらぬ形(さま)にもてなして、只手を拍(うつ)て喜び給ふ。
鱠手(かしはびと)なるもの、まづ我が両目を左手の指にてつよくとらへ、右手に礪(とぎ)すませし刀をとりて俎板(まないた)にのぼし既に切るべかりしとき、我苦しさのあまりに大声をあげて、『仏弟子を害する例やある。我を助けよ、我を助けよ』と哭叫びぬれど、聞き入れず。
終に切らるるとおぼえて夢醒たり」とかたる。
人々大いに感異(めであや)しみ、「師が物がたりにつきて思ふに、其の度ごとに魚の口の動(うご)くを見れど、更に声出だす事なし、かかる事まのあたりに見しこそいと不思議なれ」とて、従者を家に走しめて残れる鱠(なます)を湖に捨てさせけり。
現代語訳
急にお腹が減って、食べ物が欲しくなり、あちこちと食い求めたが、ありつけません。
いらいらして泳いでいくうちに、たちまち文四が釣り糸を垂れているのに出会いました。
その餌はとてもいい匂いがしていたのです。
しかし心のうちで水神が言われた戒めを思い出して、私は仏様の弟子であるということを深く思いました。
しばらく餌を取らなかったからといって、どうして魚の餌をのみこむことができようかと思い、そこを立ち去ったのです。
やがてますます腹が減り、もう我慢できなくなりました。
たとえこの餌をのみこんでも愚かにも捕らわれることがあるだろうか。
以前から文四とは顔見知りでもあり、何の遠慮をする必要があろうかととうとう餌を口に入れたのです。
文四は素早く釣り糸を巻き上げ、私を捕えました。
『これはどうしたことか』と叫んでみましたが、文四はまるで知らぬ顔をしています。
縄で私のえらを貫き、芦間に船を繋ぎ、私を籠に押し入れて、貴殿の門に入りました。
貴殿は、弟君と南向きの面座敷で碁を打っておられたました。

掃守はその傍で果物を食べていたのです。
文四が持って来た大魚を見て、そこにいる人たちはたいへん喜ばれました。
わたしは其の時、皆さんに向って大声をあげたのです。
皆さんはこの興義をお忘れになったのですか。寺に帰してください。
何度も繰り返し叫びましたが、皆さんは知らん顔で、手を打って喜んでおられました。
料理人がまず、私の両目を左手の指で強くおさえ、右手に研ぎ澄ませた包丁を取りました。
俎板に私をのせ、今にも切ろうとしたときのことです。
私は苦しさのあまり大声を上げました。
『仏に仕える僧を殺すことがあるのでしょうか。私を助けてください』
泣き叫んでみましたが、聞いてはもらえませんでした。
終に切られると思ったその瞬間、夢が覚めたのです」と語りました。
人々は、大いに感じ入ったようです。
師僧のお話を思い合わせてみると、声をたてられたというその度ごとに口が動くのを見ました。
しかしいっこうに声を出すことはありませんでした。
このような事を目の前で見たということこそ、たいへん不思議な事だといいあって、助の殿は供の者を家に走らせ、残りの鱠(なます)を残らず捨てさせたということでした。
人間の罪業
この小説は魚の視点からの筆致が実に鮮やかですね。
まさに魚の世界を見ているようだとでもいえばいいのでしょうか。
古歌の歌枕などが盛り込まれた美しい文体で描かれています。
この作品にはさまざまなテーマが重層的に組み込まれています。
しかし一番の主題は人が生きることの持つ罪悪ということではないでしょうか。
この小説のクライマックスは膾(なます)にされそうになって切り殺される瞬間の鯉の視線です。
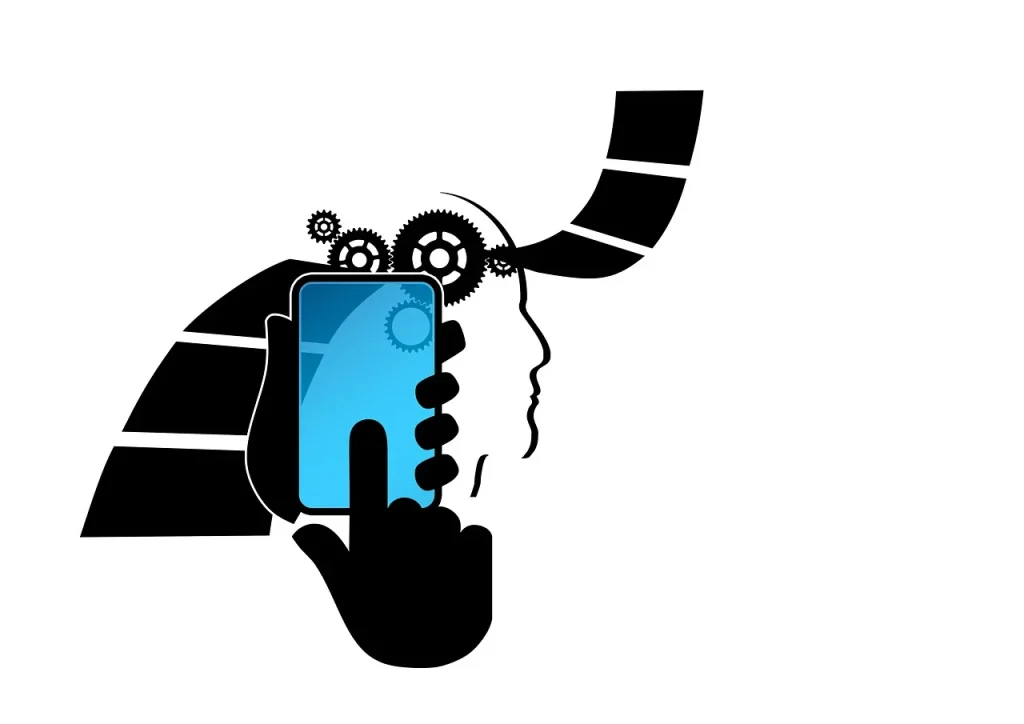
大きな口を開けて叫ぶものの、誰の耳にもその声が届きません。
人が生きるということは、他の生物を殺すことを意味します。
通常はその事実に目をつぶっています。
しかしある瞬間に、日常的な行為である殺生の持つ罪悪性を意識するのです。
魚は自由に水の中を泳ぎますが、空腹を覚えた瞬間に釣り糸に食いつきます。
結局は捕獲され、殺されそうになります。
これは、現実がどこまでも我々を襲い続けるという業から逃れられないという事実をさしています。
完全な自由というものが、存在しないという現実は厳然たる真理ということなのです。
あなたはどう考えますか。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


