言葉を超えるもの
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
たくさんの外国人が日本にやってくる時代になりました。
同様に外国で暮らしている日本人も多くいます。
日々の生活において言葉は非常に大切な伝達手段です。
突然、道を訊ねられたりしたとき、とまどってしまった経験を持つ人も多いはずです。
相手の話していることが分からないというのは苦しいですからね。
もちろん、自分の言葉が伝わらない、というのもつらいです。
スマホなどの機器があるとはいえ、単語やフレーズなどを知っていれば、簡単に自分の意志を伝えられるのにと感じる機会は多くあります。
どんなに勉強しても、知らない言葉は山のようにあります。
本当にことばがまったくわからない時、わたしたちはどうするのか。
言葉を超えて、伝達をするために必要な手段とはなにか。
それを考えてみたいと思いました。

コミュ力が今ほど重要だと言われている時代はありません。
入社試験においても最大の眼目です。
ここでは文化人類学における協操作的行為(コ・オペラティブ・アクション)という考え方について考察してみます。
コミュニケーションにとって必要なものは、言語能力だけなのかというのが、キーポイントです。
この文章を読み、よりよいコミュニケーションはどのようなものかを700字以内で述べよというのが、入試の問題として出題されました。
話し手の言語能力だけでなく、話し手と聞き手の両者が、ことばという記号を共に「操作」する作業がいかに大切かというところに焦点を絞りきれたかが、問題になります。
筆者は文化人類学者の西浦まどかさんです。
課題文
文化人類学を学ぶ学生として、インドネシアに約1年、アメリカに約2年、滞在しました。
こう話すとしばしば、「インドネシア語/英語が話せるんですか?」と訊かれます。
このとき、私はこう答えます。
「あんまり話せません。でも、コミュニケーションはできます」と。
外国暮らしにおいて、言語は大問題です。
相手のことばが分からない、自分のことばが伝わらない、というのは、非常に苦しいもの。
どんなに勉強しても、知らないことばや間違えは次から次に出てきます。
自分の存在が、非常に幼く、無力になった気分の連続です。
そのような中で出会ったのが、アメリカの言語人類学者チャールズ・グッドウィンの、「コ・オペラティブ・アクション(協操作的行為)」という考え方でした。

彼の著作には、チルという人物が出てきます。
チルは脳の一部を損傷し、「Yes」「No」「And」の3語しか話せなくなってしまいました。
しかし周囲の人びとがチルに話しかけ、チルは彼らの発言に対して様々な音調で応えることで、彼はたった三語でも独立した話し手として会話に参加している、とグッドウィンは論じます。
コミュニケーションは、話し手の言語能力だけでなく、話し手と聞き手の両者が、ことばという記号を共に「操作」し、意味を定めていくことなのです。
この考えは、外国で言語に悩む私を勇気づけました。
もちろん、その言語を知れば知るほど染み出す深みもあるでしょう。
しかし、ひとや世界と関わることは、必ずしも「正しい言語」を通してだけではありません。
相手の発することばの手ざわりを一つ一つ受け止めながら、それを共に操作=協力すること。
それがコミュニケーションの重要な一面なのではないでしょうか。
日本ではよく、英語をはじめとする外国語を話せない、という言う人がいます。
もしあなたもそうだったら、代わりにこう言うのはどうでしょうか。
「あまり話せません。でも、コミュニケーションはできます」と。
西浦まどか(2024)「外国語とコミュニケーション」『ユリイカ』
外国語とコミュニケーション
インドネシアとアメリカでの滞在経験から、多くの発見があったことがよくわかりますね。
ポイントはただひとつです。
言語能力とコミュニケーション能力は必ずしも同義ではない、ということです。
その考えのもとになるのが、彼女自身の考えの骨格になる次の論点です。
すなわち脳損傷により限られた言葉しか話せない人物の話がそれです。
チャールズ・グッドウィンの「コ・オペラティブ・アクション(協操作的行為)」の研究はぼく自身もはじめて知りました。
コミュニケーションとは話し手と聞き手の両者による言葉の共同操作であるという事実です。
そこからことばが十分に話せないとしても「コミュニケーションはできる」と捉え直す提案が読み取れます。
言葉の「正しさ」だけでなく、相手との相互作用の重要性を説いているからです。
ここで「ことばの相互作用」という表現を簡単に使ってしまいました。
具体的にはどのようなことなのでしょうか。
筆者の文章にれば、話し手と聞き手の双方が、言葉という記号を共に「操作」し、意味を定めていくとしています。

たった3つの表現しか知らない人が、周囲の人々の発言に対して様々な音調で応えるとはどういうことなのでしょうか。
心の中の言葉と他者と伝達する言葉は、互いに影響し合い、行動を促す力を持っています。
相手への言葉かけや、心の中で自分に語りかける言も相互作用に関わっています。
つまりことばの相互作用とは、言葉が人々の思いや行動に影響を与え、それらがまた言葉を生み出すという役割を持っているのです。
その場で相互に協力しながら、意味を作り出していきます。
もちろん、ジェスチャーや言葉の抑揚なども大きな材料になるのです。
その繰り返しの中で、たとえ語彙が少ないにしても、意味ある行動に結びつき、他者と意味をとりあうことが可能になるというワケです。
体験の共有
この文章では筆者自身の外国での経験が大きな意味を持っています。
ことばの壁に苦しみながらも、「あんまり話せません。でも、コミュニケーションはできます」と答えることができたのは、自身の体験が持つ重みがあるからです。
文章を書き上げる時、これと似たようなことが自分にあるのかどうか。
それを考えることも大きな意味をもっているのではないでしょうか。
いくら流暢に言葉が話せても、それで他者とコミュニケーションができるのかどうかというのはかなり難しい問題です。
むしろ話し手と聞き手の間の相互作用と協力がコミュニケーションの核心であることを示唆しているからです。
筆者自身も言葉が通じない苦しさや自分の存在が無力になった気分を経験しました。
それでも人間は協操作的行為ができれば、他者と通じ合うことができるのです。
より良いコミュニケーションとは、相手が発することばの「手ざわり」を一つ一つ受け止めるのが最初の段階です。
次にそれを共に相手と操作し、協力することなのてす。
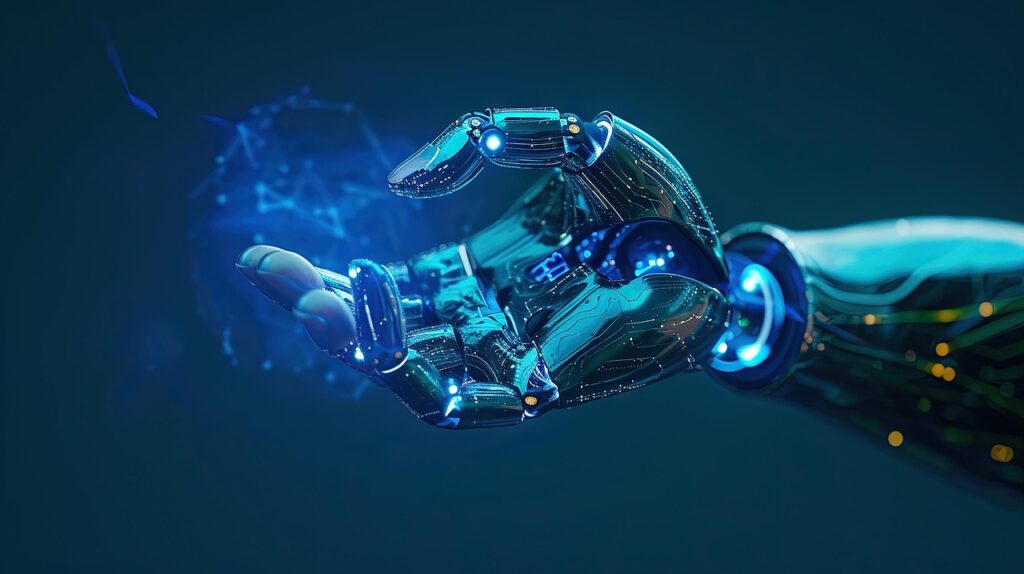
人と世界と関わることは、必ずしも「正しい言語」を通してだけではありません。
この協調的な姿勢の方がずっと大切なのです。
それが繋がりを築く上で極めて重要な要素だからです。
言語能力に自信がなくても「コミュニケーションはできる」という考え方をとることはできるはずです。
積極的に他者と関わり、共に意味を作り出していく姿勢こそが、理想的なコミュニケーションになりうる可能性に満ちています。
コミュニケーションのポイントは、言語能力という個人のスキルだけに負うのではありません。
双方向的で協調的なプロセスが大切なのです。
もちろん、言葉の量や質を高めることに意味がないということではありません。
語彙が豊かであることは意義深いことです。
さらにいえば、外国語以外に母語どうしで、うまくコミュニケーションがとれない時も、慌てずに他者と通じ合うためのプロセスを積み上げていくことの意味があるのではないでしょうか。
言葉の周辺にあるものの、手触りを大切にするということが、最も大切なのです。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうこざいました。


