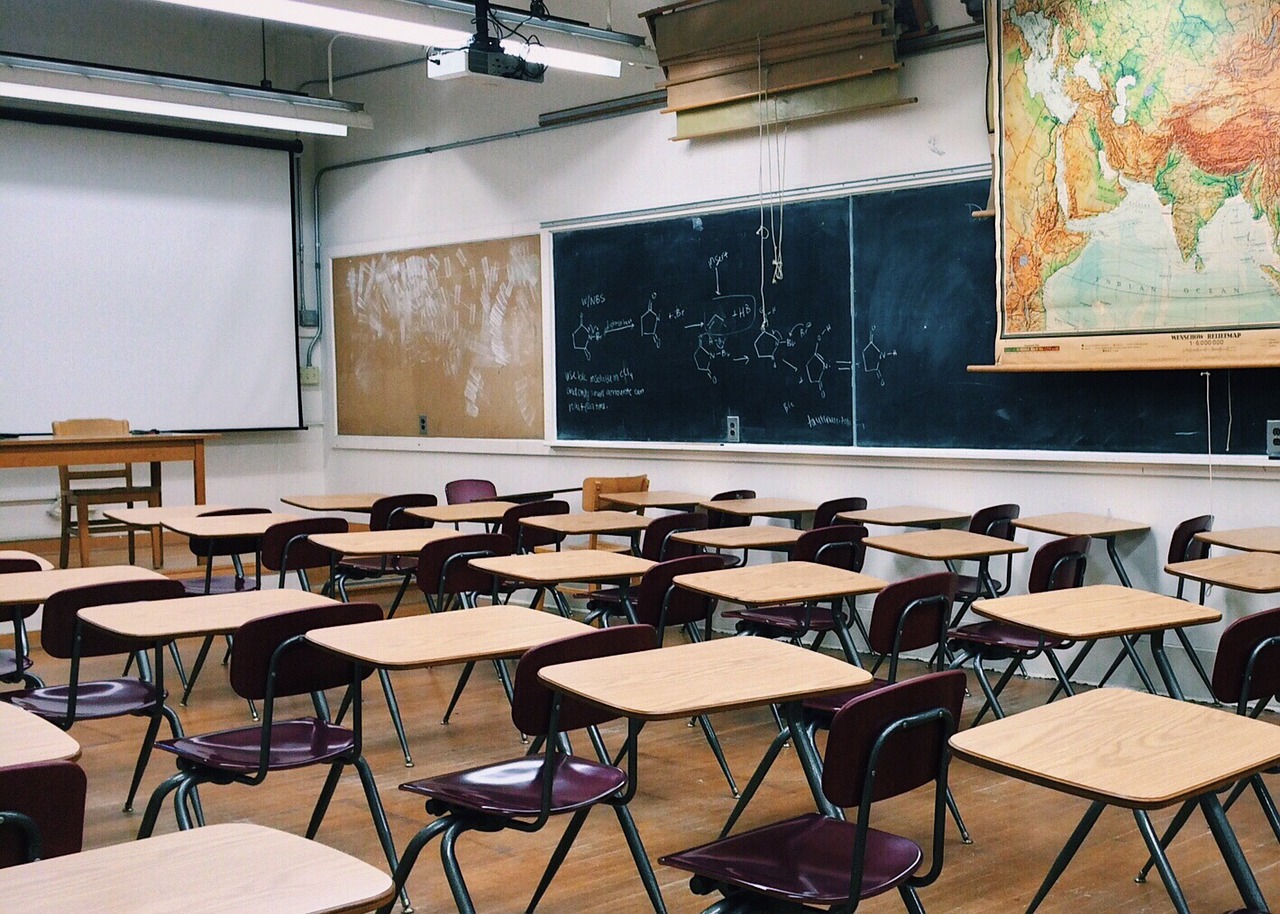教師の職制
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
学校というところは不思議なところです。
生徒からみれば、みんな先生ですが、実態は各層に分かれています。
一番、わかりやすいのが管理職ですね。
校長の上には統括校長などという職制もあります。
副校長は以前、教頭といいました。
厳密にいうと、仕事の内容は違います。
その下にいるのが主幹教諭、主任教諭などです。
今度新しく、主務教諭というのもできるとか。
その下にヒラの教諭もいます。
当然、報酬もそれぞれ違います。
手当がつきますのでね。

事務には統括事務長などという職制まであります。
今回の話題はプロパーの教員についてではありません。
それ以外の「先生」と呼ばれる人たちです。
「時間講師」の先生の存在は誰もがよく知っていますね。
授業の時間だけ、生徒とかかわりを持つ教師です。
いろいろなタイプの方がいます。
大学院で専門領域の研究をしている若い先生もアルバイトで来ていたりします。
ぼく自身、都立高校の教員をリタイアした後、近隣の市の高校へ講師として3年間、通いました。
ところで学校にはそれ以外にも先生はいます。
それが「臨時任用」の教師です。
一般に「りんにん」と呼ばれています。
1年間単位で任用される先生です。
臨時任用の教師
実は都立高校に在任しているとき、臨任の先生にはお目にかかりませんでした。
いなかったのです。
皆さん、プロパーの先生だけでした。
非正規の教員はいなかったのです。
そういう教師の存在を見るようになったのは、講師として退職後通い始めた学校ででした。
60歳で定年を終えた後、嘱託の形で残っている教員は都立にもいました。
彼らは65歳までの5年間は異動後の学校に勤務することが約束されていたのです。
しかし「臨任」の先生は全く彼らとは違っていました。
勤務は1年単位なのです。
生徒は当然、同じ教員として見ています。
どういう人が多かったのか。
単純にいえば、採用試験に合格せず、そのまま臨時雇いになって、捲土重来を期すタイプの人です。
翌年、再び試験をうけるのです。

自治体によっては、ある程度の点数をとっていれば翌年の一次試験を免除してくれるケースもあります。
特に体育科などは、今も競争が厳しいです。
教員希望者が激減しているとはいえ、卒業後すぐ現場に教員として立てる人はそれほど多くありません。
音楽、美術なども1人職種なので、大変です。
彼らは非常勤講師の口があれば、少しでもコネをもっておくために、少ないコマ数でも喜んで働きます。
「臨任」ならば、なお条件がいいです。
給料も確実にもらえ、1年間フルに働けるのです。
その間に分掌の仕事や、行事に参加してノウハウを学ぶことができます。
授業だけをする講師に比べて、翌年の採用試験で有利になると考えてもおかしくはありません。
小学校では担任も
幸いなことに高校ではある程度の研究時間もとれ、空いたコマには自分なりの勉強もできます。
つらいのは小学校です。
少ない教員数でやりくりしているので、非正規といえども仕事の量はかわりません。
担任までもたされることもあるのです。
親からみれば、彼らも先生です。
まさか、臨時雇いの非正規の先生だなどとは思いません。
新人教師のために初任者研修制度もあることはあります。
しかしその対象はプロパーの教員だけです。
「臨任」にはありません。
職場の先輩に聞きながら、真似をして覚えていく以外に方法はありません。

クラスが崩壊しかかっても、すぐに助けを求めるわけにはいかないのです。
誰もが手いっぱいで、忙しいです。
最近は各学期ごとに管理職と面談をし、そのたびに書類を提出しなければいけません。
自分がやりたいこと、やれたこと、やれなかったことなどを自己申告書にまとめるのです。
そのためにかなりの時間を取られます。
その他に授業の準備、採点などもあります。
中学、高校では定期試験をつくり、採点をし、評価をします。
そこまでやっても、翌年同じ学校にいられるかどうかの保証はありません。
その間に翌年の採用試験のための勉強もしなくてはならないのです。
雇止めの恐怖感は「ブラック」な職場のイメージを増幅させます。
教員志望者激減
非正規教員の存在について、詳しく知っている人はそれほどいないのが実態です。
それだけにこの話題はなかなか浸透しないのかもしれません。
「臨任」の先生自身もはやくプロパーになりたい意識が強く、我慢を強いられます。
クラブの顧問なども引き受け、休日が機能しなくなる人もいます。
さらに少子化の影響を受けて、生徒数の減少が深刻です。
都会では私立の中学や高校に進む生徒もかなりいます。
教育委員会は毎年、入学者数を把握するのが難しいのです。
各自治体もなるべく正規の教員を増やしたいのが本音です。
特別支援学級も多くなっていますからね。

しかしあまりに新卒の教員を増やしすぎると、年齢構成がうまくいかなくなる怖れもあるのです。
50代の教師が定年退職を迎えた後、そこに大きな穴ができてしまうのも避けたいのが本音です。
ぼく自身の経験でいうと、定年後に勤めた高校では1度に4人もの「臨任」を雇止めにしたことがありました。
対象は中堅として働いていた40代の先生方でした。
彼らはその後、どうなったのか。
なんの情報もありません。
知り合いのツテをもとめて、どこかの私立高校へ異動できたのでしょうか。
生徒にはもちろん何も知らせません。
おそらく新年度の始業式に、退職を告げただけのことだろうと想像します。
プロパーの教師は再任用を望めば、退職後65歳まで働けるシステムに今はなりつつあります。
定年延長も視野に入っています。
現役時代よりはかなり低い給料で雇えるようになるでしょう。
教員志望者の減少は、ニュースの定番になりました。
ブラックな職場で、それでも頑張っている非正規教員は、全国で10万人を超えています。
それ以外、学校には部活動指導員、スクールサポーター、学習支援員、カウンセラーなどの非正規員も存在しています。
養護教諭もプロパーだけではありません。
「臨任」の人もいます。
会計年度任用職員という名称で自治体などから送り込まれている事務職もいます。
昨今では多忙化の原因の1つとされるICT教育も複雑になりつつあります。
タブレットを全員が持っているため、陰湿なイジメなども発生しやすい環境です。
「チーム」としてまとまらなければ、とてもやってはいけないというところまで追い詰められているのが、今の学校なのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。