陰翳礼讃
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は作家、谷崎潤一郎(1886~1965年)の『陰翳礼讃』(いんえいらいさん)を読みます。
彼のエッセイの中でも珠玉の作品ですね。
読むたびに、思わず唸ってしまいます。
日本人の美意識の細部が、実感としてよくわかります。
何もかもが明るい電灯の下にさらされる現代にとって、かつての明治の暮らしがどのようなものであったのか。
谷崎潤一郎の著作で唯一教科書に入っているのが、この随筆なのです。
小説は今まで見かけたことがありません。
授業で取り上げてみたいと思った作品はありますが、それもかないませんでした。
過激な内容の作品が多いのも、谷崎文学の特徴です。

しかしそれが卓越した感性によって覆われているため、「美」に昇華しているのです。
一般には「耽美主義」といわれ、学校の文化とはそぐわなかったということなのでしょうか。
スキャンダラスな作品がよく取り上げられますが、それが全てだというわけではありません。
『痴人の愛』『春琴抄』『細雪』などのほか、『少将滋幹の母』『吉野葛』など好きな作品がたくさんあります。
『細雪』などは何度読んでも新鮮ですね。
映画や舞台などで触れたことがあるという人も、多いのではないでしょうか。
今回取り上げる『陰翳礼讃』は、彼の随筆の中でも出色のものです。
日本の美がどのような背景から生まれたのかということを、丹念に追いかけた随筆です。
日本橋人形町で生まれた谷崎は、関東大震災の後、関西に移住しました
そこから次第に日本の古典へ回帰していったのです。
日本にあった陰翳の事実を、これだけ明確に論じた作品はありません。
京都を中心とする日本の文化の粋がよく理解できます。
中で彼は、町家と呼ばれる日本の古い家屋を詳しく観察しています。
このエッセイが発表されたのは1933年。
急速に近代化される生活様式に対する焦燥も見て取れます。
彼の美意識がそれを許さなかったのでしょう。
本文
京都に「わらんじや」と云う有名な料理屋があって、ここの家では近頃まで客間に電燈をともさず、古風な燭台を使うのが名物になっていたが、ことしの春、久しぶりで行ってみると、いつの間にか行燈式の電燈を使うようになっている。
いつからこうしたのかと聞くと、去年からこれにいたしました。
蝋燭の灯ではあまり暗すぎると仰っしゃるお客様が多いものでござりますから、拠んどころなくこう云う風に致しましたが、やはり昔のまゝの方がよいと仰っしゃるお方には、燭台を持って参りますと云う。
「わらんじや」の座敷と云うのは四畳半ぐらいの小じんまりした茶席であって、床柱や天井なども黒光りに光っているから、行燈式の電燈でも勿論暗い感じがする。
が、それを一層暗い燭台に改めて、その穂のゆらゆらとまたたく蔭にある膳や椀を視詰めていると、それらの塗り物の沼のような深さと厚みとを持ったつやが、全く今までとは違った魅力を帯び出して来るのを発見する。
そしてわれわれの祖先がうるしと云う塗料を見出し、それを塗った器物の色沢に愛着を覚えたことの偶然でないのを知るのである。(中略)
「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云っていい。
今日では白漆と云うようなものも出来たけれども、昔からある漆器の肌は、黒か、茶か、赤であって、それは幾重もの「闇」が堆積した色であり、周囲を包む暗黒の中から必然的に生れ出たもののように思える。(中略)
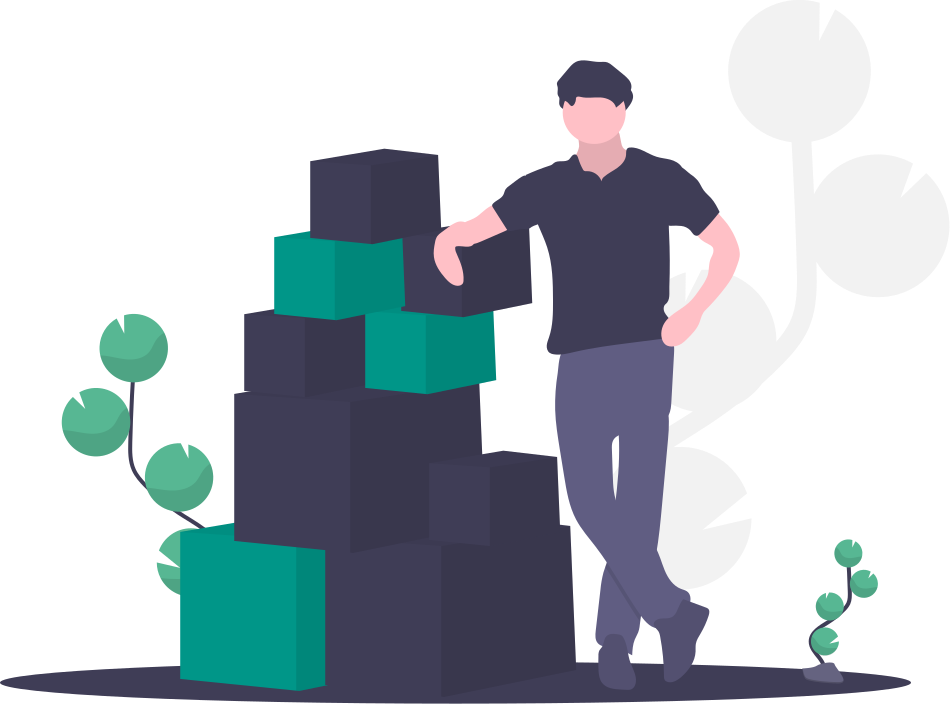
そして、あのピカピカ光る肌のつやも、暗い所に置いてみると、それがともし火の穂のゆらめきを映し、静かな部屋にもおりおり風のおとずれのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込む。
もしあの陰鬱な室内に漆器と云うものがなかったなら、蝋燭や燈明の醸し出す怪しい光りの夢の世界が、その灯のはためきが打っている夜の脈搏が、どんなに魅力を減殺されることであろう。(中略)
漆器の椀のいいことは、まずその蓋を取って、口に持って行くまでの間、暗い奥深い底の方に、容器の色と殆ど違わない液体が音もなく澱んでいるのを眺めた瞬間の気持である。
人は、その椀の中の闇に何があるかを見分けることは出来ないが、汁がゆるやかに動揺するのを手の上に感じ、椀の縁ふちがほんのり汗を掻いているので、そこから湯気が立ち昇りつゝあることを知り、その湯気が運ぶ匂に依って口に啣ふくむ前にぼんやり味わいを豫覚する。
その瞬間の心持、スープを浅い白ちゃけた皿に入れて出す西洋流に比べて何と云う相違か。
それは一種の神秘であり、禅味であるとも云えなくはない。
東洋の美意識
この文章を読んでいて感じるのは、東洋の美と西洋のそれが全く異質なものだということです。
確かに古民家などを見学していても、暗い部屋が多いことに驚かされます。
障子や襖で部屋を区切り、明かりと呼べるものはわずかです。
昔の人はどうやって本を読んだのでしょうか。
書見などというのは、よほど恵まれた人の所作には違いありません。
しかし秋の夜長に書を読むには、それなりの光がなくてはならなかったはずです。
谷崎は日本の漆器の美しさについて、かなりの字数を使っています。
こういう視点で描き出された漆器の描写は、なかったのではないでしょうか。
ぼんやりした薄明りの中に置いてこそ、発揮される美があるということも、この文章が教えてくれました。

茶室などの明かりの取り方も、独特なものがありますね。
濃淡の光が差し込む中で、茶を飲む文化の良さも味わえるに違いないのです。
自然の風光の中に、人もあたりまえのように存在しているというのが、美そのものなのでしょう。
極端に光を取り入れて、その場を照らすというのは、どう考えても日本人の感性の外にあるものなのかもしれません。
科学技術の発展などとも大きな関係があるでしょう。
照明も暖房も、日本では自然にあるもので、全てまかなってきました。
直接なものを嫌う文化もそれに付随しています。
木や紙をうまく生活に取り込んでいったことも、陰翳と大きな関係を持っているはずです。
自然との一体化
谷崎潤一郎がなぜここまで、日本の美にこだわったのか。
その背景には抗うことのできない、西洋化の流れがあったからです。
特に関東大震災で、ほとんどの家が瓦解し、その後に建てられる家は、明治の建築物とは一線を画すものでした。
もう過去の日本はそこから消えかかっていたのです。
彼は絶望的な気分に襲われたはずです。

『源氏物語』を翻訳し、中世の雅びの世界を脳裡に思い描いていたところに、近代が突如襲いかかってきました。
どうしても関西に逃げ、さらに京都の古い町並みの中に、自分の美の故郷を求めざるを得なかったのでしょう。
近代文明は明るさを求めすぎたのかもしれません。
それに疲れた人間は、どこで心の安寧を得たらよかったのか
音も光もあまりに膨張しすぎた結果、温かみのある暗闇へ抜け出そうとした人々がいたということです。
その1つの例が、漆器や金蒔絵の道具だったのです。
「陰翳」のある家屋の中でしか映えない、不思議な世界です。
さまざまな生活道具の装飾は、そうした装置の中でしか生き残れなくなりつつありました。
谷崎の直観は鋭かったというしかありません。
これからの時代にこのエッセイの持つ意味は、どのようなものなのでしょうか。
ある意味、近代文明に対する警鐘ともとれます。
エネルギーを消費するだけの現代社会は、やがて確実に崩壊していくでしょう。
今以上の光が得られるとは、どうしても思えないからです。
作家の感性は、鋭くその先まで見つめていたに相違ありません。
そこには救いがあるのでしょうか。
ぜひ、あなたも考えてみてください。
全文が「青空文庫」で読めます。
谷崎の他の作品に触れてください。
王朝の美もそこにはあるのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


