狩りの使ひ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『伊勢物語』を読みます。
伊勢斎宮の話です。
御存知ですか。
斎王とは、伊勢の伊勢神宮または京都の賀茂神社に奉仕する天皇の未婚の娘(皇女や内親王)や、玄孫までの女王(にょおう)のことをさします。
2つの神社に仕える聖なる存在です。
伊勢神宮は斎宮、賀茂神社は斎院と呼び分けました。
斎王になると、宮中に定められた初斎院に入り、翌年の秋に都の郊外の野宮(ののみや)に移り潔斎の日々を送り身を清めたのです。
その翌年9月に、伊勢神宮の神嘗祭(かんなめさい)に合わせて都を旅立ちました。
斎宮の話は『伊勢物語』という題名の由来となっているとも言われています。
天照大神に仕える聖なる存在であるだけに、男性たちにとっては結界を超えた別枠の存在だったのです。
斎宮の座をおりるのは、天皇が崩御するか譲位した時、または斎宮の母親が病気の時に限られました。

それくらい厳しい戒律があったのです。
古典文学にも伊勢の斎宮は多く描かれています。
特によく知られているのは『源氏物語』ですね。
六条御息所の娘が伊勢の斎宮として下る際、京都嵯峨野の野々宮神社に光源氏が六条御息所を見送りに行く場面が有名です。
六条御息所は、源氏の正妻、葵上に対して、すさまじい確執を持っていました。
生霊になって葵上を襲った場面は、能にもなっています。
その斎宮がこの物語では、自分から在原業平と言われる男に会おうとしているのです。
かなりスリリングな展開だと言わざるを得ません。
本文
昔、男ありけり。
その男、伊勢の国に狩りの使ひに行きけるに、かの伊勢の斎宮なりける人の親、
「常の使ひよりは、この人よくいたはれ。」と言ひやれりければ、親の言なりければ、いとねむごろにいたはりけり。
朝には狩りに出だし立ててやり、夕さりは帰りつつ、そこに来させけり。
かくて、ねむごろにいたつきけり。
二日といふ夜、男、われて、「逢はむ」と言ふ。
女もはた、いと逢はじとも思へらず。
されど、人目繁ければ、え逢はず。
使ひざねとある人なれば、遠くも宿さず。
女の閨近くありければ、女、人を静めて、子一つばかりに、男のもとに来たりけり。
男はた、寝られざりければ、外の方を見出だして臥せるに、月のおぼろなるに、小さき童を先に立てて、人立てり。
男、いとうれしくて、わが寝る所に率て入りて、子一つより丑三つまであるに、まだ何事も語らはぬに帰りにけり。
男、いと悲しくて、寝ずなりにけり。
つとめて、いぶかしけれど、わが人をやるべきにしあらねば、いと心もとなくて待ちをれば、明け離れてしばしあるに、女のもとより、詞はなくて、
君や来し我や行きけむ思ほえず 夢かうつつか寝てか覚めてか

男、いといたう泣きて詠める、
かきくらす心の闇に惑ひにき 夢うつつとは今宵定めよ
と詠みてやりて、狩りに出でぬ。
野にありけど、心はそらにて、今宵だに人静めて、いと疾く逢はむと思ふに、国守、斎宮頭かけたる、狩りの使ひありと聞きて、夜ひと夜酒飲みしければ、もはら逢ひごともえせで、明けば尾張の国へ立ちなむとすれば、男も人知れず血の涙を流せど、え逢はず。
夜やうやう明けなむとするほどに、女方より出だす杯の皿に、歌を書きて出だしたり。
取りて見れば、「かち人の渡れど濡れぬえにしあれば」と書きて、末はなし。
その杯の皿に、続松の炭して、歌の末を書き継ぐ。
「また逢坂の関は越えなむ」とて、明くれば尾張の国へ越えにけり。
斎宮は水尾の御時、文徳天皇の御娘、惟喬親王の妹。
現代語訳
昔、男がおりました。
その男が、伊勢の国に鷹狩りの勅使として行った時に、伊勢神宮の斎宮であった人の親が、
「普通の狩りの使いとは違います。この人は特に大切にしなさい」と言い送ったので、親の言いつけであったこともあり、女はその男をとても心をこめてもてなしました。
朝には狩りに送り出し、夕方は帰ってくると、斎宮の邸宅にまで来てもらうほどだったのです。
このように、心をこめてお世話しました。
二日目の夜、男は、「逢いたい」と言ってきたのです。
女もまた、逢いたくないというわけではありませんでした。
しかし、人目が多いので、なかなか逢うことができないのです。
男は正使として来ている人ですので、端の部屋にお泊めしてはいません。
男は女の寝室の近くにいたわけです。
女はまわりの人を寝静まらせてから、子一つ頃に、男の所にやって来ました。
男もまた、眠れなかったので、外の方を見やって横になっていると、月の光がぼんやりと差している中に、小さな童女を先に立たせて、女が立っているではありませんか。
男はとてもうれしくて、自分の寝所に連れて入って、子一つから丑三つまで一緒におりました。
しかし契りを結ばないうちに、女は帰ってしまったのです。
男は、とても悲しく、そのまま寝ないで夜を明かしてしまいました。
翌朝、男は女のことが気がかりでしたが、自分のほうから使いにやるわけにはいかないので、とても待ち遠しい思いで、女からの手紙を待っていました。
すると、夜がすっかり明けてしばらくして、女のところから、手紙ではなく、歌だけが贈られてきました。
あなたがやって来たのでしょうか、私が行ったのでしょうか、それもよくわかりません。
いったいこれは夢なのでしょうか、現実なのでしょうか、寝ている間のことなのでしょうか、起きている時のことなのでしょうか。
私は今、とても苦しいのです。
男は、たいそう泣きながら、次のような歌を詠みました。
悲しみで分別を失い真っ暗になってしまった心の闇の中で、何がなんだかわからなくなってしまいました。

夢か現実かは、今夜もう一度私のところへやって来て、はっきりと決めてください。
その後、狩りに出かけたのです。
野を歩き回っていても、心はうわの空で、せめて今夜だけでも人が寝静まってから、早く女に逢おうと思っていたのです。
ところが伊勢の国の国守で、斎宮寮の長官を兼ねている人が、狩りの使いが来ていると聞いて、一晩中酒宴を催したので、全く逢うこともできません。
夜が明けると尾張の国へ出立することになっていたので、女の悲しみは言うまでもなく、男もひそかに血の涙を流して悲しみましたが、やはり逢瀬はかないませんでした。
夜が次第に明けようとする頃に、お別れの杯を載せる皿に、女が歌を書いてよこしました。
男が手に取って見ると、
徒歩の人が渡っても着物の裾が濡れない川のように、浅い浅い二人の縁でしたねと書いてあります。
そこには下の句がありませんでした。
男はその杯の皿に、松明の燃え残りの炭で、下の句を書き継ぎました。
私はまた逢坂の関を越えようと思いますと詠んで、夜が明けると男は尾張の国へ行ってしまったのです。
この斎宮は清和天皇の御代、文徳天皇の皇女、惟喬親王の妹だったとのことです。
逢瀬はかなったのか
この時の伊勢の斎宮は文徳天皇の娘であり惟喬親王の妹である恬子(やすこ)内親王でした。
業平は惟喬親王にお仕えしていましたから、その縁もあって、もともと妹の恬子内親王とは親しかったのかもしれません。
古典には似合わず、かなりストレートな記述ですね。
その1つが、女のほうから男を訪ねていっていることです。
相手は神に仕える神聖な女性です。
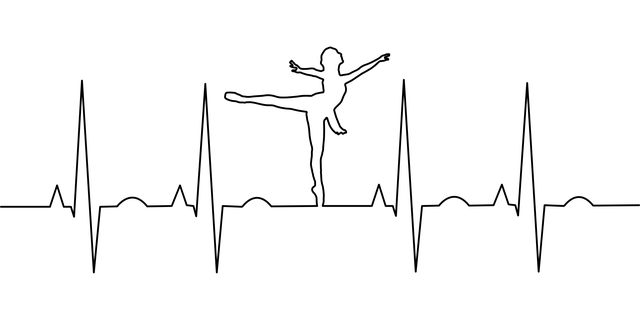
とうてい許されることではありません。
まさにタブーを破る大胆な行為とでもいえばいいでしょう。
「子一つより丑三つまで」一緒に過ごしたと、時刻が具体的に描かれています。
描写が妙に生々しいですね。
二人の間に密通の事実はなかったのでしょうか。
「語る」というのは男女が関係を持つことを意味します。
「語らなかった」というのをどう捉えるのかも、議論のわかれるところでしょう。
とはいえ、一夜をすごした後の歌のやり取りは、どちらとも取れる形になっています。
すべてが夢の中の出来事のような記述には、古文の味わいがあります。
いつの時代も禁忌があれば、それを破ってしまおうとする力が働きます。
そこに底知れない魅力があるからこそ、人の世なのかもしれません。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。


