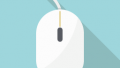わたしを束ねないで
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は中学校時代に学んだことのある詩を1つ紹介します。
あるいは高校で習った人がいるかもしれません。
詩というのは不思議な力を持った言葉の表現です。
そこに出てくる言葉は日常の生活で誰もが使っているものです。
しかし詩人の魂から紡ぎ出される時、全く別の表情を持ちます。
それがまさに詩魂と呼べるものなんでしょうね。

新川和江という詩人をご存知でしょうか。
名前くらいは聞いたことがあるかもしれません。
あるいは、この詩だけは知っているという人もいるでしょう。
胸に残る詩です。
それはなぜなのか。
1929年、彼女は茨城県の結城に生まれました。
高等女学校を出ると17才で近所の新川家に嫁ぎます。
生家は桑園で、母親同士が親しい縁でした。
その後26才で長男を出産します。
しかしこれからが彼女の面目躍如たるところでしょう。
夫は妻に何でもしてよいという人だったのです。
そこで彼女は小説、詩などの創作活動を始めます。
新川和江について、詩人の茨木のり子は「環境にめぐまれてぐうたらな有閑マダムとなってしかるべきところを、精神の安住を嫌い、本質的な問いをたえず発し続けてきた」と述べています。
女、妻、母
女に生まれ、恋をし、妻となり母となるという、ある意味ではごく平凡な人生の中に、しかしそれでも折れない自我の強さを感じます。
彼女の作品の中では、ことにこの詩が好きですね。
いつ読んでもあたらしい気持ちにさせてくれます。
この詩は、かつてあるテレビ番組の中で、母親が子供の中学校の教科書を広げながら一緒に勉強するシーンに登場しました。
あの時、ああいい詩だなと思ったのが最初です。
それからいろいろな詩集を調べ、新川和江のものであることを知りました。
言葉は不思議です。
本当にひそやかに語られたものが、心を打つのです。
ここに詩を紹介しましょう。

できたら声に出して読んでみてください。
————————————-
わたしを束ねないで
あらせいとうの花のように
白い葱のように
束ねないでください わたしは稲穂
秋 大地が胸を焦がす
見渡すかぎりの金色の稲穂
わたしを止めないで
標本箱の昆虫のように
草原からきた絵葉書のように
止めないでください わたしは羽撃き
こやみなく空のひろさをかいくぐっている
目には見えないつばさの音
わたしを注がないで
日常性に薄められた牛乳のように
ぬるい酒のように
注がないでください わたしは海
夜 とほうもなく満ちてくる
苦い潮 ふちのない水
わたしを名付けないで
娘という名 妻という名
重々しい母という名でしつらえた座に
坐りきりにさせないでください わたしは風
りんごの木と
泉のありかを知っている風
わたしを区切らないで
,(コンマ)や.(ピリオド)いくつかの段落
そしておしまいに「さようなら」があったりする手紙のようには
こまめにけりをつけないでください わたしは終りのない文章
川と同じに
はてしなく流れていく 拡がっていく 一行の詩
精神の自由
精神の自由と身体的な言葉が複雑にからまりあった詩です。
主人公は自らを「稲穂、羽撃き、海、風、川」にたとえて、精神の自由を謳っているのです。
そこに描かれているのは、何物にも縛られない、何処までも拡がっていく心です。
では、これらの比喩が突拍子もないのでしょうか。
そんなことはありません。
そうではなく、むしろ実感のある言葉です。
生き生きしていて、肉体をもった言葉と言ってもいいでしょう。
単なる比喩をこえて、自然と一体になっています。
だから、この詩に触れていると、まるで自分まで大自然に溶け込んでいって、満ちあふれていくような感覚にとらわれます。
この詩のもうひとつの特徴は、難しくいえば、存在のアンビバレンスということです。

外から求められている自分と、内から感じている自分が違うのです。
誰もが日常的に感じる二律背反です。
「娘、母、妻」である自分は同時に1人の「わたし」です。
世間や社会は外側の顔をわたしに要求します。
しかし本当の自分は内側からの圧力に負けたくない、たった1人の「わたし」でしかないのです。
黙っていると内なる本来の自分が、声を上げそうになります。
先ほども触れましたが、現代人はこういった葛藤を覚えている人が多いのではないでしょうか。
永遠の希求
世間、社会の中で生きるということは、1つの価値の体系をなぞることに似ています。
女性ならば良妻賢母であるべきだという時代では、さすがにありません。
価値観が多様化して、求められる役割もより複雑になってきているような気がします。
以前より、複雑な横顔をもつことも許される社会になりました。
しかしそこでやりとりされる人間関係は、どこか記号的です。
一種のアバター的要素に縁どられているのかもしれません。
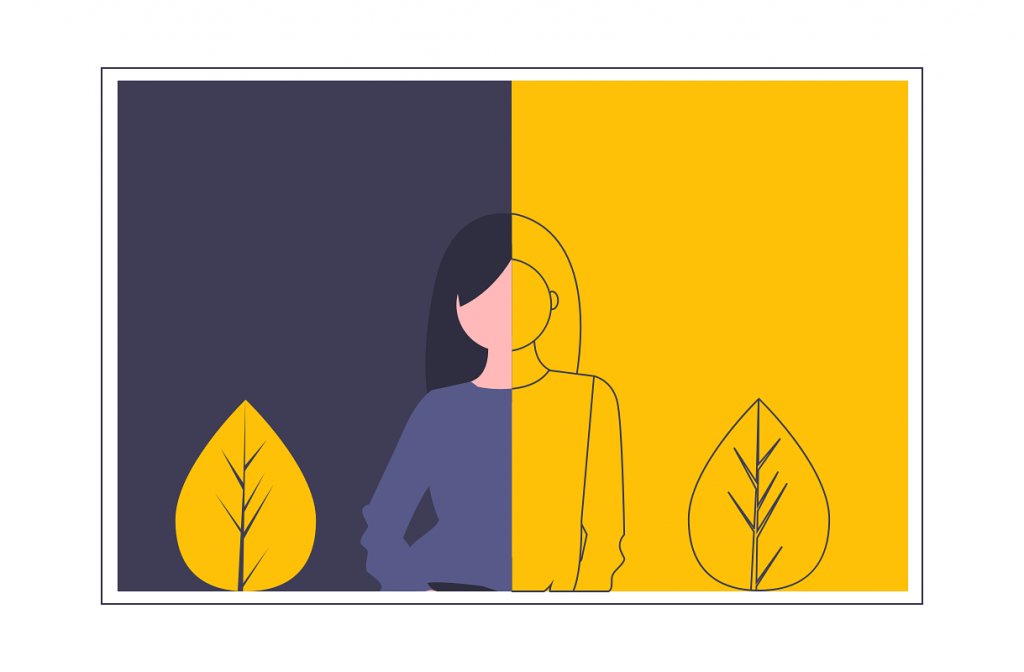
そうした時代環境の中で「わたしを束ねないで」と呟かれると、非常に新鮮に感じるのです
そこに身体性があるからでしょうか。
むしろ次々と繰り返される言葉の束に、共感を覚えます。
「わたしを束ねないで」「わたしを止めないで」「わたしを注がないで」と次々に注がれる言葉には、それだけ社会の中で硬直化している自分がいるのだという実感を強くさせます。
全てのしがらみから抜け出て、どのような地平に躍り出していけるのか。
そのためのチャレンジをどうすればいいのかを問われているようにも感じます。
おそらく、ほんのわずかな勇気を持てば、別のステージに立てるのでしょうね。
ところが普通はそれが怖いのです。
だから詩人はそこを飛び越えましょうと呼びかけているのかもしれません。
中学校時代の最後に、この詩に出会ったら、いろいろなことを感じると思います。
自分らしさを取り戻すために、何をしたらいいのか。
もがき苦しんでいる時期に違いありません。
声に出して読みながら、自分を鼓舞してもらいたいものです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。