小説のヒミツ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は小説の冒頭と結末について考えます。
といってもミステリーの話ではありません。
誰が犯人だったという類のヒミツではないのです。
実は久しぶりに文学論を読みました。
昔はいろいろな人の評論を題材にして授業もしました。
もちろん、自分の勉強のためだけに読んだものもあります。
最近はあまり手にすることもなくなりましたね。
今でも本棚の中にはかなりそのジャンルの本があります。
文芸評論家の講演会にも随分出かけました。
大学時代には、文芸評論家の先生のゼミをとったりもしました。
いい勉強になりました。
あの時代がなければ、今はないといっても過言ではありません。

たまにはあまり馴染みのない作家の文学論に目を通すこともありました。
河野多恵子著『小説の秘密をめぐる十二章』などもそのうちの1冊です。
これは雑誌「文学界」に連載されたものをまとめたものです。
河野といえば、ぼくにはすぐあの独特な髪型と『みいら採り猟奇譚』が思い出されます
面白い小説だった。
とにかく不思議な味わいのある作家です。
今ではそれほど多くの読者がいるとは思えません。
いわゆる純文学と呼ばれるものは、ほとんど消えてしまいました。
なくなったワケではありません。
しかしかつてのような勢いをもっているかといえば、そんなことはありません。
リアリティが命
それはともかくとして、この本は小説の持つ秘密を解き明かしていこうというものです。
古今東西の小説を題材にして、どこがよくどこが悪いのかを解明しようというのです。
小説というのは単純に言ってしまえば、どう書いてもいいものなのです。
主人公の名前も性別も出身も門地も学歴も、なんだって自由です。
名前なんか本当のことをいえば、必要がないのかもしれません。
アルファベットでもいいし、男だけでもかまいません。
あるいは極端なことをいえば、人間でなくてもいい。
もちろん、そこには自ずとリアリティがなくてはいけません。
荒唐無稽なことがらばかりが続くのでは、読むに耐えません。
いい小説はとにかく読者を引きずりこむ力を持っています。
たとえ、想像が容易にできないストーリーでも、そこに真実があれば、十分に小説たりえるのです。

さらにいえば、時間の経過を感じさせずに読者を引きずり込む力を持っています。
読後には形容しがたい味わいを残すのです。
大げさにいえば、世界が今までとは違った風景に見えなくてはいけません。
近年、確実にいい読者は減っているといいます。
つまり作家を懼れさせるような読者のことです。
つまらないしかけをいくら組んでも、彼らは即座に見破ってしまいます。
もっとうねりのある場所へ連れていけと読者が叫ぶのです。
彼らに鍛えられて、作家も成長するのです。
小説を読む人の数が確実に減りましたね。
電車の中で、文庫本を開いている人の数がめっきり少なくなりました。
世の中は確実に効率主義にシフトしています。
面倒臭い人間の心理の襞を知りたいという人より、てっとり早くお金を稼ぎたいとする人の方がはるかに多いのです。
書き出しと結末
章中に「導入と終わり方」というのがありました。
実際、文章を書いてみるとこれほど難しいものはないですね。
これはやったことがある人なら、だれでも実感として持っているものです。
どう始める、どう終わらせるかについて悩まなかった作家はいないでしょう。
この本の中で題材に上げられているのは芥川龍之介の『羅生門』でした。
高校1年生の教科書に載っている定番の小説です。
ほくのサイトでも『羅生門』については記事にしました。
最後にリンクを貼っておきましょう。
読んでいない人はほとんどいないと思われます。
河野多恵子によれば、特にこの小説の終わり方がよくないというのです。
たった一行を書いたばかりに、作品の余韻が崩れたというのが彼女の主張です。
その一行とは何でしょうか。
1番最後のところを覚えていますか。
「下人の行方は誰も知らない」というところです。
これがなければ「外にはただ黒洞々たる夜があるばかりである」で終わります。
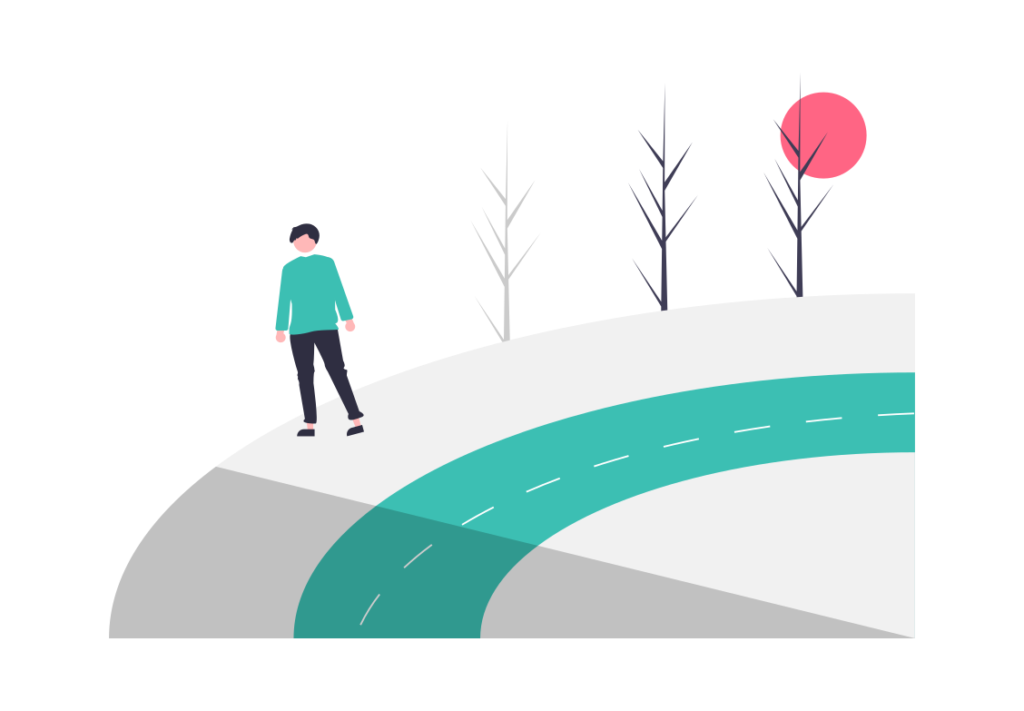
さてどちらがいいのか。
河野の論理によれば、一見これはすてきな文章に思えるかもしれないが、実質的な意味合いは何もない。
非力な一行で、玉に疵であるというのです。
目の中にゴミでも入った気がすると書いています。
いかにも小説家らしい比喩ですね。
最後の一行がなければ、際だってよく書けていたのにというワケなのです。
美意識の問題
実はここに創作の秘密があります。
美意識の問題なのです。
ぼくの個人的な意見をいえば、なくても確かにいいと思います。
しかしあえて書いた芥川龍之介の心中はどうだったのでしょうか。
それが知りたいです。
こういう細かいところへのこだわりが、一生文学を志すプロの作家を生み出すのです。
有名な小説には必ずこういう類の話がありますね。
川端康成の『雪国』はどうですか。
読めば読むほど病的な細い糸でくくられている作品だということに気づきます。
登場人物たちも細い崖の上を歩いているような危なっかしい人ばかりです。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
この文章に「そこは」を入れると、文章がだれてしまいます。
「夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」と立て続けに短く簡潔な文を連ねています。
心の動くスピードと、文章のスピードが同調しているとでもいったらいいのでしょうか。
上越線の水上と越後湯沢を結ぶトンネルを何度も往復したぼくとしては、やはり見事だなと感じざるをえません。

書き出しと結末に命をかける作家の気分がわかるでしょうか。
井伏鱒二も、死ぬまで代表作『山椒魚』を書き直し続けました。
旧版はこういう終わり方をします。
————————–
よほど暫くしてから山椒魚はたずねた。
「お前は今どういうことを考えているようなのだろうか?」
相手は極めて遠慮がちに答えた。
「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ」
————————–
ところが自選集を出した時には、全てカットしてしまったのです。
たかが小説などと言うなかれ。
作品というのは、作家にとってまったく空おそろしいほどの執念の世界の産物なのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。





