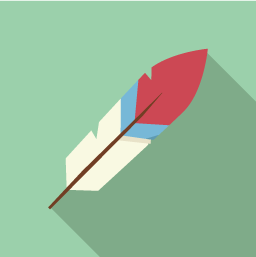看護のあり方
みなさん、こんにちは。
小論文添削歴20年の元都立高校国語科教師、すい喬です。
みなさんはいよいよ大学、専門学校を具体的に決めて、受験準備に励んでいることと思います。
その中で、特に勉強しにくいのが小論文です。
こんな試験なければいいのにと考えたこともあるでしょう。
しかしそういう訳にはいきません。
なぜなら、この試験を実施することで受験生のパーソナリティをきちんと捉えておきたいからです。
看護の仕事は一筋縄ではいきません。
超過酷な勤務体系の日々が続きます。
患者との緊密なコミュニケーションも必要です。
看護の基本に立ち戻らなければならないシーンが次々と襲ってきます。
そんな時でも揺らぐことなく、落ち着いていられるかどうか。
受験生が職務に邁進できる信念を持っているかどうかを見極めたいのです。
よく文は人なりと言いますね。
文章を書かせると、その人間の横顔がみえてきます。
今後もこの試験がなくなるということは考えられません。
むしろ様々な角度からいくつもの論文を書いてもらうということが増えるのではないでしょうか。
今回はその中でも最もよく出る基本的なテーマについて考えてみます。
それは何か。
ズバリ、「看護のあり方」です。

sasint / Pixabay
どの学校で何度出しても古びない最もコアな内容です。
今までおざなりにしてきた人は、ここでもう一度立ち止まり文章にまとめてみてください。
けっしてムダにはならないはずです。
看護と治癒
今まで医療の世界ではまず「治癒」が先行していました。
とにかく病気を治すということが第一の目標だったのです。
これは基本的に今日もかわりがないともいえます。
しかし高齢化社会の今日、単純に病気を治せばそれで役割が終わったということはできなくなっています。
健康で理性の働く状況が健常だとすれば、そうでない人間はみな弱者です。
それは同時に健常者以外の者を全て自分より劣った人間だと認識するということと同じです。
今日の高齢化社会における看護の意味とはかなりのズレを感じざるを得ません。
現在では医者のアシスタントとしての看護というレベルをとうに越えています。

Tumisu / Pixabay
患者が自分の生をいきいきと生きていけるようにサポートするという考え方が主流になってきました。
これは障害者についても同様です。
患者、障害者は弱く庇護すべき存在であり、病気を背負った気の毒な人々だという認識ではこれからの看護はできないのです。
とくに患者と長い時間接する看護師は、心のケア、心を支える者としての存在理由を強く求められています。
看護と治癒という両輪がうまくリンクしないと今日の医療は進みません。
現実に多くの高齢者は自宅でその生涯を閉じるということがほとんどなくなりました。
病室で家族に看取られながら生を終えることができれば、まだ幸福な方です。
実際のところ、最後は老人施設の看護師や介護士に世話になるというケースが非常に多いのです。
つまり相手の人格と真剣に向き合い、ケアしていくことを人間関係の基本におかない限り、これからの看護は成り立ちません。
この点をきちんと納得して看護の世界に飛び込むという意志をきちんとみせてください。
表現はどのようなものであれ、これなしに文章を書くと、どこか上っ調子なものになりがちです。
逆にいえば、この覚悟がきちんとできていれば、必ず文章に反映してきます。
ケアするという行為は逆にいえば、ケアされるという行為にも通じます。
難しくいえば、関係の絶対性ということです。
こちら側からのベクトルは、必ず相手側からのベクトルにもなり得ます。
一方的にお世話をしているという考え方で看護はできません。

jossuetrejo_oficial / Pixabay
相互の関係が成立しない限り、本当の意味での看護にはならないのです。
いい看護ができたと自分で感じる時は、必ず自分も成長しているというのが、この考え方の根本です。
ここをまず押さえてください。
どのような問題が出ても、この基本的なスタンスを書き込めば、その人間の誠実さが採点者に届きます、
信じてください。
今日的役割とは?
患者はあたりまえのことですが、さまざまな感情や価値観を持っています。
しかしともすると、看護人はそれを忘れてしまう傾向があるようです。
特に仕事が過密になってくると、患者から名前が取れ、それこそ番号でしかなくなります。
他の患者との区別もつかず、ただ時間に支配され薬を与えられるだけの人なのです。
そこにある不安や不満は全て見えません。
患者は一人の個性です。

geralt / Pixabay
人間としての尊厳をきちんと守り、見抜くことが最も看護する側の人間にとって必要なことでしょう。
しかし同時に適切な看護とは何かという問題も生まれてきます。
「病気と闘って欲しい」という気持ちも強く出過ぎれば、それは患者にとって重荷でしかないのです。
あくまでも背後からサポートするという立ち位置をキープし続けることが大切になります。
ケアするということの本質がここにあるのではないでしょうか。
現在の医療ではQOL(クォリティ・オブ・ライフ)を重視するというのが原点です。
患者の生命がただ長くなればよいというものではありません。
あくまでも生命の質ということが大切です。
確かに過去にはただ生き長らえぱそれでよいという考え方もありました。
俗にスパゲッティ症候群と呼ばれ、身体のあちこちに管を入れられて、患者や家族の意志などどこにもないような治療もあったのです。
しかし現在の医療の考え方は全く違います。
よりよい生の質を維持しつつ、患者を手助けするという考え方が主流です。
その論点をつねに頭の隅に置いておいてください。
チーム医療の問題
今日の医療は医者が単体で行うものではありません。
看護師は当然重要なスタッフの一人として、そのチームに加わります。
ということはスタッフ同士の信頼関係を構築するということがなによりも大切になるのです。

truthseeker08 / Pixabay
多数の専門スタッフとともに同じ治療にあたるということは、医療的な知識の充実だけでは不十分です。
特に医療ミスなどがおこると、人間関係も病院に対する信頼も全てが一瞬で崩れます。
最近では訴訟問題も頻発しています。
その責任を負わなければならないということもありえる訳です。
もちろん、不正などということはあってはならないことです。
特に延命治療などに関しても、医療チームの連携がきちんととれていないと、患者やその家族との関係が疑心暗鬼になるということもあり得ます。
医療の目的が何であるのかという基本がとらえられていないと、こうしたミスが起こる原因にもなるわけです。
再び生還することがかなわない患者に、不必要と思われる治療を重ねることがあってはなりません。
しかしそれもどの時点で判断するのかというのも難しい課題です。
看護師は的確なアドバイスを伝え、患者の刻々の変化をチーム全体に流す役割を担っています。
その際、あくまでもインフォームド・コンセントの基本に立って、行動しなければならないことはいうまでもありません。
最後に一番大切なものは看護師の資質です。
なによりも必要なもの。
それは人間としてのやさしさです。
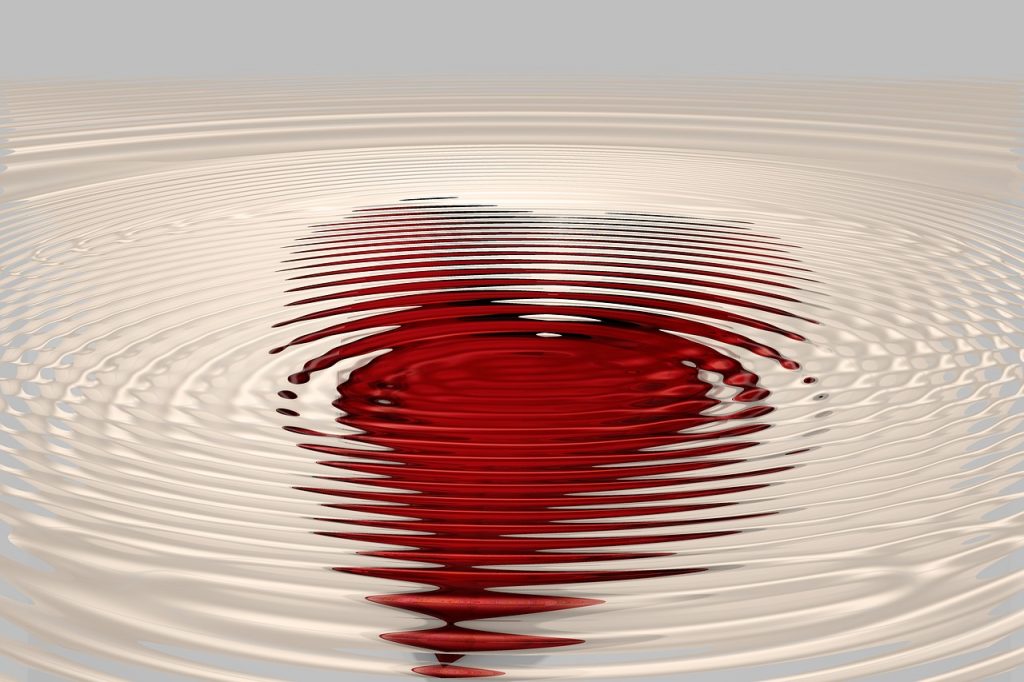
geralt / Pixabay
看護師として最後に必要なものは何かといえば、この資質につきるのではないでしょうか。
そのことをあらためて自分に問いかけてください。
経済や効率とは正反対の仕事であるという捉え方ができない限り、長くこの仕事に就くことはできないと思います。
諦めずに小論文の勉強を続けてくださいね。
みなさんの希望が届くことを祈っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。