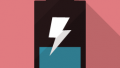短編の味わい
みなさん、こんにちは。
毎日何をしていいのか迷いながら暮らしています。
ブロガーのすい喬です。
新型コロナウィルスに世界が覆われてから、随分と風景が変わってしまいました。
今まで元気だった人が突然病に侵され、やがて亡くなってしまうということも珍しくありません。
いつもテレビで見ていた人がふっと消えてしまうというのは、ものすごいショックです。

何をしたというわけでもないのに、少し肺が弱くなっていたり、癌の手術をして免疫力が落ちているところを突然襲われたりするのです。
本当に人の命はあっけないものだと感じます。
それに対して、人間のやれることはせいぜい人との間隔を離し、マスクをつけて暮らすことぐらいしかありません。
薬もいくつか開発されつつありますが、これが決定的だというところまではいっていません。
時間をもてあまして、つい読書ということになります。
昔読んだ本をめくってみるというのも、時間潰しの1つの手です。

今日も村上春樹の短編をいくつか読んでみました。
彼の小説についてはぼくもいくつか記事を書いています。
「トニー滝谷」「鏡」「とんがり焼きの盛衰」「象の消滅」などです。
いずれも短編ばかり。
この小説家はぼくと年齢がほぼ同じです。
群像新人文学賞『風の歌を聴け』の頃からずっと読み続けています。
長編を好んだ時期もありますが、最近はもっぱら短いものばかりです。
村上春樹の味わいは短編にあるのではないでしょうか。
授業で取り扱ったものもいくつかあります。
『レキシントンの幽霊』もかつては教科書に載っていたとか。
残念ながら、ぼくは扱いませんでした。
あらすじ
ストーリーはそれほど複雑なものではありません。
主人公の小説家「僕」はボストン郊外の屋敷に住むケイシーという男と友人になります。
彼は膨大なジャズレコードを持っていました。
ある日ケイシーはレコードを好きなだけ聴いていいという条件で1週間の留守番を僕に頼みます。

仕事でロンドンにでかけるというのです。
その家に泊まった最初の晩、僕は階下の居間から聞こえてくる音で目を覚まします。
パーティをしているような喧噪が聞こえてきたのです。
まるで幽霊のパーティのようでした
僕はその晩をなんとかやり過ごします。
幽霊が出たのは1晩だけでした。
1週間後、ケイシーが帰ってきます。
ケイシーが家に着いた時の描写は特筆ものです。
留守の間に何かかわったことはなかったと玄関先で僕に訊ねたのです。
つまりケイシーはこの家に幽霊が出ることを以前から知っていたようです。
僕はこう答えます。
「いや、とくに何もなかったよ。とても静かで仕事がよくはかどった」
「それはよかった。何よりだ」
僕は作家です。
ケイシーとは編集部に届いた手紙で知り合った仲なのでした。
しかしなぜこの台詞が玄関先ですぐに出たのか。

何もかもを知っていたケイシーの存在が際立ってきます。
彼は母親が亡くなった時の父の悲しみと父を失くした時の自分の悲しみを次々と僕に打ち明けていくのです。
どちらの時も、ただ眠り続けたという事実を語ります。
最初は父が、そして次にケイシー自身が。
数週間の間ただ眠り続けたというのです。
ここに「現実」と「異界」とをつなぐ装置としての眠りが登場します。
眠りに眠る
最初に眠り続けたのは父です。
ケイシーの母親が亡くなった直後から目を覚ますことがなくなりました。
微かに息をするだけで、少しも動くことはなかったそうです。
考えてみれば、その間に実世界から異世界へ飛び立つものとそこで最後の別れの儀式をしていたのかもしれません。
その後、父が亡くなった時はケイシー自身が眠ります。

小説の記述は次の通りです。
たぶん全部で2週間くらいだったと思う。
眠って眠って、時間が腐って溶けてなくなってしまうまで眠った。
そのときには、眠りの世界がぼくにとっての本当の世界で、現実の世界はむなしい仮初めの世界に過ぎなかった。
母が亡くなったときに父が感じていたばすのことを、ぼくはそこでようやく理解することができたというわけさ。
この後、きっとこの作品全体のキーワードになる言葉が出てきます。
それは何でしょうか。
「つまりある種のものごとは、別のかたちをとるんだ。それは別のかたちをとらずにはいられないんだ」
この表現です。

その後、ケイシーは微笑みを浮かべながら、こう言います。
「ぼくが今ここで死んでも、世界中の誰もぼくのためにそんなに深く眠ってはくれない」
彼自身の諦めともとれる表現です。
ある種のものごとは別のかたちをとるとはなんのことなのでしょうか。
この文章は必ず試験の問題になりました。
教員用の解説書にはそのことが示してあります。
みなさんはどういう意味だと思いますか。
別のかたちとは
常識的に考えれば、このケイシーという男性の哀しみ、孤独感は誰にも癒せなかったということでしょう。
突然の喪失は他のもので補えるわけではありません。
すると、ここでいう別の形とは何か。
この作品に限っていえば、眠り続けることに変化したことともとれます。

あるいは人間のある感情が全く別の行動を招いたとも解釈できます。
しかしこの答えは言葉をその意味のままに捉え過ぎているかもしれません。
愛する人を突然失った悲しみを別のかたちに捉えなおすというのは、他者には容易に理解できないことなのではないでしょうか。
きっと世界の色が突然変わってしまうことなのです。
それまでカラーだったとすれば、モノクロに変化するのかもしれません。
色が全て抜け落ちてしまうということも考えられます。
国語の授業ならば、そのレベルで解釈を終えれば十分です。
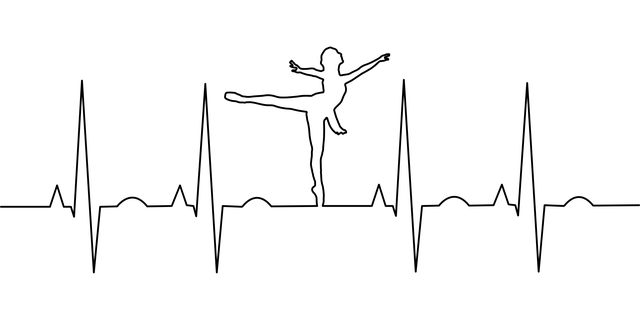
あるいはレキシントンという地名をなぜここに入れたのかということも1つのヒントになるかもしれません。
この土地は1775年、アメリカ独立戦争の火ぶたが切られたところでもあります。
当然、多くの人が死にました。
そのことにあまりこだわりすぎると、作品の味わいを失うかもしれません。
しかし忘れてはいけない事実です。
ここには詳しくは書きませんでしたが、大切なヒントとして同居していたジェレミーというピアノ調律師の友人がいます。
母親の具合が悪くなり、彼はウェストバージニアに戻ってしまいます
その母が亡くなったことで、ジェレミーは別人のように人がかわり、電話で星座の話しかしなくなってしまうのです。
人が亡くなることの喪失感がここにも深く現れています。
これもある意味、別のかたちといえるのかもしれません。
この小説には何人もの人の死が登場します。
それがデジャビュのようにこの館物の中を揺曳するのです。
我が物顔に歩き回るといってもいいのかもしれません。
読み終わった時、人は必ず死に、その後に深い闇を残すのだということを考えました。
村上春樹の死生観にもつながる小説です。
最後までおつきあいいただきありがとうございました。