範円上人の出家
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はある高僧の出家話を読みます。
『撰集抄』は現世の無常を悟って賢明なふるまいをした高僧や聖の言行録、往生談などを集めた仏教説話集です。
寿永2年(1183)に完成し江戸時代まで、西行法師の自作と信じられてきました。
しかし後になって別人の作であることが明らかになっています。
歌人の西行が旅先で見聞きした話を、語り手として書き記した説話集という体裁をとっています。
ところが本当の作者はわかっていません。
全9巻に神仏の霊験、高僧の行い、遁世者たちの行動、発心・出家・往生などの体験談が記されているのです。
謡曲の「江口」「雨月」や上田秋成の『雨月物語』の中の「白峯」など、本書に想を得た作品は数多くあります。

近代にいたっても幸田露伴の『二日物語』が本書から題材を得ています。
今回の段は範円上人という高僧に関連した話です。
範円は平安時代末期から鎌倉時代にかけての僧侶で、源義朝の六男の源範頼の嫡男です。
中納言であったころはまだ経光と名乗っていました。
大宰府の長官になって、九州に下るとき、都から浅からず思っていた妻を連れていったのです。
だがやがて別の女性に心がうつり、病気の重くなった妻はどうしようもなく経光に歌を贈って亡くなってしまいます。
しばらく後、経光はその衝撃から出家してしまいました。
一時的に愛情が離れた妻が亡くなったことによほどショックを受けたものとみえます。
捨てがたい世を離れようと決心したのでしょう。
この段では上人の出家話になっていますが、その妻の律儀な愛情の形にも触れています。
本文
中ごろ、筑紫の横川といふ所に、範円上人といふ人いまそかりけり。
智行ひとしくそなはりて、生きとし生けるたぐひをあはれみ給ふことねんごろなり。
観音を本尊として、つねに大悲の法門をなん心にかけ給へり。
いまだこの聖人、飾りおろし給はざりけるさきは、吉田中納言経光と申けり。
帥になりて、筑紫へ下り給ひける時、都より浅からずおぼえ給へりける妻をなん、いざなひていましけるを、いかが侍けん、
あらぬ方に移りつつ、花の都人は古めかしくなりて、薄き袂(たもと)に秋風の吹きて、あるかなきかをも問ひ給はぬを、憂しと思ふ乱れの、はれもせぬつもりにや、
この北の方、重くわづらひて、都へ上るべき便りだにもなく、病は重く見えける。
「とさまにして、都に上りなん」と思ひ侍りけれども、心にかなふつぶねもなくて、海を渡り、山を越へんやうもおぼえざりければ、帥のもとへ、かく、
問へかしな置き所なき露の身はしばしも言の葉にやかかると

と詠みてつかはしたるを見侍るに、日ごろの情け、今さら身にそふ心地し給ひて、あはれにも侍るに、
また、人の走り重なりて、「すでにはかなくならせ給ひぬ」と言ふに、夢に夢見る心地して、わが身にもあられ侍らぬままに、手づから髻(もとどり)切りて、横川といふ所におはして、行ひすましていまそかりける。
まことに、昔、芝蘭の契り、こまやかに、偕老の睦び、さこそわりなく侍りけめども、うるせき情けの色にうつりて、秋風の吹き重ぬる人の身まかりけるに驚きて、
さしも捨てがたきこの世を離れんと、思ひなり給へる心のうち、かへすがへすありがたく侍り。
現代語訳
昔、中ごろ(平安時代の中期)、筑紫の横川というところに、範円上人という僧がいらっしゃいました。
智慧と修行の徳を兼ね備え、生きとし生けるものを深くあわれみ慈しむ心が厚かった方です。
観音菩薩を本尊として、常に大悲の教えを心にかけておられました。
この聖人がまだ出家しておられなかった頃は、吉田中納言経光と申し上げました。
筑紫守として筑紫に赴任なさった時、深く愛していた妻を伴って行かれたのです。
しかしどうしたことでしょうか。
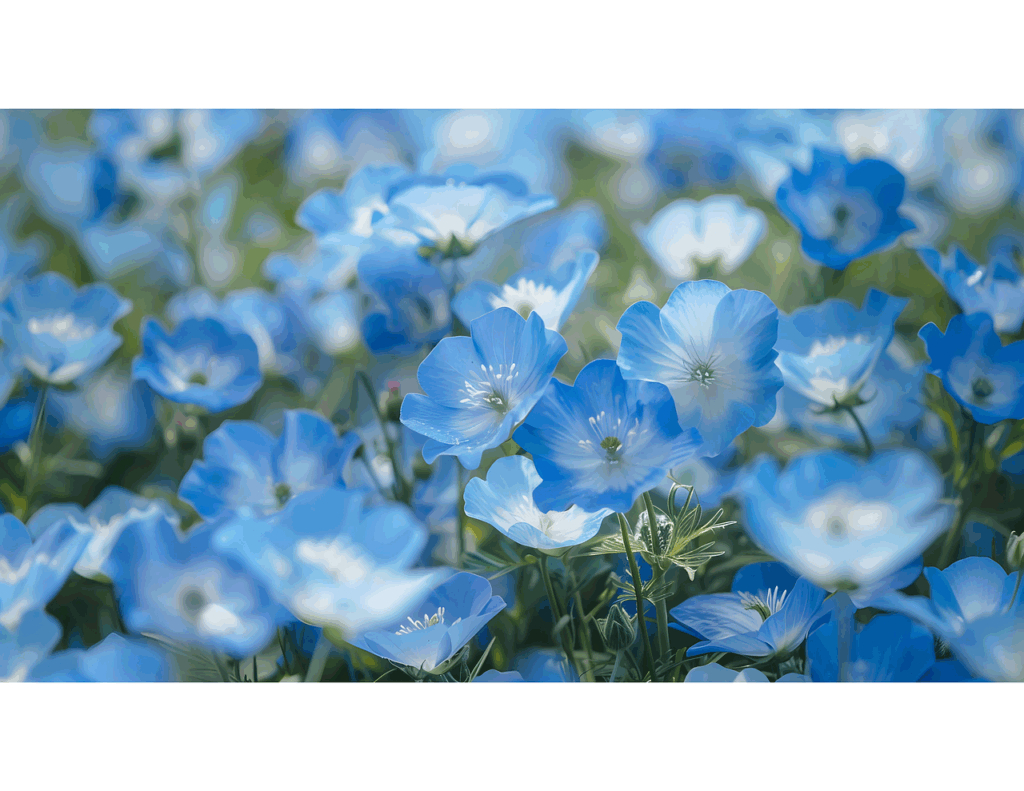
年月がたつうちに都の華やかさが遠い昔のことのようになり、秋風が吹く頃には、薄い衣の袖に冷たい風がしみて、妻のことを生きているかどうかさえ尋ねもしなくなってしまいました。
その憂いと悲しみに心が乱れるままに、妻は重い病にかかり、都に帰るすべもなく、病状はますます悪くなっていきました。
妻は「このままでは都へ帰りたいと思っても、思うように船もなく、海を渡ることもできません」と嘆き、夫の経光に次のような歌を詠んで送りました。
「どうかわたしを訪ねてきてください。この行き場のない露のような身は、せめてあなたの言葉の葉の上にでも留まれるものでしょうか。」
その歌を見た経光は、日ごろの妻への情が今さら胸に迫り、深くあわれに思いました。
そのうち続けざまに知らせがやってきて、「奥方はすでに亡くなられました」と告げられました。
経光はまるで夢を見ているようで、自分の身にもあらぬような心地がして、髻(もとどり)を自ら切り落とし、出家して横川に籠り、そののち修行に励まれたということです。
まことに、昔は芝蘭(しらん=芳しい夫婦愛)の契りを結び、共に老いようと誓った睦まじさは、並々ならぬものであったのでしょう。
だが、深い情愛がかえって執着となって、秋風に散るように妻が亡くなったことに心を打たれ、ついに、この世を捨てようと思い立ったのです。
その心のありようは、何度思い返しても尊く、ありがたいことだとしみじみ感じいったものです。
愛妻の病死
文章全体の意味はそれほど難しいものではありません。
吉田経光という貴族が、筑紫に赴任中に愛妻を病で失います。
深い悲しみのあまり出家し、範円と名乗り、仏道修行に励むようになったという話です。
いわゆる出家物語のひとつと考えればいいでしょう。
かつては夫婦といっても常に同じ屋敷に住み、ともに食事するというわけではありませんでした。
女性はいつも待つ身だったのです。
愛情が薄れてしまえば、夫が同じ屋敷に住んでいても部屋を訪ねることがなくなります。
それでもじっと待ち続けなければならないというのが、女性の日々の暮らしそのものなのです。
多くの日記を読んでいると、この時代の女性のおかれた立場の難しさが実によくわかります。
夫には当然、仕事があります。
財力があれば、他の女性のところへ通うことも可能です。
大宰府の長官となって、九州へ出向くに際し、都から正妻を連れていったところまではよかったのです。
しかしいつの頃からか、他の女性に心が移っていってしまったのでしょう。
秋風が吹くように飽きていき、部屋を訪れることもなくなってしまいました。
あるいは別の屋敷に住むようになったのかもしれません、
消息さえも尋ねなくなったのを、北の方はあれこれと思い乱れてつらい日々を送ったにちがいありません。
ましてや都を離れて病に臥せったりすれば、その心細さは想像を絶するものだったはずです。

知り合いのいる京都に戻りたいと思うのは当然ですね。
この段に出てくる女性は、かなり夫に愛されていたようです。
それでも長い人生の間には愛情が薄れる時期もあったりするのでしょう。
問へかしな置き所なき露の身はしばしも言の葉にやかかると
この歌は妻が夫に差し出した魂の叫びともいえるものです。
どうかわたしを訪ねてきてください。
この行き場のない露のような身は、せめてあなたの言葉の葉の上にでも留まれるでしょうか、というのが歌の意味です。
妻は夫にただ顔を見せてくださいと懇願しています。
夫婦のさりげない会話の中に愛情のかけらをみて取りたかったのでしょう。
今も昔も男女の関係というのは複雑きわまりないものです。
「共に白髪の生えるまで」という表現は、それを実践することの難しさを同時に意味します。
亡くなった後、妻の気持ちを知るにつけ、夫は自分の人生を振り返ったことと思われます。
そこから仏道への帰依は一直線でした。
この段は人の愛情が「執着」に変わり、それをきっかけに「悟り」への道に進むという、仏教的なテーマを持っています。
当時の人びとはこの話を聞いて、どのような感想を抱いたのでしょうか。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


