週に2冊
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
暑い夏の到来となりました。
涼しい環境にいると、つい横になることが増えます。
いつの間にか35度が標準、40度が猛暑という基準になってしまいました。
毎日、熱中症に気をつけろとテレビのニュースが叫んでいます。
こんな日常がやってくるとは思ってもみませんでしたね。
野菜も肉も卵も値上がりし、さらに円安の中で、日本人の生活意識も確実に変化しています。
日本人をもっと大切にしろという政党が、若者に支持される時代です。
今のまま、社会保障費を維持するために、だれからどのようにそのための財源を手に入れるのか。
考えてみれば、答えはすぐに出てきます。
いわゆるZ世代までをふくめての若年層でしょう。
それでも不十分なことは明らかです。

高齢者を厚遇しすぎれば、当然不平が若い人々の間にマグマのようにたまっていきます。
さらに外国人にも同様です。
ファクトチェックもなされないSNSの言動が不安を呼び起こすという現象は、かつての歴史を思い起こさせます。
不安の増殖の先には、当然暴力も起こります。
きちんとした論理で自分の周囲を見るということが、それだけ苦痛に満ちているからです。
休みに入って、ほぼ1週間に2冊のペースで好きな本を読んでいます。
読後の感想を書きます。
『ハヤブサ消防団』
池井戸潤の『ハヤブサ消防団』は地方の村に移住した作家が事件に巻き込まれる話です。
ストーリーを広げるための要素をいくつもばらまき、そこから最後に大団円を迎えるというバターンは、彼の得意とするところです。
数年前、テレビでドラマ化もされました。
田舎の風景が懐かしさを呼び起こします。
しかし入団希望者のいない消防団という話は、現代の風景そのものですね
つい先日も出動費を個人に支払わず、団が運営費に流用していたというニュースがありました。
そのくらいのレベルなら、なるほどと納得もできますが、この小説では殺人事件や連続放火が次々と起こるのです。
さらには、やや影のある美貌の若い女性の存在。
ソーラーシステムの営業マンを装った謎の新興宗教団体関係者。
ストーリーを先に進めるための装置はいくらでも用意しておかないとという作家の方法論がここにはあります。
池井戸潤は元銀行員でした。
それだけに銀行や金融の闇を扱った初期の作品は、非常に面白いです。
半沢直樹が活躍するドラマは高い視聴率を稼ぎだしました。

ここにあげた中にはずれはありません。
『果つる底なき』2001年
『銀行総務特命』2002年
『架空通貨』2003年
『仇敵』2003年
『株価暴落』2004年
『銀行狐』2004年
『オレたちバブル入行組』2004年
『オレたち花のバブル組』2008年
『不祥事・花崎舞は黙ってない』2011年
ところがさすがにネタも尽きてしまうのでしょう。
『下町ロケット』のシリーズの後は、スポーツを話題にした作品が続きました。
特にランニングシューズを開発した足袋のメーカーの話は興味深かったです。
さらに「箱根駅伝」を扱った小説では、正式な枠ではない、関東学連選抜にスポットをあてた点がユニークでしたね。
3位争いに入ると豪語した若い監督の横顔に引き込まれました。
さらにテレビクルーの視聴率に対する古参ディレクターと新人との意識との落差が、ある意味新鮮でした。
今回の『ハヤブサ』ではさまざまな要素がからむものの、やはりどこか作り物めいてみえた印象が強いです。
個人の心情の内部にまで、降りるという筆致ではないからかもしれません。
都会人がイメージする田舎の暮らしはここに示された通りです。
息苦しく自由のない世界を覗き見た印象が強いです。
しかしそこにオウム真理教が上九一色村を侵食していった時のような、恐怖感はなかったです。
『彼は早稲田で死んだ』
最近、友人が勧めてくれたので読みました。
著者は早稲田大学を卒業後、朝日新聞の記者になった樋田毅氏です。
このルポは第53回大宅賞の受賞作です。
時は今から50年以上も前にさかのぼります。
1972年11月、早稲田大学構内でリンチ殺人事件が起こりました。
当時、革マル派が支配していた早稲田大学文学部構内で、一人の学生が虐殺されたのです。
「川口大三郎君事件」と呼ばれています。
今となってはほとんど誰もが知らない事実かもしれません。

筆者である樋田氏はあとがきに自分の人生のテーマは2つあると書いています。
ーーーーーーーーーーーーー
1人は1978年5月3日の憲法記念日の夜、朝日新聞阪神支局で勤務中に「赤報隊」の男によって射殺された、当時29歳の小尻知博君。
私は朝日新聞の記者として犯人を追い続けた。
戦前につながる日本社会の深い闇が見え隠れする事件だったが、いまだに未解決のままである。
そしてもう一人が1972年11月8日、早稲田大学の校舎で革マル派によって虐殺された、当時20歳の川口大三郎君。
私は仲間たちとともに、革マル派の責任を追及したが、闘いは頓挫したまま、大学を卒業した。
ーーーーーーーーーーーーー
大学の中で殺人が起こるなどということは、現在全く考えられません。
それも思想的に対立する相手をリンチで殺すなどいうことは想像の外です。
今の時代との落差を知らない人々からみれば、狂気の沙汰でしょう。
しかしこれが現実でした。
大学構内が自治の名のもと、ほとんど治外法権に近かったのです。
それをうまく利用して、革マル派が暴力で支配していました。
非暴力
樋田氏は当時第一文学部自治会執行委員として、暴力によらない、大学の自治を標榜していきます。
しかし既得権を持っている相手の組織はさまざまな手段をとり、容易に支配権を手放しません。
それだけでなく、暴力によって、日常を取り去ろうとしていくのです。
このルポを読んでいると、当時の学生たちの日々の行動がよく見て取れます。
巻末にある当時の革マル派幹部との対談も非常に興味深いものです。
彼らがどのような意識をもって鉄パイプをふりまわしていたのかとよくわかります。
その後、自治権をめぐって闘いは続きましたが、1994年、奥島総長が就任した後、商学部自治会の公認を取り消したことで、事態は急速に動き出します。
1997には早稲田祭の中止。
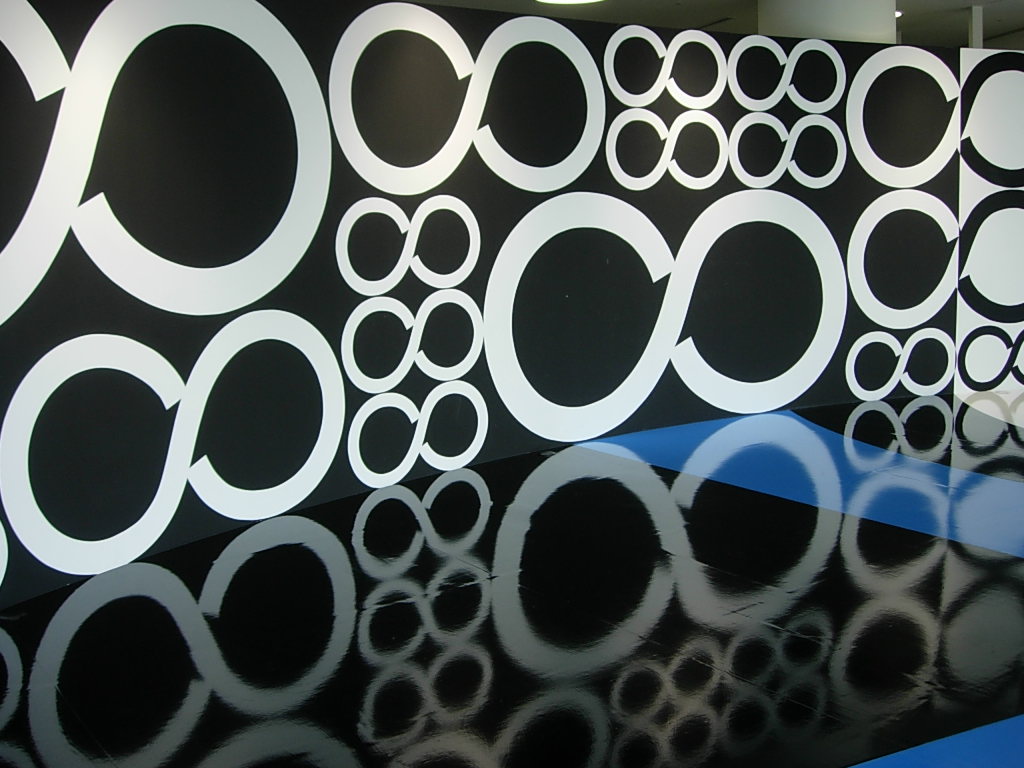
これには年間1000万円以上の資金流失がありました。
実質的に革マル派の活動資金になっていたのです。
学生会館の建て替えも行いました。
その間、脅迫、尾行、盗聴などの妨害をはねのけたのです。
全ては過去の話だといってしまえば、それまでのことです。
あらためて、このルポを読み、人が人として生きていくことの難しさを感じました。
自分に正直に生きるということは、いかに困難なものか。
関心のある方はぜひご一読ください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


