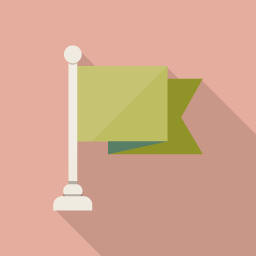城の崎にて
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は高校で習う小説『城の崎にて』について考えてみましょう。
志賀直哉の代表的な短編です。
1917年、白樺派の同人誌『白樺』に発表されたものです。
この流派の名前をきいたことがありますか。
『白樺』というのは当時のモダンな雑誌の代表でした。
学習院に集った青年たちが始めた同人誌です。
理想主義、人道主義、個人主義を高く標榜しました。
それが大正デモクラシーと重なり、社会の思想的な潮流になったのです。
武者小路実篤、有島武郎、里見弴などが同人にいました。
『城の崎にて』は日本の私小説の代表的な作品とされています。
小説というよりは、むしろ当時の心境を綴ったエッセイの趣きが強いのです。

志賀直哉はよく「小説の神様」と呼ばれました。
文学青年たちは、よく彼の文体を模写したと言われています。
どこがうまいのか。
それはプロの作家をうならせる独特の筆致にあります。
この作品も事故に際した自らの体験を綴ったものです。
ちょっと読んだだけでは、その描写の的確さを味わうことはできません。
一言でいえば、無駄がないのです。
登場する小動物たちの描写は見事なものです。
冒頭
小説の最初のところをご紹介しましょう。
味わって読んでください。
————————
山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした。
その後養生に、一人で但馬の城崎温泉へ出かけた。
背中の傷が脊椎カリエスになれば致命傷になりかねないが、そんなことはあるまいと医者に言われた。
2、3年で出なければあとは心配はいらない。
とにかく要心は肝心だからといわれて、それで来た。
3週間以上、我慢できたら5週間くらいいたいものだと考えてきた。
———————–
この書き出しのリズムはどうでしょうか。
なんでもないようですが、そこには自ずと計算があります。
しかしそれを見せないところがプロの腕なのです。
彼は文筆を仕事にしている人たちを唸らせる手腕の持ち主でした。
谷崎潤一郎「文章には芸術的な手腕がある」
三島由紀夫「自然描写は世界に卓越している」

いずれも志賀直哉に脱帽しています。
どこがうまいのか、わかりますか。
文体が乾いています。
粘っこくない。
さらっとしているのです。
それでいて描写は鋭いです。
1913年、里見弴と芝浦へ涼みに行き、相撲を見て帰る途中、線路の側を歩いていて山手線の電車に後からはね飛ばされ、重傷を負いました。
しばらく東京の病院に入院したものの、療養のために兵庫県にある城崎温泉を訪れたのです。
その時の様子と心境を淡々と綴った掌編です。
事故に際し何を考えたのか。
それは文字通り自分の死でした。
そのことが文中に出てきます。
死の意味
一つ間違えば、今頃は青山の土の下に仰向けになって寝ているところだったなと思う。
青い冷たい堅い顔をして、顔の傷も背中の傷もそのままで、祖父や母の屍骸が傍にある。
それももうお互いに何の交渉もなく、こんなことが思い浮かぶ。
それは寂しいが、それほどに自分を恐怖させない考えだった。
いつかはそうなる。
それがいつか。
今まではそんなこと思って、その「いつか」を知らず知らず遠い先のことにしていた。
しかし今はそれが本当にいつかしれないような気がしてきた。
————————
ここには自分の死を冷静に客観的にみた描写が続いています。
誰もが自分の死を考えないワケではありません。
ところが実際にそれはいつのことかわからない、未来の図なのです。
それが事故によって引き寄せられたという実感がありますね。
その心境を際立たせるために、志賀は他の生き物を配置しました。
彼らの死を生きている作家がじっと見るという図式にしたのです。

主人公である作家は、蜂、鼠、いもりなど、小動物の死を次々と目撃します。
特にいもりのケースでは、何気なく投げた石があたってしまいます。
その気がないのに結果として殺してしまったのです。
事故で死ぬはずだった自分は助かり、いもりはほんの偶然で死んでしまいます。
蜂は玄関にあるヤツデに群がっています。
退屈な時に、よく蜂が出入りしているところをみていました。
ところがある日、触角をだらしなく顔へ垂れ下げたまま、死んでいる蜂を見つけます。
他の蜂は見向きもしません。
3日間ほど、そのまま動かずにいるのでした。
やがてひどい雨の翌日、もうそこに蜂の姿はありません。
雨どいを伝わって地面へ流れ去ったのだろうと、主人公は想像します。
そこで使われる表現が「静かだった」と「寂しかった」の2つです。
この言い回しが、何度も登場します。
その度に読者は、同じように死の意味を考えるのです。
生き物の寂しさ
生きているということはどれほど寂しいことかということを、作者は何度も重ねていいます。
生きていることと死んでしまっていることの間に、それほどの差がないような気分にひたるのです。
これがまさに心境小説と言われる所以でしょう。
その象徴がネズミの殺されるシーンです。
首のところに魚用の串を刺し貫かれたネズミが登場します。
川の真ん中へ逃げるネズミは魚串のため、石垣をよじ登ることができません。
それをめがけて、子供や車夫が面白がって石を投げます。
全力をつくして逃げようとするネズミと、石を投げる人間との様子がさりげなく描写されるのです。
その後の文章を読んでみてください。
————————–
自分は鼠の最期を見る気がしなかった。
鼠が殺されまいと、死ぬに決まった運命を担いながら、全力を尽くして逃げ回っている様子が妙に頭についた。
自分は寂しいいやな気持ちになった。
あれが本当なのだと思った。
自分が希っている静かさの前に、ああいう苦しみのあることは恐ろしいことだ。
死後の静寂に親しみを持つにしろ、死に到達するまでのああいう動騒は恐ろしいと思った。
————————-
ここに彼の死生観がよく出ています。
この作品の末尾は次の通りです。
————————
生きていることと死んでしまっていることと、それは両極ではなかった。

それほどに差はないような気がした。
もうかなり暗かった。
視覚は遠い灯を感ずるだけだった。
足の踏む感覚も視覚を離れて、いかにも不確かだった。
ただ頭だけが勝手に働く。
それがいっそうそういう気分に自分を誘って行った。
3週間いて、自分はここを去った。
それからもう3年以上になる。
自分は脊椎カリエスになるだけは助かった。
————————–
「死」が文学における最大のテーマであることに間違いはありません。
今さらながら、そのことを痛感しました。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。