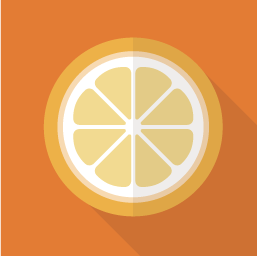モードの論理
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は「モード」ということについて考えます。
ここでは服装のことだけを扱うのではありません。
私たちが使うあらゆるモノは全てイメージの対象として処理されるというのが主題です。
小論文の課題として出題されました。
実際はかなり長い文章の一部です。
筆者は哲学者の鷲田清一。
『ひとはなぜ服を着るのか』というのが原題です。
モードといえば、誰でもすぐに服装のことをイメージするでしょうね。

しかし彼は単純にそればかりに言及しているワケではありません。
著作には他にも『モードの迷宮』など、人が服を着ることについての本質的なポイントに焦点をあてたものがあります。
問1は課題文を読んでここに示された人間の特性を考えなさい、というのが問題です。
問2は未来の社会においてよりよく生きるためのあなたの考えを示しなさい、というものです。
全文は長いので、一部だけを掲載します。
—————————
わたしたちは服を、よれよれになったり擦り切れたりという風に、着られるギリギリのところまで着ることはめったにありません。
特に上着は、流行遅れな感じがしだすとなんとなく着にくくなります。
マイカーでもポンコツになってエンストばかり、もう動かないというところまで乗る人は珍しいようです。
モード変換(モデルチェンジ)がなされると、ついそちらに気がなびいて、買い替えてしまうという人がほとんどではないでしょうか。
まだ着られるけれど、もう着られない。
まだ乗れるけれどもう乗れない。
物へのわたしたちの欲望は、どうしてこんな動きをするのでしょうか。
社会的記号
たんなる物的な対象ではなく、欲望の対象となっているような物をモノというふうに、仮にカタカナで表記してみましょう。
モノには単なる物的な特性だけではなく、イメージ的な特性や象徴的な意味といった、社会的な記号としての働きがあるからです。
そして現在のような高度消費社会においてはそういう社会的な記号を消費するということが、モノを選び、購入するときの基本的な動機になっている場合がほとんどです。
——————————
ここまで読んであなたはどのような感想を持ちましたか。
つまり現代を生きる人間にとってモノはたんなる物ではないのです。
そこには自ずと意味があります。

どの店に行ってもたくさんの商品が並んでいます。
ほとんどの商品はそれほどに機能の違いがありません。
日常的に使うのであれば、どれでも十分なのです。
しかし消費者はあえて選びます。
本当に私たちは自分で選んでいるのでしょうか。
むしろそこにある記号を選ばされているといった方が正確なのかもしれません。
そのことを筆者は次のように述べています。
もう少し読んでみましょう。
売る側の論理
売る側から言うと、こうなります。
テレビや洗濯機、音響機器とか自動車といった、たいていの耐久消費財がどの家庭にもゆきわたって、商品としては飽和状態です。
そして品質もほとんど差異がないということになってくると、売る側は機能にいろいろとプラスアルファをつけたり、さらにイメージや記号としての特性を色々に付加したりします。

現代のTVコマーシャルを見てもすぐわかるように、モノは、現代では、その機能とは別の次元で人を誘惑するようになっています。
商品が飽和状態になったとき、販売者はモノの機能的価値に差異はほとんどないわけですから、今度はモノへの欲望をいかにかきたてるかという方向に関心をシフトしていきます。
欲望の対象ではなくて欲望そのものの生産です。
現代のコマーシャルで商品の機能をこと細かに説明しているようなものはほとんどありません。
いろんなタレントを使って、さまざまな映像や音楽を使って、イメージで人々の欲望を疼かせることに躍起になっています。
他者の視線
高度消費社会の問題点がうまくまとめられていますね。
つまり現代はモノを買っていないのです。
商品に付随している社会的な記号を消費しているにすぎないのです。
モノを選んだり購入するときの基本的な動機になっているものはなにか。
それはイメージです。
つまりモードの影響を受け続けているということです。
1番わかりやすいのがコマーシャルでしょう。
商品の機能を説明しているものなどはありません。
タレント、映像、音楽のコラボレーションでイメージを喚起します。

それだけにタレントの不祥事などは最も嫌われます。
実態がないだけに、欲望をかきたててくれるイメージを持った人だけが必要とされるのです。
ポイントはなんといっても「他者の視線」でしょう。
商品に差がないとしたら、それを他人がどう評価するかという1点が大切です。
洋服、時計、靴。
全てが意味を持たなくてはなりません。
他者から見て、それをモードとして身につけている人間が評価されるのです。
それだけにイメージを構成する服飾というものの持つ効果は予想以上に大きいのです。
モードの波
鷲田清一の論理にブレはありません。
現代の消費財は全てモードの波をかぶります。
そのいい例が「無印」ですね。
ノーブランドです。
これは反モードの姿勢をさりげなく提出したもう1つのモードです。
それさえも現代はモードの中に組み込んでいきます。
ドレスダウンをすることが最もSDGsの現代にふさわしいとなれば、あらゆる方法を使って自然志向を強調します。
ユニクロなどのファストファッションもその1つでしょう。
着古したフリースを再生して新たなものにする。
そこに1つのコンセプトが生まれます。
企業理念そのものです。
いかがでしょうか。
あなたはこれらの考えを全てまとめて、未来社会の構図を描くことができますか。

より自由に人間性を発揮するために何が可能なのか。
思考の自由を巨大なIT企業に奪われる不安はないのか。
それを十分に示していかなければ、内容のある論文にはならないでしょう。
AIに支配される多チャンネル化が本当に自分の望む情報になっているのかどうか。
細かな検証をせずに、情報の渦に巻き込まれることがあってはなりません。
スマホやパソコンなどの端末からは得られない、自分独自の経験をより深める方法を考えなければならないでしょう。
そうしたものが自分の周囲にあるという安心感が、より深い考察を保証することになるのです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。