胸にしみる
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はスタジオジブリのアニメ「千と千尋の神隠し」の主題歌について書きます。
断っておきますが、ぼくはジブリの映画を全て見ているわけではありません。
トトロなどはかわいいので何度も見ましたけどね。
「千と千尋の神隠し」にしても20年以上も前の作品です。
なにをいまさらの感があります。
ところがこの歌を最近たまたま耳にして、なぜか胸にしみました。
ずいぶん何度も聞いているはずなのに、と最初思いました。
コード進行が特別に複雑なワケでもありません。
どこにでもあるごく平凡なものです。

誰もがになんの気なしに歌っているのではないでしょうか。
ぼく自身、歌詞をここまで真剣に読み取ろうとしたのは初めてのことです。
なぜひきつけられたのか。
その理由もはっきりとはしません。
偶然、youtubeでみた動画がすばらしかったからです。
オリジナルの作品の歌手、木村弓さんについては、少しだけ知っていました。
小さなハープを手に持ちながら、歌っている様子は何度か見ています。
これがシュタイナー教育に基づいた楽器だというのは、今回はじめて知りました。
実は最近、別の人が歌っている動画をみたのです。
高校生くらいの女性が歌っていました。
韓国で流された歌番組です。
東亜樹というのがその人の名前です。
ご存知でしょうか。
彼女はいろいろな歌を歌っているようですが、なぜかこの曲だけに心惹かれました。
透明な声
日本の番組とは趣向が違い、何人かの日本人が登場していました。
その中で唯一、ぼくをとらえたのは、彼女の声の質です。
非常に透明感のある声でした。
歌詞と声がみごとに融合し、清浄な空気を醸し出していました。
テロップに流れる歌詞に着目したのは、ごく自然な流れです。
それが「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」でした。
このアニメについては、何も言うことがありません。
テレビで目にしたことはありますが、いつも部分的な視聴に終わっていました。
今回、この歌から作品とはじめて正対したわけです。
歌にひきつけられました。
理由は1つです。
歌詞の中に生と死の関係がみごとに描かれていたからなのです。
詞を書いたのは覚和歌子さんという作詞家です。
どんな人なのか、最初全く知りませんでした。

覚さんは2002年に「ゼロになるからだ」という散文詩集を上梓しています。
読んでみました。
巻頭の詩には鬼が登場します。
最後の詩は自分が死ぬことと、ふと出かけた陶芸展の話です。
器をつくるという話が、祈ること意味しているように感じました。
自分の死を予感して書いたもののようです。
最後に詩人の谷川俊太郎が文章を寄せています。
「ゼロになるからだ」という言葉に彼女の人生が見えると。
生きている不思議と死んでいく不思議の境に、いつもゼロがたゆたっているという事実があることを強調していました。
歌詞
何度も聞いてはいましたが、よく読むと最後の数行などは特に心を打ちますね。
———————————–
呼んでいる胸のどこか奥で
いつも心踊る夢を見たい
かなしみは数えきれないけれど
その向こうできっとあなたに会える
繰り返すあやまちのそのたびひとは
ただ青い空の青さを知る
果てしなく道は続いて見えるけれど
この両手は光を抱ける
さよならのときの静かな胸
ゼロになるからだが耳をすませる
生きている不思議死んでいく不思議
花も風も街もみんなおなじ

呼んでいる胸のどこか奥で
いつも心踊る夢を描こう
かなしみの数を言い尽くすより
同じくちびるでそっとうたおう
閉じていく思い出のそのなかにいつも
忘れたくないささやきを聞く
こなごなに砕かれた鏡の上にも
新しい景色が映される
はじまりの朝の静かな窓
ゼロになるからだ充たされてゆけ
海の彼方にはもう探さない
輝くものはいつもここに
わたしのなかに見つけられたから
ゼロになるからだ
キーワードは「ゼロになるからだ」です。
この表現は「死」を意味するものなのか。
あるいは「生」を意味するのでしょうか。
この言葉に向かって、この詩ができあがっているような気がしてなりません。

最後の2行に、結局もとめたものは自分の外にはなかったという事実がつきつけられています。
求めるものはつねに自分の内側にしかないという厳粛な真実です。
たまたま、文春ジブリ文庫を読んでいたら、この歌が出来上がった時のトピックスが載っていました。
まるで運慶が木の中に埋もれていた仏を掘り出した時の話に似ています。
夏目漱石の『夢十夜』に出てきますね。
どうしてもこれだけはここに載せたかったので、転写します。
木村弓の話
次のコンサートの準備をしていましたら、ふっと出てくるメロディがあったんです。
それが何度も何度も繰り返し浮かんでくるんです。
この忙しい時におかしいなって思いながら、でもいいメロディのような気がしたので書き留めておきました。
そしてまた一カ月ほど経った頃でしょうか。
その譜面を何気なく見直してみましたら、ただ明るいというのではなく、心の深いところから湧いてきて弾む気持ちの乗る、とてもいいメロディだなと思いました。
これにあう、いい言葉はないかと考えていましたら、
「呼んでいる 胸のどこか奥で いつも心踊る 夢をみたい」っていう一つのフレーズが浮かんだんです。
目の前の現実を変える本当のエネルギーの元になるものは、心の中で心踊る夢を繰り返し体験することだと私は常々思っているのです。
このフレーズはそういう思いから出てきました。
でもその後はなかなかうまく言葉が続きませんでした。
そこで私の友人で、詩作朗読家の覚和歌子さんにお願いしてみたんです。
そうしましたら、私の漠然とした思いを覚さんは不思議なほどちゃんと汲み取ってくれて、メロディに本当にあう詞を作ってくれたんです。
最初は出来上がった曲を宮崎さんに送るつもりはありませんでした。
映画にあうかどうかは別として、この曲ができたことをきっと一緒に喜んでくださるんじゃないかと思い、お送りすることにしました。
覚和歌子の話
木村さんが「こんなのが浮かぶんだけど、企画にあうかもしれないと思って」と言いながら口ずさんでくれたメロディがとてもよかった。
透明で健気で、少しだけかなしくて。
私は「ああきっといい曲になるな」と予感したのを覚えています。(中略)
「さよならのときの」から四行は確実に何かに書かされている感覚がありました。
そう「生きている不思議 死んでいく不思議」のところですね。
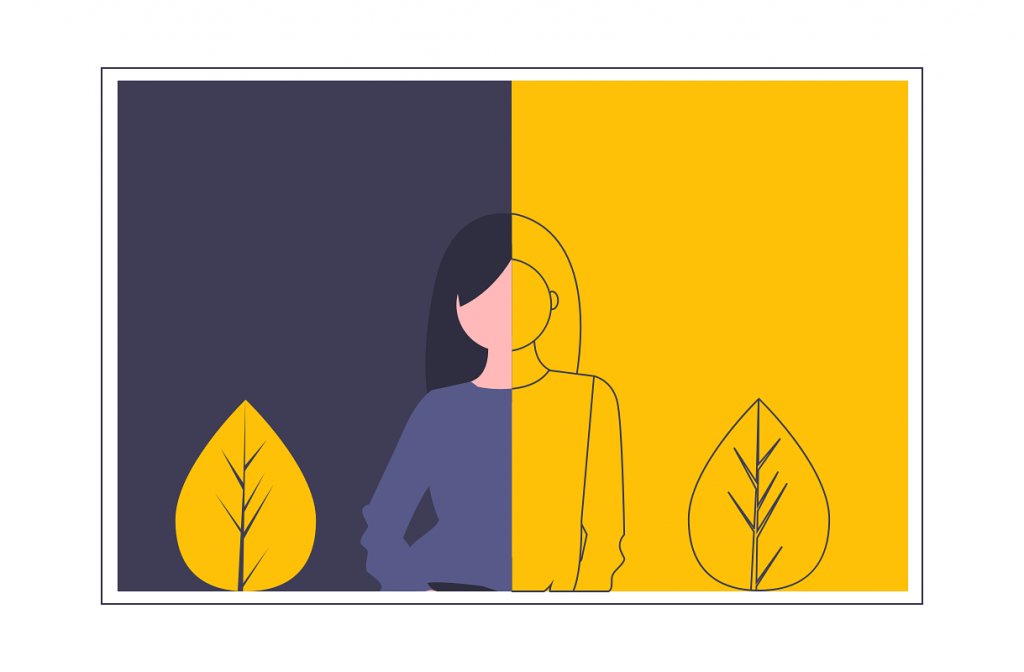
書きながら悲しくもないのに、涙があとからあとから出てきて止まらなかった。
普通じゃないことが起こっていると思いました。
こういう風に生まれる作品というのは、聴き手の意識の深いところに触れる力を持っていることが多いです。
自分は本当は誰なのかというような、存在の根源的な問いと関わっている意識の層ですね。
そこに届くことによって、聴き手一人1人の生き方が変わってくれたりするとうれしい。
歌が生まれる時の不思議な出会いの話です。
ゼロになるからだは寂しい表現ですけれど、一面では豊饒なのかもしれません。
そのことを告げたくて、今回は文章をまとめてみました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


