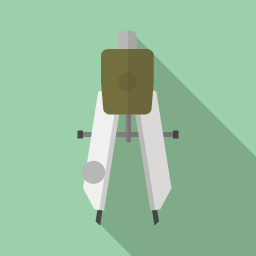詩人・石原吉郎
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は詩人、石原吉郎の壮絶な記録『望郷と海』を読みます。
彼の思想のエッセンスが最も端的に凝縮されている本がこれです。
この教材は高校の教科書に所収されています。
新指導要領では「論理国語」に入っているようです。
飽食の現代を生きているぼくたちには、全く想像もできない日々の暮らしです。
彼は日本の敗戦とともに、ソ連に抑留され、シベリアの強制収容所で8年間過ごしました。
1963年、スターリン死去に伴う特赦により、日本に戻ることができたのです。
ここで扱った「ある共生の経験から」は全てが実体験に基づく話です。
世界大戦後、ソ連各地の収容所には、多くの日本人が捕虜として非人間的な抑留生活を強いられました。

人々は飢えと寒さのなかで、あらゆる物が不足した状態で生き延びていかねばならなかったのです。
お互いの生命を削り取っていく敵とは、すなわち収容所の仲間そのものでした。
抑留者同士が共生していかなければ、死が目の前に迫ってきます。
人間関係をどう作り上げるのかといったレベルの話ではありません。
命を繋ぐためには、自我を抑える以外になかったのです。
偶然組み合わされた他人と、どう生きていったのか。
そのあまりにも生々しい現実が、ここには示されています。
生物は生命を維持するために、何かを食べなくてはなりません。
しかし食糧事情が厳しく、反ソ・スパイの罪で重労働25年の判決を受けた彼にとって、生き残るために必要な食料も満足には与えられませんでした。
石原が収容された第3分所も例外ではなく、食糧の組織的な横流しも行われていました。
収容者約800人のうち約2割が収容後半年の間に栄養失調が原因で亡くなったと言われています。
事実はあまりにも重いです。
食事の分配の様子を読みましょう。
これが彼らのいう「共生」の実態なのでした。
食事の分配
食事の分配の様子をここに掲載します。
あまりにも苛酷な現実の前に、言葉を失ってしまいます。
しかし人間というものは、結局こうなるだろうと十分に予想のつく内容です。
哀しいけれど、生きていくということの実態なのでしょう。
他人に対して優しくありたいと考えても、収容所の貧しい食事の前では、とても考えられませんでした。
軍属や民間人が主に収容された第3分所では、兵士用の飯盒を所持していた人が少なく、食事は2人分が1つの飯盒で配られました。
——————————–
1つの食器を2人で付き合うのは傍から見れば何でもない風景だが当時の私たちの 這い回るような上が想像できるなら この食感 組がどんなに激しい神経の消耗であるかが理解できるだろう。
私たちはほとんど 奪い合わんばかりの勢いで飯盒の1/3にも満たぬ粟がゆをあっという間に食い終わってしまうのである。
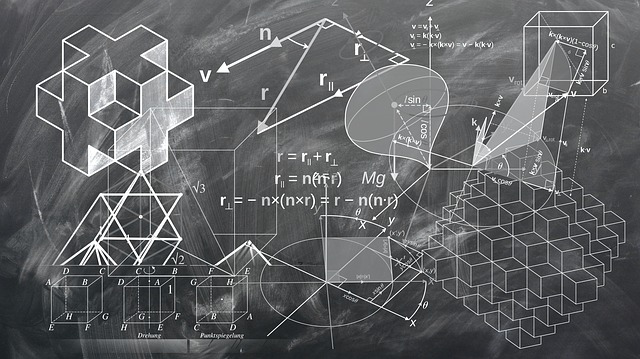
結局、こういう状態が長く続けば、腕ずくの争いにまで至りかねないことを予感した私たちはできるだけ公平な食事が取れるような方法を考えるようになった。
まず、両方が厳密に同じ寸法の匙を手に入れ、交互にひと匙ずつ食べる。
しかしこの方法も、同じ大きさの匙を2本手に入れることがほとんど不可能であり、相手の匙のすくい加減を監視する煩わしさもあって、あまり長続きしなかった。
次に考えられたのは飯盒の中央へ板または金属の仕切りを立てて、内容を折半する方法である。
しかしこの方法も、飯盒の内容が均質の粥類の時はいいが、豆類などのスープの時は底に沈んだ豆を公平に両分できず、仕切りの隙間から水分が相手の方へ逃げる恐れもあって間もなく廃った。
最後に考えついたのは、缶詰の空缶を2つ用意して、飯盒から別々に盛り分ける方法である。
幸いなことに、ソ連の缶詰の企画は2、3種類しかないので、寸法の揃った空き缶を作業現場などからいくらでも拾ってくることができる。
分配は 食缶組の1人が、多くの場合1日交代で行ったが相手に対する警戒心が強い組ではほとんど 1回ごとに交代した。
ひと匙ずつ豆を
この食事の分配というのが大変な仕事で、柔らかい粥の場合はそのまま両方の空缶に流し込んでその水準の平均すればいいが、粥が固めの場合は、押し込み方によって粥の密度にいくらでも差ができる。
したがって、分配の間中、相手は瞬きもせずに、一方の手元を凝視していなければならない。
さらに、豆類のスープなどの分配にいたっては、それこそ大騒動で、まず水分だけを両方に分けて平均した後、ひと匙ずつ豆をすくっては交互に空き缶に入れなければならない
分配が行われている間、相手は一言も発せず、分配者の手元を睨みつけているので、はた目には、この2人が互いに憎み合っているとしか思えないほどである。
こうして長い時間をかけて分配を終えると、次にどっちの缶を取るかという問題が残る。
これにも色々な方法があるが、最も広く行われたやり方では、まず分配者が相手に後ろを向かせる。
そして一方の缶に匙を入れておいて、匙の入った方は誰が取るかと尋ねる。
相手はこれに対しておれとかあんたとか答えて、缶の所属が決まるのである。
この場合、相手は答えたらすぐ後ろを振り向かなくてはならない。

でないと、分配者が相手の答えに応じて、素早く匙を置き換えるかもしれないからである。
——————————-
収容者たちは2人ずつの食罐組を組み、1人が飯盒に入った食事を同じ大きさの空き缶2つに分けることから始めました。
その間、もう1人は瞬きもせず相手の手元をにらみつけています。
豆が沈んだ薄いスープも、雑穀の3分粥も、完全に『公平』に分けなければならないのです。
互いの生死がそれにかかっていたからです。
しかし公平ということを徹底させることが、いかに難しいか。
この文章を読んでいると、実感させられます。
もっと悲しいのは寝る時の様子です。
「共生」と「連帯」
食事を分け終わると、途端に食罐組は解消します。
眠るときになると、2人1組の「共生」と「連帯」の関係は再度立ち上がります。
真冬の外気が氷点下30度に達するこの地で、収容者たちは1人に1枚支給されるだけの毛布を、2人が、1枚を床に敷き1枚を体にかけて、体をくっつけあって眠るしかありませんでした。
いま私に、骨ばった背を押しつけているこの男は、たぶん明日、私の生命のなにがしかをくいちぎろうとするだろう。

だが、すくなくともいまは、暗黙の了解の中で、お互いの生命をあたためあわなければならないのだと石原は書いています。
「共生」「連帯」などという響きのいい言葉を使っていていいのかとふと考えてしまいますね。
「それは、助け合って生きる、というような甘いものではなく、不信と憎悪を向け合う人間同士が、自分が生き延びるために結ぶぎりぎりの関係にほかならなかった」と彼は書いています。
それが、石原の社会に対する根本的な姿勢となりました。
彼にとって収容所での生活からしか、人間を捉えることはできません。
全てがその原風景に繋がってしまうのです。
戦後の日本を見る時の目も、当然収容所での体験が光源になります。
真の意味で他者と共生することは可能なのか。
それは許されるのか。
彼の詩は現在も出版されています。
最も代表的なのが以下の4作品です。
『石原吉郎詩集』(現代詩文庫、1969、思潮社)
『新選・石原吉郎詩集』(新選現代詩文庫、1979、思潮社)
『続・石原吉郎詩集』(現代詩文庫、1994、思潮社)
『石原吉郎詩文集』(2005、講談社文芸文庫)
ぜひ、手にとって読んでみてください。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。