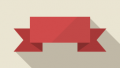扇の的
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『平家物語』の中で最も人気のある那須与一の話をしましょう。
この話は1185年に起きた屋島の戦いでの出来事を描いています。
源氏と平氏が川を隔てて、向き合った合戦の場面です。
源氏方は陸地に陣をとり、平家方は舟の上にいます。
そこへ弓の名人で源氏の武将、那須与一が登場します。
平家の船の先の竿には、扇の的がありました。
時刻は酉の刻、現在の午後6時頃のことです。
沖には平家の武将たちが、舟を一面に並べて見物しているのです。
この時の状況を少し整理してみましょう。
どんな場面が脳裏に浮かぶでしょうか。
この時、那須与一に与えられた命令は非常に難しいものだったということが、よくわかるはずです。
まず、馬に乗ったままで矢を放たなければなりません。
さらに風が激しく、波も高いので舟の先に掲げられた扇がつねに動いていました。
標的までの距離は約70メートルほどありました。

春先の夕方6時頃なので、視界が不明瞭です。
大将、源義経からの指示なので失敗は絶対に許されません。
緊張感がピークに達していたことが、すぐに想像できると思います。
岸辺と舟の上では、源氏と平氏が注視しているのです。
失敗したら、死が待っていると考えるのが普通でしょう。
平家の前で恥をかくということは、源氏の武将にとって許されません。
死んで責任を取る以外の道はないのです。
那須与一はあらゆる神々と、自らの氏神にも成功を祈りました。
緊張感の増すシーンです。
ぜひ、声に出して読んでみてください。
本文
ころは二月十八日の酉の刻ばかりの事なるに、折節北風激しくて、磯(いそ)打つ波も高かりけり。
舟は、揺り上げ揺り据ゑ漂へば、扇も串に定まらずひらめいたり。
沖には平家、舟を一面に並べて見物す。
陸(くが)には源氏、くつばみを並べてこれを見る。
いづれもいづれも晴れならずといふ事ぞなき。
与一目をふさいで、
「南無八幡大菩薩(なむはちまんだいぼさつ)、我が国の神明(しんめい)、日光の権現(ごんげん)、宇都宮、那須の湯泉大明神(ゆぜんだいみょうじん)、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ。
これを射損ずるものならば、弓切り折り自害して、人に二度(ふたたび)面(おもて)を向かふべからず。
今一度本国へ迎へんとおぼしめさば、この矢外させ給ふな」と心の内に祈念して、目を見開いたれば、風少し吹き弱り、扇も射よげにぞなつたりける。
与一、かぶらを取つてつがひ、よつぴいてひやうど放つ。
小兵(こひょう)といふ条、十二束三伏(じゅうにそくみつぶせ)、弓は強し、浦響くほど長鳴りして、あやまたず扇の要際(かなめぎわ)一寸ばかり置いて、ひいふつとぞ射切つたる。
かぶらは海に入りければ、扇は空へぞ上がりける。
しばしは虚空(こくう)にひらめきけるが、春風に一揉み二揉み揉まれて、海へさつとぞ散つたりける。

夕日のかかやいたるに、みな紅の扇の日出だしたるが、白波の上に漂ひ、浮きぬ沈みぬ揺られければ、沖には平家、ふなばたを叩いて感じたり。
陸には源氏、えびらを叩いてどよめきけり。
あまりのおもしろさに、感に堪へざるにやおぼしくて、舟のうちより、年五十ばかりなる男の、黒革をどしの鎧着て、白柄(しらえ)の長刀(なぎなた)持ったるが、扇立てたりける所に立つて舞ひ締めたり。
伊勢三郎義盛(いせのさぶろうよしもり)、与一が後ろへ歩ませ寄つて、「御定(ごじょう)であるぞ、つかまつれ。」と言ひければ、今度は中差取つてうちくはせ、よつぴいて、しや頸(くび)の骨をひやうふつと射て、舟底へ逆さまに射倒す。
平家の方には音もせず、源氏の方にはまたえびらをたたいてどよめきけり。
「あ、射たり」と言ふ人もあり、また、「情けなし」と言ふ者もあり。
現代語訳
時は二月十八日、午後六時頃のことでした。
折から北風が激しく吹いて、岸を打つ波も高かったのです。
舟は、揺り上げられ揺り落とされ上下に漂っているので、竿頭(かんとう)の扇もそれにつれて揺れ動き、しばらくも留まることはありませんでした。
沖には平家が、海上一面に舟を並べて見物しています。
陸では源氏が、馬のくつわを連ねてこれを見守っていました。
どちらを見ても、まことに晴れがましい情景とはこのことです。
与一は目を閉じて、「南無八幡大菩薩、我が故郷の神々の、日光の権現、宇都宮大明神、那須の湯泉大明神、願わくは、あの扇の真ん中を射させたまえ。
これを射損じれば、弓を折り、腹をかき切って、再び人にまみえる心はありません。
いま一度本国へ帰そうとおぼしめされるならば、この矢を外させてくださいますな」
と念じながら、目をかっと見開いて見ると、うれしいことに風も少し収まり、的の扇も静まって射やすくなっていました。
与一は、かぶら弓を取ってつがえ、十分に引き絞ってひょうと放ちました。
小兵とはいいながら、矢は十二束三伏で、弓は強いのです。
かぶら矢は、浦一帯に鳴り響くほど長いうなりを立てて、あやまたず扇の要から一寸ほど離れた所をひいてふっと射切りました。
かぶら矢は飛んで海へ落ち、扇は空へを舞い上がりました。
しばしの間空に舞っていたが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっと散り落ちたのです。

夕日に輝く白い波の上に、金の日輪を描いた真っ赤な扇が漂って、浮きつ沈みつ揺れているのを、沖では平家が、舟端をたたいて感嘆し、陸では源氏が、えびらをたたいてはやし立てました。
あまりのおもしろさに、感に堪えなかったのでしょう。
舟の中から、年の頃五十歳ばかり、黒革おどしの鎧を着、白柄の長刀を持った男が、扇の立ててあった所に立って舞を舞いました。
そのとき、伊勢三郎義盛が、那須与一の後ろへ馬を歩ませてきて、「命令であるぞ、射よ」と命じたので、今度は中差を取ってしっかりと弓につがえ、十分に引き絞って、男の頸の骨をひょうふっと射て、舟底へ真っ逆さまに射倒しました。
平家方は静まりかえって音もしません。
源氏方は今度もえびらをたたいてどっと歓声を上げたのです。
「ああ、よく射たものだ」と言う人もあり、また、「心ないことを」と言う者もありました。
戦いの厳しさ
船の先にある扇の的を射る挑戦を受けることの意味は、どのようなものだったのでしょうか。
矢を射るとき、那須与一は心の中で神に願いをかけました。
「南無八幡大菩薩」は、弓の神です。
「日光の権現」「宇都宮」「那須の湯泉大明神」は、与一の故郷である栃木の神です。
神に祈りをささげた与一が目を開くと、あれだけ激しく吹いていた風が少し弱まっていました。
与一が最初に放った矢は、「かぶら矢」です。
戦いを始める合図に使う、音を立てて飛ぶ矢のことです。
与一は体が小さく弓を引く力も弱いのです。
このかぶら矢は「十二束三伏」の長さがありました。
ちなみに普通の矢は、十二束です。
「1束」は指4本分の幅、「1伏」は指1本分の幅といわれています。
つまり普通の矢よりも指3本分の幅が長いということなのです。
さらに弓も強いものを使っていたので、矢は鳴り響くほどのうなりを立てて飛んでいきました。
夕日が輝いている中、白い波の上に、金色の日の丸が描かれた真っ赤な扇が漂って、浮いたり沈んだりしたのです。
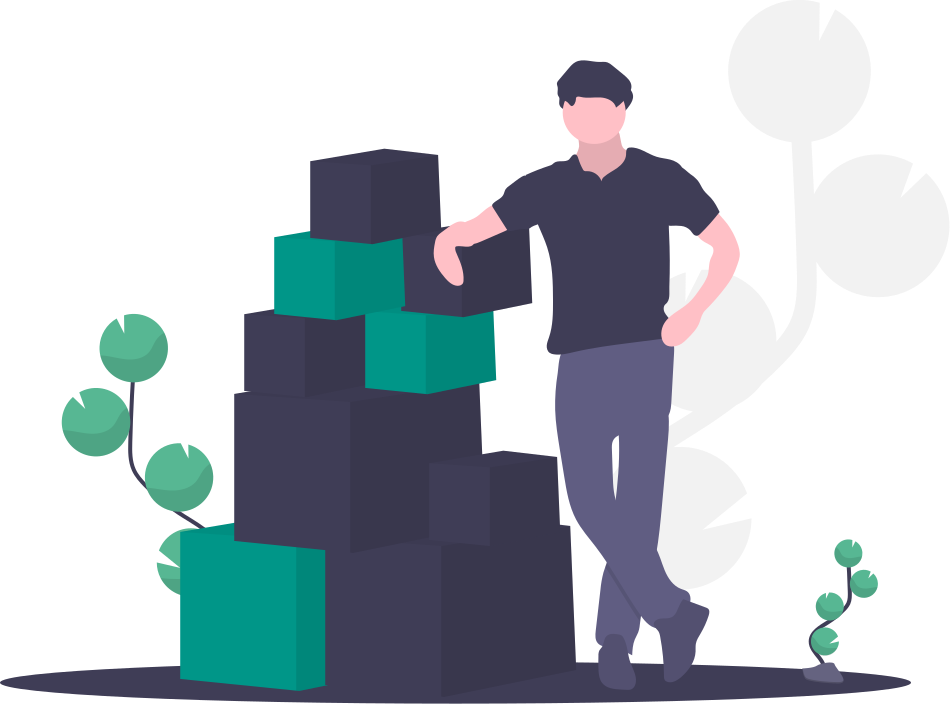
那須与一は扇を射切ったあと、もう一度矢を放っています。
みごとに扇を射ったことに感動した平家の男が、扇があった場所で舞を舞い始めたからです。
なぜそんなことをしたのかについては、諸説あります。
少し調子にのったとも考えられますね。
源氏方の大将、義経はこの男を矢で射るように命じました。
今まで味わってきた源氏の苦しさが、栄華に溺れていた平家のお前たちにはわからないのかという、義経の無念さがあったともとれます。
最後のところに「あ、射たり」と言う人もあれば、「情けなし」と言うひともあったと書かれていますね。
この部分の意味は、今でもいろいろに解釈されています。
与一が男の頸を射ると、平家の方はみんな静まりかえってしまいました。
これが戦さの本質なのかもしれません。
心の怯みを少しも許さないということなのでしょう。
相手に隙をみせないことが、ここでも必要だったと思われます。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。