痛みと癒し
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は哲学者、河野哲也氏の『境界の現象学』から痛みの問題を考えてみます。
ポイントは痛みとは何かということです。
普段、あまり考えたことのないテーマですね。
しかしちょっと視線をずらすと、確かにその通りだと感心してしまいます。
例えば歯の痛みを想像してください。
自分の痛さをどう他人に伝えたらいいのか。
その反対に、他の人の痛みを引き受けろと言われても、無理な話です。
つまり人は自分の痛みを伝えることも、人の痛みを感じることも、不得手なのです。
では痛みとは、本質的に他者とは無関係なものなのでしょうか。
そのメカニズムを少し考えてみましょうというのが、この本の主題です。

本文中にでてくる例として、一般の市民と負傷兵の場合があります。
簡単にいえば、鎮痛剤の要求の度合いに差があるというのです。
あなたはどちらの場合の方が多いと思いますか。
同じくらいの傷の時、市民と兵士はどちらが、より鎮痛剤を欲しがるのでしょうか。
正解は市民です。
同じ損傷で8割の市民が鎮痛剤を要求したのに対して、兵士においては3割にしか過ぎなかったという例があります。
もちろん、症状は同じです。
理由がわかりますか。
野戦病院の兵士に比べて、安全な病院で危険を脱することができた人たちは、安心感から、より痛みを覚えたのです。
緊張がとぎれたことで、より痛みが増したといえるのです。
本文の一部を読みましょう。
本文
痛みは、人間関係や社会的な文脈によっても異なってくる。
看護学の専門家である西村ユミの研究によれば、患者の痛みは、看護婦の患者への態度や認識によって変化する。
ある末期ガン患者は、ペインスケールで痛みを客観的に表現することを拒否し、絶えることなく痛みを訴えていた。
しかし、看護師が患者の痛みに同調して、介護の反応をしたときには、その患者は痛みを訴えるのを忘れて、和らいだ表情になったという。
あるいは 医療人類学のヘルマンによれば、社会集団によって痛みへの対処の仕方や扱い方が変わってくる。
ある社会集団は、痛みに耐えて我慢することを推奨する。
自分の痛みを他人に隠すことは、道徳的に望ましい態度として、社会的に評価される。
だが、こうした態度が、他の社会集団で同じように評価されるとは限らない。
患者が医療関係者に対して痛みについてどのように伝え、表現するかは、その社会の価値に大きく影響を受ける。
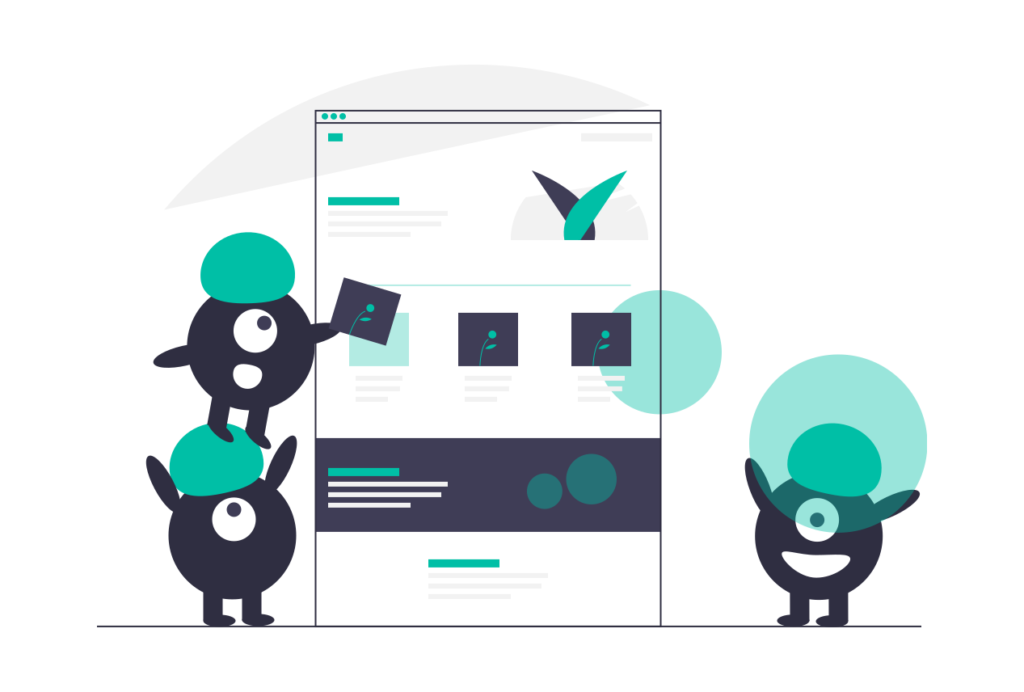
こうしたエピソードからわかることは、痛みとは、身体的損傷によって機械的に生じる反応ではなく、自分への対処とケアを求める反応であり、援助を請う動作だということである。
この求めは、しばしば「痛みの情動的側面」と呼ばれている。
痛みとは、自分自身に対して行動を求める呼びかけであると同様に、他者に対しても向けられている呼びかけなのだ。
意識の志向性とは、私たちの意識が対象を狙う矢のように対象に向かうということではない。
あらゆる経験は、文脈の中で他の経験と関連性を持つことによって意味づけられる。
志向性とは対象を意味づける働きなのだから、それは経験の対象を他の対象と結びつけ、文脈の中に埋め込み、対象をより大きな経験の中に部分として位置づける働きである。
痛みも同様に、それがどのような形で人々に対処されケアされるかによって、異なって意味づけられる。
痛みが志向的な経験であるのは、それが単に自己身体についての経験だからではなく、それがより大きな文脈の中に置かれるからである。
ユニークな視点
興味深い文章ですね。
あまり考えたことがないテーマなのではありませんか。
「痛み」という身体的な現象が、実はそれほど単純なものではないというのです。
筆者は痛みが何によって変化するといっているのでしょう。
注意深く読んでみると、そこにキーワードがあることに気づきます。
「社会的意味」「人間関係」の2つです。
つまりこの両者の間におかれることによって、痛みは変化するのです。

患者がどのような状態に置かれているのかによって、明らかに痛みは異なります。
もっと要約すれば、痛みとは自分自身に対して行動を求める呼びかけなのです。
私をケアして欲しいという訴えです。
援助を求める動作とも呼べるのです。
痛みという経験が個人的なものを超えて、他者への反応を求めます。
それを受け取る一連のプロセスがあって、はじめて意味を持つということなのです。
逆に言えば、どのようにケアをしてもらえるのかという期待とともに、そこに投げ出されています。
介護者の態度によって、痛みの程度は大きく変化するという事実も指摘されています。
自分の痛みを他人に隠すことが、道徳的に望ましい態度として評価される時、人は明らかに痛みを訴えようとはしません。
自分が患者として身体の痛みを訴えられる場所に至ったとき、以前よりも急速に痛みが増したという経験を持ったことはありませんか。
そこで痛みを訴えられるという安心感が、痛みを増幅させたのです。
これこそが、人間の関係の中にある痛みです。
子供が泣く時
子供が転んで泣く時の様子を思い出してください。
地面に倒れこんで、膝を擦りむいたとしましょう。
倒れた当座はすぐに泣き出したりはしないものです。
当然、痛みはあります。
親が次の瞬間、子供の名前を呼び、傍に飛んでいった時から、痛みが頂点に達するのです。
そして泣くという行為が始まります。

その間に数秒間のブランクがあります。
これがまさに人間関係の痛みとでもいえるのではないでしょうか。
社会的な意味も同様です。
自分自身への援助を請う行為として、呼びかけに相当する泣くというプロセスが痛みを増幅します。
自分の痛みがどのような性質のものであるのかというのは、興味深い内容です。
おそらく今までに考えたことのないテーマなのではないでしょうか。
この機会に自分で小論文をまとめてみてください。
「痛みとは何か」という曖昧なタイトルでもかまいません。
このケースだと、心の痛みという視点からも書けます。
肉体的な痛みだけでなく、大きな視点から捉えることも可能です。
ぜひ、試みてください。
必ず、添削してもらうことです。
友人では無理です。
信頼できる先生にお願いしてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


