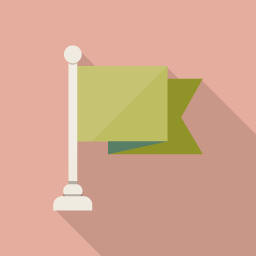捨て耳の効用
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家、すい喬です。
再び新しい年を迎えました。
去年はコロナ禍でさんざんでした。
高座の数もめっきりと減りましたのでね。
落語はライブでないと空気感がどうしてもつかめない芸です。
もちろん、無観客リモート落語もありでしょう。
しかしそこまではやる気がしません。
お帰りの時、お客様に声をかけていただく。
その嬉しさはかけがえのないものです。
落語の世界でよく使われる言葉に「捨て耳」というのがあります。
ご存知ですか。

面白い表現ですね。
この言葉はどこからきたものなのでしょう。
柳家権太楼師の『大落語論』にも、その師匠の柳家つばめが書いた『落語の世界』にも載っています。
捨て耳というのは、人と話をしている時に神経を別のところへたえず持って行く行為をいうそうです。
噺家の前座修行は実につらい理不尽なことの連続です。
師匠方にお茶をいれたり、着物をたたむのはあたりまえのことです。
その間に太鼓をたたいたり、座布団を返したりといくらでも用事はあります。
しかし言われたことをただやっているだけでは評価されません。
つねに意識を先へ先へと働かせていなければならないのです。
高座から噺家が降りてくるのに、太鼓の準備をしていないというのはNGです。
神経を細かく使う
お囃子を終えたら、師匠の帰りの靴を出す必要もあります。
お茶を差し替えることも大切です。
ありとあらゆるところに神経を使わなくてはならないのです。
師匠方の靴も草履もみな似たようなものばかりです。
その中で、帰る人の靴をどうやって見分けるのかということも、立派な修行の一つになるのです。
売れている師匠の靴は明らかに高そうで、いいものなのです。
それを瞬時に見抜く目も必要です。
あらゆることに心配りをすることが、芸人として生きていく上でもっとも大切なのです。
そんなことがどうして必要なのか。
人の心の先を読むことで、芸の心が磨かれるとよく言います。
人間の心理の奥までわかっていなければ、誰も笑ってくれません。
こころに大きな空洞をつくる作業ができなければ、人を笑いの渦に巻き込むことはできないのです。
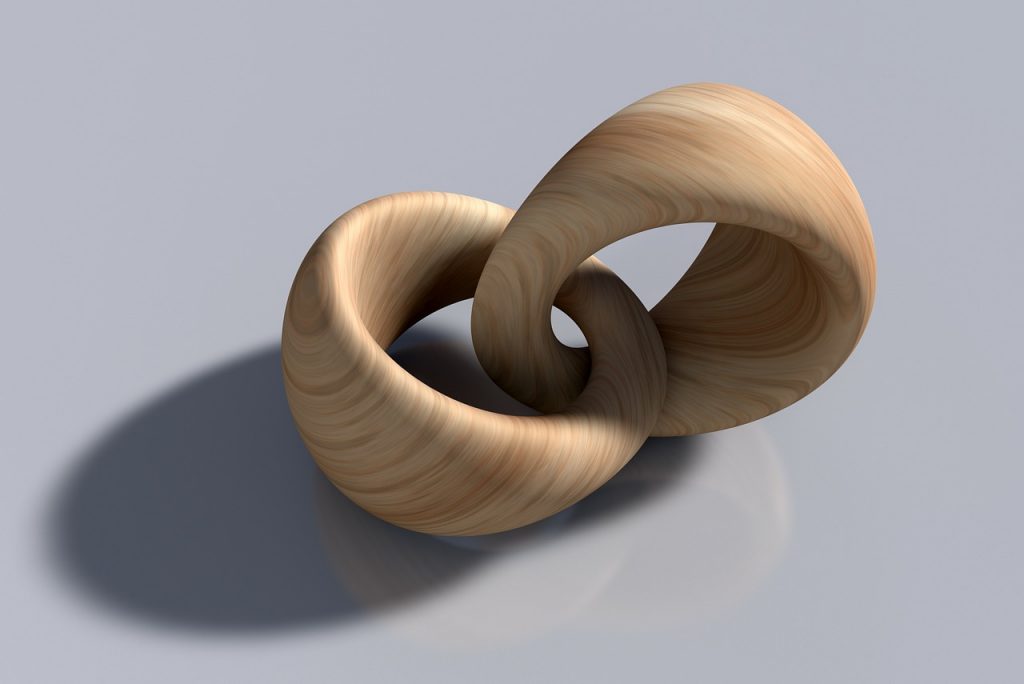
さらに楽屋内で仕事をしながら、先輩の落語を聞き続けることも大切です。
噺を覚え、独特の間を盗むのです。
教えてもらっているうちは、まだ一人前とは言えません。
捨て耳の効用がここにあるのです。
力のある者だけが生き残るというのは、あらゆる場面において通用する鉄則なのではないでしょうか。
しかしいくら運をつかんでも、それを次に伸ばすことができるのかどうかは、またその人自身に負うというのも厳しい現実です。
捨て耳という行為はどの世界にも通用する生きるための方法論かもしれません。
そしてそれを他人に悟られてはならないのです。
実はここが一番難しいのではないでしょうか。
余計なことは言わない。
しかしじっと聞いている。
神経を研ぎ澄ましてつねに全身の感度を最高にしておくのです。
師匠の噺をよく聞いていると、次第に噺家の間になっていきます。
これが怖いですね。
アマチュアがいくらうまいといっても、前座には勝てません。
プロの洗礼は想像以上の力を持っています。
まくらを黙って聞く
落語にはまくらと呼ばれる導入部分があります。
柳家小三治には『まくら』という本があるくらいです。
文明批評と呼んでもいいものも数多く入っています。
噺家はこのまくらで客の反応をみます。
そして極端なことをいうと、その場で演目を替えたりもします。
それだけにまくらを話すときの真剣さは並々のものではありません。
もちろん、演者はそのことを客に悟られてはなりません。
小三治の『まくら』はあまりにも評判が良かったので、続編も出版されています。
一度手にとってみてください。

噺に入る時、よく引き合いにだされる川柳にも味わい深いものがありますね。
特に欲に目がくらんだ人物が登場する時に使うのがこれです。
欲深き人の心と降る雪は積もるにつれて道を忘るる
実に含蓄のある表現じゃありませんか。
人間の欲望には際限がありません。
そのことが人生を大きく狂わせる材料ともなります。
あらゆる犯罪には欲望がからんでいます。
捨てる勇気、諦める勇気も同時に必要です。
まくらを聞きながら、噺の世界を広げるのも捨て耳の効用です。
前座修行中に何気なく、高座で師匠方が話すことを絶えず耳に入れておきます。
それを膨らませてやがて自分のものにしていくのです。
芸は盗むしかありません。
上手になるには
これが1番の難問ですね。
もちろん答えはありません。
しかし1つの方法論として次のようなことが言えます。
それはいつも冷静な第三者の視点を持っていることです。
能の大成者、世阿弥の言葉でいえば「離見の見」です。
もう1人の自分の目で自分自身を冷静に見る。
自分の芸に酔いしれてはダメです。
たとえ登場人物が泣くシーンでも噺家本人が泣いてはいけないのです。
さらに自分の芸が陽か陰かを知らなければなりません。
どうやっても自分のカラーを抜け出すことはできないからです。
それぞれの演者が持っている特性を最大限に生かすということでしか、噺の大成はありません。
漫才との違いは相手と対立してはいけないところにあります。
隠居が与太郎の話に本気でつっこむと、笑いが出なくなります。

つねにゆとりをもって流していくのです。
音楽で言うところの裏拍ということになるのでしょうか。
この裏拍が実は想像以上に大切なものなのです。
ただの相鎚の場合も、リズムが重要なものとなります。
さらに複数の人を声で演じ分けないということもあります。
無理に高い声を出したり、低くしたりする必要はありません。
声の質をよく捕まえること、さらにブレスをどうとるのかによっても、お客様の気が変化していきます。
一人一人の演者にはそれぞれ独自の間合いというものがあるのです。
客席の空気をつかんだら離さないために、その間が必要となります。
ブレスと深い関わりがあるのです。
これらの全てを寄席の楽屋で習得していかなくてはいけません。
捨て耳がどれほど大切か。
噺家にとって寄席は道場なのです。
ホール落語だけでは得られない貴重な場所だということが理解していただけたでしょうか。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。