小説とは何か
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は作家、三島由紀夫の小説論について考えてみます。
彼の作品についてはかなりこのブログでも書きました。
リンクを貼っておきます。
後で読んでみてくださいね。
三島はどういう人間だったのでしょうか。
一言で言えば、早熟の天才です。
あまりにも世の中を早くに見過ぎてしまい、成人した後の日々は余生に近いものだったかもしれません。
ぼくもいつの頃からか、三島由紀夫の小説を読むようになりました。
装飾華美な彼の言語体系の中に分け入るのは、並々のことではありません。
代表作と呼ばれる小説にはどれも毒があります。
『金閣寺』『仮面の告白』「豊穣の海』『近代能楽集』。
しかしその光源から発する熱に一度触れると、次々と作品を読まずにはいられなくなるのです。
そういう意味では不可解な存在だともいえるでしょう。
教科書で扱われている作品はごく限られています。
初期のもの数編と、評論がいくつかある程度です。

学校教育が求める倫理の対極に、位置する作家であったからかもしれません。
今回は彼が、何を「小説」と考えたのかというテーマについて考えてみたいのです。
その糸口となるのが柳田国男が1910年に発表した『遠野物語』です。
柳田国男の初期三部作の一作です。
岩手県遠野地方に伝わる逸話や伝承などを記した説話集です。
遠野地方に住む佐々木喜善という人から、聞いた話を次々と筆記し採録していったものです。
日本民俗学の先駆けとも称されています。
青空文庫に入っていますので、いつでも読めます。
民話の世界
遠野地方を旅行すると、かつての日本人の暮らしが見て取れます。
民話は確実に今も生きているのです。
天狗、河童、座敷童子など妖怪に関わるものや、山人、神隠し、あるいは土地の神や行事、風習に関するものなど、内容は多岐に渡っています。

その中の1つの話に、三島が小説を感じたということの意味をここでは探ってみましょう。
小説とは何かというのは永遠のテーマですね。
実に難解でもあり、魅力的です。
今も多くの小説が生まれていますが、どれが本物なのかと言い出すと、それだけで答えが出なくなってしまいます。
三島由紀夫のエッセイがそのためのヒントになるかも知れません。
彼が何を小説だと考えていたのかということが、よく表現されています。
柳田国男の『遠野物語』を引用し、その考えの一端を示しているのです。
本文
私が小説を嫌いになったかと言えば、そうも言えない。依然私は「小説」を探しているからである。
評論を読んでも歴史を読んでも私が小説を探していることに変わりはなく、その点は、法律の講義を聞きながら、その中に一生懸命「小説」を探していた学生時代の私と、今の私が別人になったわけではない。
私は最近、そういう自分の楽しみのためだけの読書として、柳田国男氏の名著『遠野物語』を再読した。(中略)
私のあげたいのは、第22節の次のような小話である。
————————————
佐々木氏の曾祖母年よりて死去せし時、棺に取り納め親族の者集まりきてその夜は一同座敷にて寝たり。
死者の娘にて乱心のため離縁せられたる婦人もまたその中にありき。
喪の間は火の気を絶やすことを忌むがところのふうなれば、祖母と母との二人のみは、大なる囲炉裡の両側に坐り、母人は傍らに炭籠を置き、おりおり炭を継ぎてありしに、ふと裏口の方より足音してくる者あるを見れば、亡くなりし老女なり。
平生腰かがみて衣物の裾の引きずるを、三角に取り上げて前に縫いつけてありしが、まざまざとその通りにて、縞目にも目覚えあり。
あなやと思う間もなく、二人の女の坐れる炉の脇を通り行くとて、裾にて炭取にさわりしに、丸き炭取なればくるくるとまわりたり。
母人は気丈の人なれば振り返りあとを見送りたれば、親縁の人々の打ち臥したる座敷の方へ近より行くと思うほどに、かの狂女のけたたましき声にて、おばあさんが来たと叫びたり。
その余の人々はこの声に睡りを覚ましただ打ち驚くばかりなりしといえり。
————————————-
この中で私が「あ、ここに小説があった」と三嘆これ久しゅうしたのは、「裾にて炭取にさわりしに、丸き炭取なればくるくるとまわりたり」というくだりである。
ここがこの短い怪異譚の焦点であり、日常性と怪異との疑いようのない接点である。

この一行のおかげで、わずか1ページの物語が、百枚二百枚のえせ小説よりも、はるかにみごとな小説になっており、人の心に永久に忘れ難い印象を残すのである。
その原因はあくまでも炭取の回転にある。
炭取が「くるくる」と回らなければ、こんなことにはならなかったのだ。
炭取はいわば現実の転位の蝶番のようなもので、この蝶番がなければ、われわれはせいぜい「現実と超現実の併存状態」までしか到達することができない。
それから先へもう一歩進むには、どうしても炭取が回らなければならないのである。
しかもこの効果が一にかかって「言葉」にある、とは、驚くべきことである。
小説は言葉
三島由紀夫がどれほど言葉を大切にしていたかがよくわかりますね。
このエッセイにもそのことが書いてあります。
現実を震撼させることによって作家の書きつけた言葉を現実化する根源的な力が備わっていなければ、小説にはならないとしています。
その力はいかにもそれらしい長い叙述から生まれるものではないとも言っています。
たった一行でもいいのです。
短く圧縮されていてもかまわないのです。
ああ、そんなことがありうるなというリアリティに満ちていることが大切です。
それはどこにあるのか。
おそらく作家の脳裡に浮かぶ言霊の塊りの中にあるに違いありません。
いくら小説だといってみても、作者自身を動かすものもなく、読者も何も感じようがないという作品は無意味です。
仕掛けが大切なのではありません。
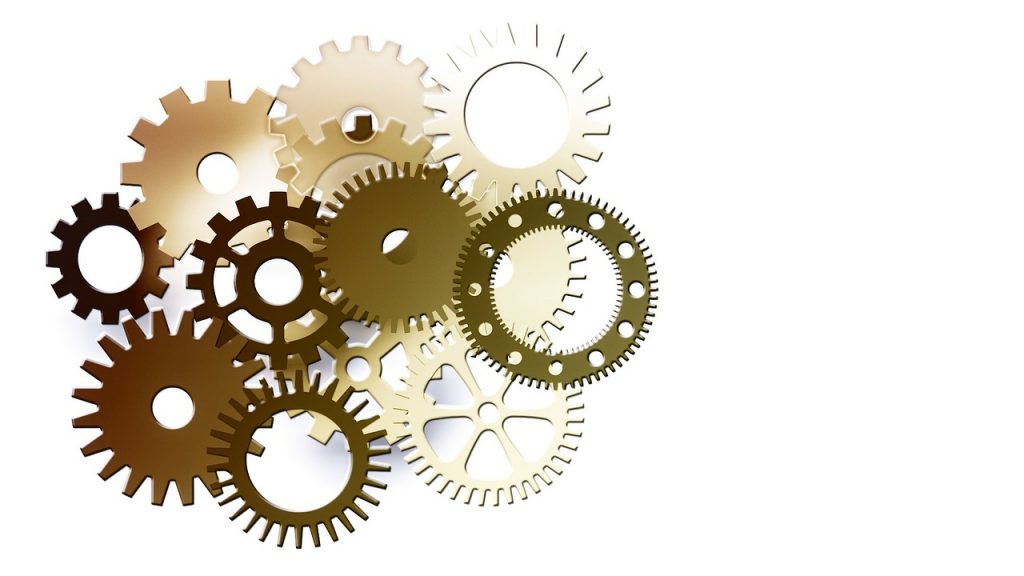
書き手が想像もつかないような力が、どこからか舞い降りてきて、それが読者を動かすかどうかが問題なのです。
「現実と超現実」とのあわいに到達したのかどうか。
それを確認する作業はどのようにしたらいいのでしょうか。
これが最大の難問ですね。
残念ながらぼくにはわかりません。
しかしその言霊の力に頼る以外に方法がないというのも事実です。
その瞬間に出会うために、作家は書き続けるのでしょう。
原稿用途やパソコンに向かって、ひたすら言葉を埋め、打ち続けるのです。
一方が現実であり、一方が超現実でもかまいません。
それが確かに起こりうると確信させられるだけの言葉が必要です。
神の領域に頼るしかないのかもしれません。
三島由紀夫はその降臨を信じていたのでしょうね。
そのために、日々認識世界を超えるための修練を続けたのです。
言葉が現実になりうる瞬間がくるまで、ペンを動かしたに違いありません。
それが成功したのかどうか。
あなたも考えてみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。




