倹約が根本
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『徒然草』184段を取り上げます。
選択科目の古文ではよくやる単元です。
内容も読み取りもそれほど難しくありません。
ここに示されていることは、いつの時代にも通用する真理ではないでしょうか。
金利が低い上に物価が高騰している現代、人々はすぐに資産運用に走りがちです。
政府も銀行に預けているだけではお金は増えませんと声高に叫んでいます。
しかしここに書かれている倹約の考え方が、全ての基本でしょう。
人間は贅沢にすぐ慣れてしまいます。
今までの生活の基準をそれほど簡単に落とすことはできません。
それが1番怖いのです。
相模の守時頼という人は、鎌倉幕府第5代の執権です。
才色兼備の政治家として知られました。
執権は政治の全権を握っています。
権力者の持つ傲慢さを母親は知っていたのでしょう。
だからこそ、自分が息子を戒めるためにも、破れた明かり障子を貼ってみせたのです。
それも全てを一時に新しくするのではなく、破れたところだけを小刀で器用に切り取っては、ひとますずつ貼りました。

これにはさすがに城の介義景もあきれたとみえます。
次官の地位にいる彼の目からみれば、執権の母親がやる仕事ではありません。
そのうえ、破れたところだけを繕っているのです。
つい若い者にやらせると口走ってしまいました。
その時の母親である禅尼の言葉が重いですね。
普段ならそれでもいい。
しかし今はダメです。
私がこのように修繕する姿を息子に見せなくてはならないのですと呟きました。
その話をわざわざ『徒然草』に書いた兼好法師はどんな気分だったのでしょうか。
全文をまず読んでみましょう。
ぜひ、声に出してみてください。
原文
相模守時頼の母は、松下禅尼とぞ申しける。
守を入れ申さるることありけるに、すすけたる明かり障子の破ればかりを、禅尼、手づから、小刀して切り回しつつ張られければ、兄の城介義景、その日の経営して候ひけるが、
「賜りて、某男に張らせ候はん。さやうのことに心得たる者に候ふ。」
と申されければ、
「その男、尼が細工によも勝り侍らじ。」

とて、なほ、一間づつ張られけるを、義景、
「皆を張り替へ候はんは、はるかにたやすく候ふべし。まだらに候ふも見苦しくや。」
と重ねて申されければ、
「尼も、後は、さはさはと張り替へんと思へども、今日ばかりは、わざとかくてあるべきなり。物は破れたる所ばかりを修理して用ゐることぞと、若き人に見習はせて、心づけんためなり。」
と申されける、いとありがたかりけり。
世を治むる道、倹約を本とす。
女性なれども、聖人の心に通へり。
天下を保つほどの人を子にて持たれける、まことに、ただ人にはあらざりけるとぞ。
現代語訳
相模守時頼の母は、松下禅尼と申し上げました。
相模守をご招待申しあげなさることがあった時に、すすけた障子の破れたところだけを、禅尼が、自分の手で、小刀であちこち切っては張っていらっしゃいました。
そこで禅尼の兄の義景という、その日の世話や準備などをしてそばにお控え申しあげていた方が、
「その仕事はこちらにやらせていただいて、下男に張らせましょう。障子の張り替えに熟達している者でございます。」
と申しあげなさったところ、
「その人は、きっとこの私の細工より優れておりますまい。」
と言って、やはり、ひとますずつお張りになったので、義景は
「全部の障子を一度に張り替える方が、ずっと容易でございます。あちこち古いところと新しいところが、まだらになってはかえって見苦しくはございませんか。」
と重ねて申しあげなさったところ、
「私も、時頼の来訪が済んだ後は、さっぱりと張り替えようと思います。しかし、今日だけは、ことさらにこうしておくのがよいのです。

物は破れたところだけを修理して用いるものだと、若い人に見習わせて、気づかせようとするためなのです。」
と申しあげなさったことは、たいそう立派で滅多にないことでした。
世の中を治める道理は、倹約を根本とするのです。
この禅尼は女性ですが、聖人の心に通じていると思われます。
天下を治めるほどの人を子としてお持ちになった方は本当に、凡人ではなかったと聞いております。
光と障子
最近は和室のない家も随分増えましたね。
畳は想像以上に高価です。
さらに数年ごとに裏返しにしたり、張り替えたりしなければなりません。
結局、フローリングの洋室の方が手軽だということになるのでしょう。
しかし日本の気候風土には、障子が大変有効なのです。
紙は湿気を通します。
乾きすぎるのを避けることもできるのです。
もう一つは明り取りとしての要素です。
明瞭すぎない光の要素として、日本間には大変よくあっています。
谷崎潤一郎が『陰翳礼讃』というエッセイの中で述べている通りです。
蝋燭の光が、障子に揺らめく姿には、日本人の美意識が見られます。
障子というものが、日本の建築に取り入れられるようになったのは、かなり時代が進んでからなのです。
安徳天皇が祖父である平清盛に抱かれながら障子に穴を開けたところ、清盛が「この障子を大切に蔵にしまっておきなさい」と命じたエピソードが残されています。
平安時代後期頃からと考えた方がいいでしょう。
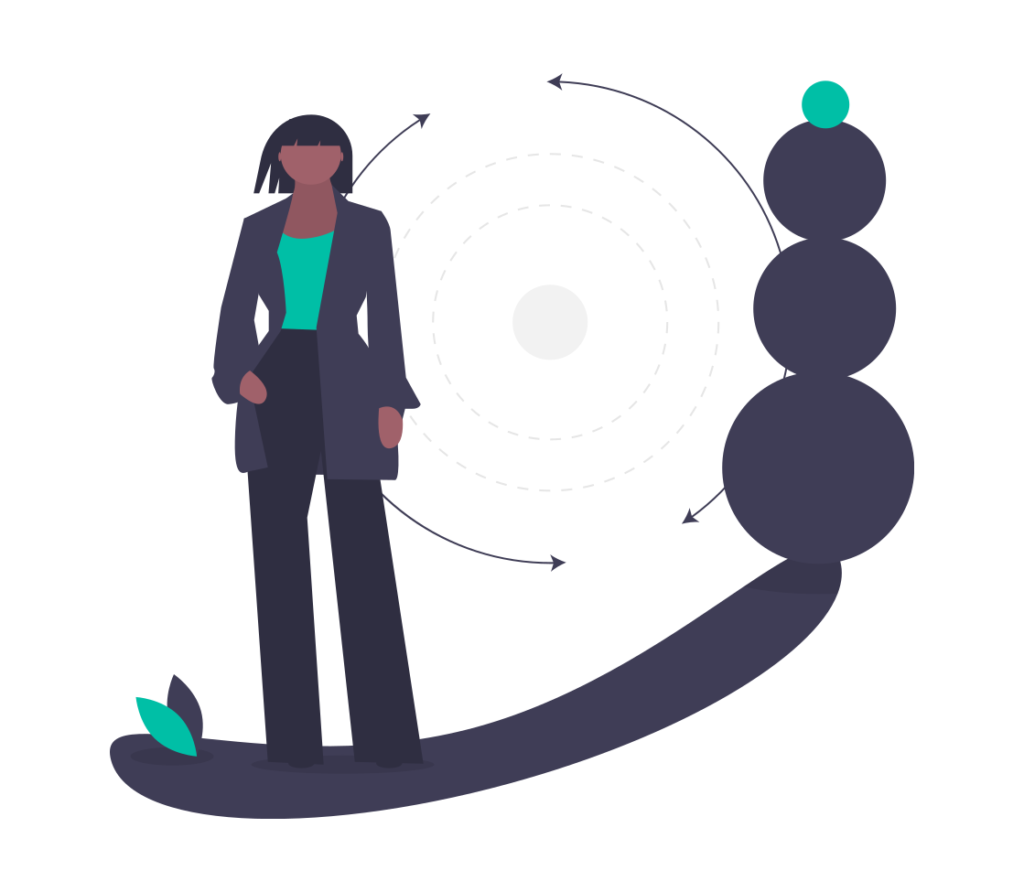
『徒然草』以前の随筆に障子の話があったかどうか。
これから調べてみたいと思います。
多く用いられるようになったのは、和紙の生産量が増加した南北朝時代からです。
閉めても外の光が漏れ通ってくることから、よく使われるようになりました。
紙は貴重品でしたからね。
政治の実権を握った息子に、自ら倹約の意味を教えようとした母親に対して、兼好法師はひたすら感じ入っています。
「ただ人」ではないと言い切っているのです。
女性(にょしょう)なれども聖人の心に通へりと書いています。
政治にお金がかかるというのは、今ではごくあたりまえのこととして通用しています。
だからこそ、こういう話の持つ意味がより深いのではないでしょうか。
「ふすま」とは違う「障子」の味わいを感じとってください。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。


