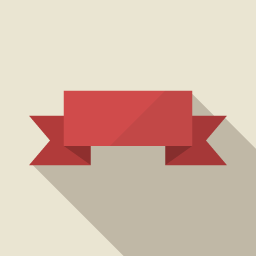赤い繭
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は安部公房の小説をとりあげます。
今までに読んだことがありますか。
毎年夏に出ている「新潮の100冊」という読書案内にも、必ず彼の作品が収められています。
代表作『砂の女』です。
何度、この本の紹介を授業でしたかわかりません。
授業が終わって、少し時間があった時、よく生徒に紹介しました。
映画化もされています。
主人公の女を演じたのが岸田今日子だといったら、少しはイメージの浮かぶ人がいるかもしれません。
無機質でおどろおどろしい女性を演じさせたら、彼女の右にでる人はいませんでした。
監督が勅使河原宏、音楽が武満徹です。

砂のざらざらした感触が特異な映画でした。
これほどに不思議な読後感のある作品も珍しいですね。
彼の代表作です。
ストーリーは現実離れしたものです。
海辺の砂丘に昆虫採集にやって来た男が、女が1人で住む砂の中にある家に閉じ込められるという話です。
アリジゴクのような構造になっているので。脱出しようとしても、砂が崩れて逃げられないのです。
男は最初はあらゆる方法で、何度も逃げることを考えます。
しかしそのうちにここから逃げても、また似たような会社と家を往復する生活が繰り返されるだけだということに気づくのです。
やがてある日、脱出の機会が訪れます。
村の人間が飲み水を下すロープを引き上げるのを忘れてしまったのです。
男はその頃、砂の生活に順応し始めていました。
女との暮らしに幸福感さえ感じるようになっていたのです。
一言でいえば、市民社会の日常性をその場で取り戻したといえます。
人が生きることの本当の意味とは何かという、根本的な問題を考えさせる問題作です。
世界の言語に翻訳され、今でも多くの人に読まれています。
ある人はカフカの『変身』との類似性を論じています。
また実存主義の持つ、根本的な実在の概念について語ってる人もいます。
特にカミュの『異邦人』との関連を感じる人もいるようです。
アイデンティティ
安部公房は他にも話題作を次々と発表しました。
なかでも『壁』『他人の顔』『燃えつきた地図』『箱男』は有名です。
むさぼるように読んだ記憶がありますね。
それ以上によく知られているのが戯曲です。
自分の劇団を持ち、精力的な活動をしました。
最も有名なのが『友達』『棒になった男』でしょうか。
チャンスがあったら、是非舞台をみてください。
どれも不思議な感覚に彩られています。
『友達』は特にすぐれています。
人間のアイデンティティを確認するための方法が、存在するのかというのがテーマです。
難しくいえば「自同律の不安」です。
自分が自分であることをどのように証明できるのかということです。

デカルトの「コギト」という表現を聞いたことがあるかもしれません。
「我思う故に我あり」という証明方法です。
自分が誰であり、なぜここにいるかどうかということを考えていることは今、事実だというのです。
だからそのことがらを考えている自分は、確かに存在するという考え方です。
『友達』にもその論理が応用されています。
真の友達を証明する方法がこの世にあるのか。
自分が友達であるといえば、それはもう友達なのではないかという論理です。
さらにそれをわかりやすくしたのが短編『赤い繭』なのです。
高校の教科書に所収されています。
覚えている人がいるかもしれません。
小説本文
日が暮れかかる。
人はねぐらに急ぐときだが、おれには帰る家がない。
おれは家と家との間の狭い割れ目をゆっくり歩き続ける。
街じゅうこんなにたくさんの家が並んでいるのに、おれの家が一軒もないのはなぜだろう?……と、何万遍かの疑問を、また繰り返しながら。(中略)
夜は毎日やって来る。
夜が来れば休まなければならない。
休むために家がいる。
そんなら俺の家がないわけがないじゃないか。
ふと思い付く。
もしかするとおれは何か重大な思い違いをしているのかもしれない。
家がないのではなく、単に忘れてしまっただけなのかもしれない。
そうだ、あり得ることだ。
例えば……と、偶然通りかかった一軒の前に足を止め、これがおれの家かもしれないではないか。
無論他の家と比べて、特にそういう可能性をにおわせる特徴があるわけではないが、それはどの家についても同じように言えることだし、またそれはおれの家であることを否定するなんの証拠にもなり得ない。

勇気を奮って、さあ、ドアをたたこう。
運よく半開きの窓からのぞいた親切そうな女の笑顔。
希望の風が心臓の近くに吹き込み、それでおれの心臓は平たく広がり旗になって翻る。
おれも笑って紳士のように会釈した。
「ちょっと伺いたいのですが、ここは私の家ではなかったでしょうか?」
女の顔が急にこわばる。
「あら、どなたでしょう?」
おれは説明しようとして、はたと行き詰まる。
なんと説明すべきか分からなくなる。
おれがだれであるのか、そんなことはこの際問題ではないのだということを、彼女にどうやって納得させたらいいだろう?(中略)
疎外という現実
この後、男は黄昏の町をさまよい歩き続けます。
すると足に突然まとわりつくものがありました。
粘り気のある絹糸だったのです。
つまんで、引っ張ると、その端は靴の破れ目の中にあって、いくらでもずるずる伸びていきます。
糸を手繰るにつれて、足がどんどん短くなっていくのです。
足がほぐれているのでした。
左足が全部ほぐれると、次は右足です。
そして、男は消滅してしまいます。
後に残ったのは大きな空っぽの繭でした。
夕日が赤々と繭を染めています。
誰からも妨げられない自分の家だと男は悟ります。
しかしそこに大きな疑問が残るのです。
家が出来ても、今度は帰ってゆく自分がいないという現実です。

アイデンティティを失いつつある現代の人間の横顔を、これだけ痛烈に描いた短編は少ないです。
自らの足を食べて消滅する小動物の存在を連想してしまいます。
あるいは自分自身の存在が、この小説の主人公と同じだと考える人がいても不思議ではありません。
安部公房は何度かノーベル賞にもノミネートされました。
もう少し生きていたら、きっと受賞を果たしたに違いないのです。
晩年は脳の構造にたいして、強い関心を示していたときいています。
興味のある人は、『砂の女』から読み始めてみてください。
近寄りすぎると、危険な作家の1人です。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。