荒れたる宿の
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『徒然草』を読みましょう。
いつものエッセイと少し趣きが異なります。
貴公子が荒れた家に高貴な女性を訪ねるという話は、平安期の物語に多いですね。
この文章は『源氏物語』の「花散里」の段を念頭において書かれたものと言われています。
描かれているのはある日の夕方から翌朝の様子です。
一人の男性が籠居中の女性の荒れた家を訪ねました。
そこで触れた情趣の数々、一夜の思いを今も忘れがたい思い出としているという男性がその感慨を中心に叙述しています。

『徒然草』の中では懐古趣味の章段のひとつと言えます。
男女が一夜をともにした翌朝の別れを「後朝(きぬぎぬ)の別れ」といいます。
情趣あふれるその光景と女性の風情を懐かしむ男性の心象風景を読み取ってください。
『徒然草』は無常観に基づく思想を色濃く残しています。
章段の中には、自然や人生を論じたものが多いです。
しかしなかにはここに示されたような王朝趣味の文章などもあり、兼好法師の持っていた多面的な要素をみてとることもできます。
『徒然草』は1330年頃に成立されたといわれています。
この時期は『古事記』『日本書紀』などの古代文学と、さらに平安期文学、また松尾芭蕉などにみられる江戸文学の、ちょうど折り返し地点に近いところに位置しています。
その成立年代を同時にチェックしておくと、より理解が深まると考えられます。
本文
荒れたる宿の、人目なきに、女のはばかる事あるころにて、つれづれと籠り居たるを、或人、とぶらひ給はんとて、
夕月夜のおぼつかなきほどに、忍びて尋ねおはしたるに、犬のことことしくとがむれば、下衆女の出でて、「いづくよりぞ」と言ふに、
やがて案内(あない)せさせて入り給ひぬ。
心ぼそげなる有様、いかで過ぐすらんと、いと心ぐるし。
あやしき板敷にしばし立ち給へるを、もてしづめたるけはひの、わかやかなるして、「こなた」と言ふ人あれば、たてあけ所狭(せ)げなる遣戸(やりど)よりぞ入り給ひぬる。
内のさまは、いたくすさまじからず、心にくく、火はあなたにほのかなれど、もののきらなど見えて、俄かにしもあらぬ匂ひ、いとなつかしう住みなしたり。
「門よくさしてよ。雨もぞ降る、御車は門の下に。御供の人はそこそこに」と言へば、「今宵ぞやすき寝は寝(ぬ)べかめる」と、うちささめくも忍びたれど、程なければ、ほの聞ゆ。

さて、このほどの事どもも、こまやかに聞え給ふに、夜深き鳥も鳴きぬ。
来しかた行末かけて、まめやかなる御物語に、このたびは鳥もはなやかなる声にうちしきれば、明けはなるるにやと聞え給へど、
夜深く急ぐべき所のさまにもあらねば、少したゆみ給へるに、隙(ひま)白くなれば、忘れがたき事など言ひて、立ち出で給ふに、
梢も庭もめづらしく青みわたりたる卯月ばかりのあけぼの、艶にをかしかりしを思(おぼ)し出(い)でて、桂の木の大きなるが隠るるまで、今も見送り給ふとぞ。
現代語訳
荒れた宿で、人の出入りもないところに、ある女性が世間をはばかる物忌みなどの時期であるので、所在ないままに籠っていました。
ある人が、お訪ねなさろうとして、夕月がほの暗いおぼろな夜に、忍んで尋ねていったときのことです。
犬がやかましく怪しんで吠え立てるので、召使いの女が出てきて、「どこからいらっしゃいました」と訊ねます。
その下女にそのまま案内させて邸内にお入りになりました。

心細いご様子で、どんなふうにお過ごしになっていたのだろうかと、たいそう気の毒に思われました。
みすぼらしい板敷にしばらくお立ちになっていると、しとやかな感じで、若やいだ声で、「こちらへ」と言う人があるので、閉めるのも開けるのも窮屈そうな引き戸からお入りになりました。
家の中の様子は、外に比べてさほどは荒れていません。
奥ゆかしく、火は部屋の向うのほうでほのかに灯っています。
あたりのものの美しいさまなどが見えて、来客のためにあわてて焚いたとも思われない香の匂いが、たいそうゆかしい感じで住んでいるようです。
「門をしっかり閉めてください。雨が降るといけませんからね。牛車は門の下に。お供の人々はどこそこへ」と誰かが言うと、
「今夜こそ安心して寝られるでしょう」と、ひそひそ囁いているのも、忍び声だけれども狭い部屋なので、ほのかに聞こえてきます。
さて、近況を細やかに情をこめてお話申し上げなさるうちに一番鶏が鳴きました。
これまでのことやこれからのことにわたって、こまやかに物語なさっていると、今夜は鶏が高い声でしきりに鳴くようです。
もう夜が明けたのだろうかとお聞きになりましたが、夜の明けきらないうちに人目を避けて急いで帰らなければならないような場所柄でもないので、少しゆっくりしていました。
戸の隙間が白くなってきたので、忘れがたい事など話して、立ち出でなさった時、梢も庭も目の覚めるようにどこまでも青々としています。
4月頃の夜明けが、優美だった、あの頃のことをお思い出しになって、そのあたりを通る時は今でも女性の家の庭にあった大きな桂の木が隠れるまで、今でもその男性はじっと見ていらっしゃるということです。
章段の持つ意味
この文章は、『徒然草』の中で、人目を避けて生きる女性のもとを、ある男性が忍んで訪ねた一夜の様子を描いたものです。
荒れた宿、夕月、犬の声、遣戸の狭さ、ほのかな灯、夜深く鳴く鳥、卯月のあけぼのなど描かれたものがそれぞれがきわめて小さなものなのに、空間と時間の移ろいがていねいに重ねられています。
ここで描かれているのは、恋の高揚ではありません。
心細さ、つつましさ、互いを思いやる慎み、別れの余韻といった、静かな人間の心の情景です。
兼好法師は、なぜこのような文章を書いたのでしょうか。
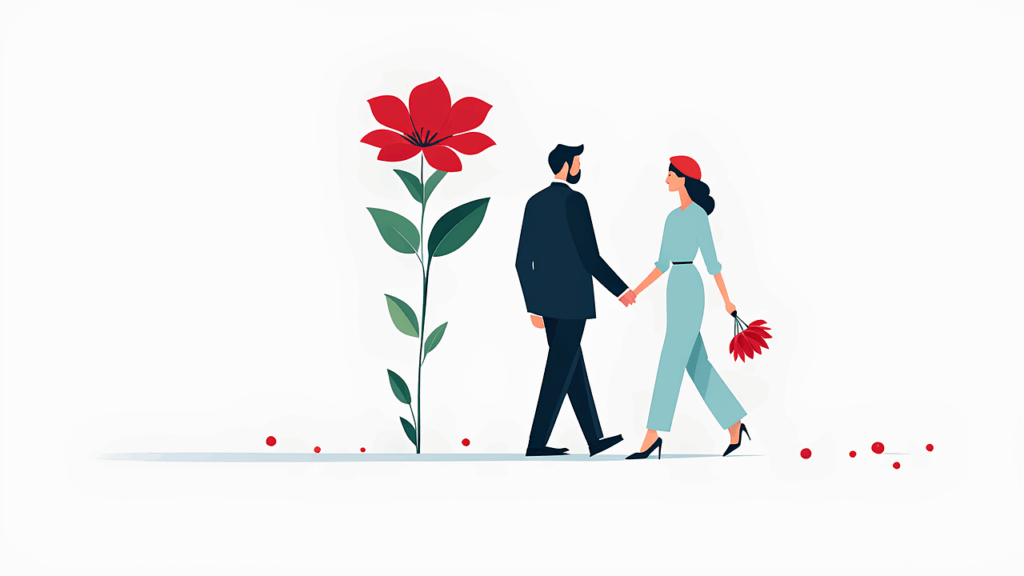
彼は恋愛そのものを賛美したかったわけではありません。
ここで兼好が描きたかったのは、華やかさを失った後にも残る、人の情の美しさです。
荒れた宿に住む女性は、社会の中心からは外れた存在です。
しかし、その住まいには、物が少なくても「心にくい」整え方、匂いに宿る生活の記憶、言葉をひそめる配慮などがあり、人間としての品位が保たれています。
兼好はここで、「栄えているかどうか」ではなく「どう生きているか」を見る目を、読者に持たせようとしていると思われます。
ストーリー全体は実にささやかなものですが、そこには余情があふれているのです。
日本の文学が好んで描いてきた小さくて弱いものに対する美を感じることもできます。
花散里との関係
この章段はしばしば『源氏物語』の「花散里」を思い起こさせるというのは、偶然ではありません。
ここで「花散里」の段の特徴を少し考えてみます。
彼女は源氏の寵愛の中心にはいませんでした。
住まいは荒れがちで、人目も少ないのです。
しかし、思いやり、落ち着き、変わらぬ情を持つ女性として描かれています。
この章段に登場する女性もまさに同じタイプで、男性を引き止めようとはしません。
また、ことさらに感情をあらわにしないのです。
別れの朝を、景色の美しさとして受け止めるという姿も、花散里的な感情の表現そのものといえます。
兼好の持っていた美学の中には理想的な恋のかたちがありました。
それによれば恋は激しさではなく、余韻にこそ品が出るという、中世的な美意識です。
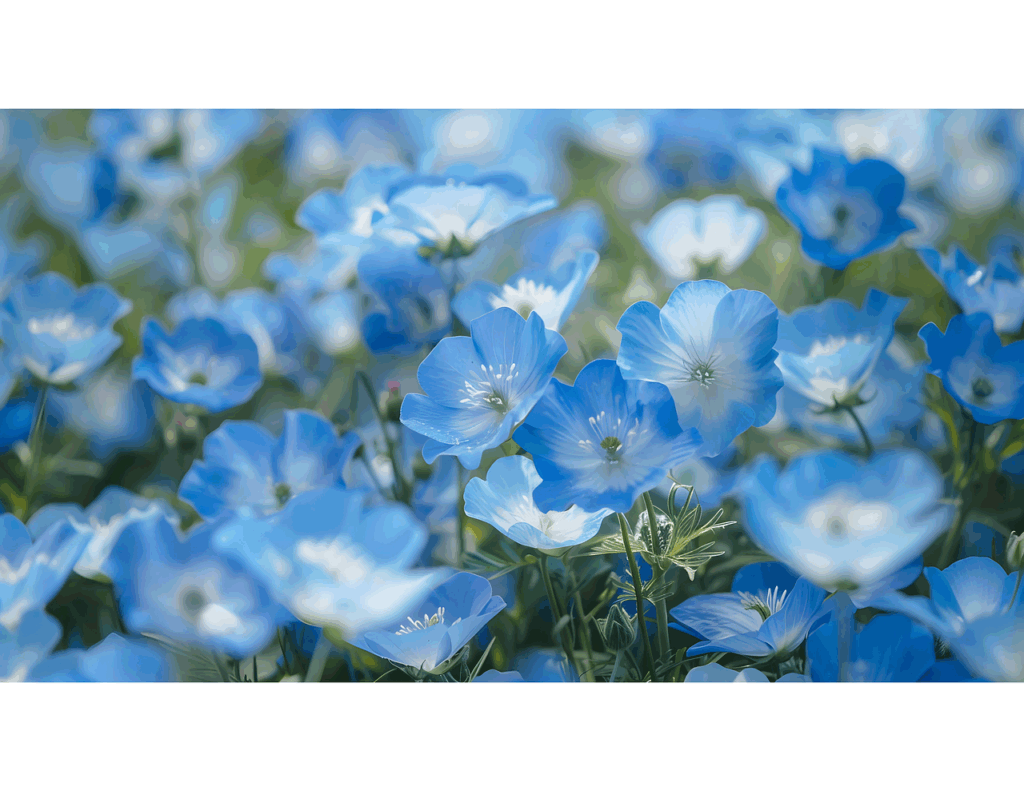
夜は深く、語りは静かで、別れはあっさりとしているのがよいのです。
だからこそ、4月のあけぼのの青さと桂の木の影に消えるまで見送る姿が、いつまでも心に残ります。
兼好は、人生で忘れがたいのは、大事件ではなく、こうした一夜なのだという感覚を持っていました。
日々の暮らしの中にある、人間の生きざまそのものです。
花散里と同じく、華やかさの外側にある美を描いたものと考えられます。
兼好が望んでいた「もののあはれ」への理解が、極めて純度高く表れた場面として読まれ続けてきたと言えるのです。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

