有明の月に
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『和泉式部日記』を取り上げましょう。
この作品は敦道(あつみち)親王との10カ月の恋愛を物語風につづった日記です。
成立は平安時代中期の1007年頃で、『源氏物語』と同時代の作品です。
作者は和泉式部とされています。
しかし異説もあります。

『和泉式部日記』は次のような場面から始まります。
最初の恋人は冷泉(れいぜい)天皇の第3皇子為尊(ためたか)親王でした。
女のもとへ通うため夜中に出歩き、流行病に感染して亡くなってしまったのです。
その弟がここでの登場人物、第4皇子の敦道(あつみち)親王です。
亡き夫の弟であった敦道親王の求愛に心を開き、2人の恋愛が深まっていく様子がこの段には描かれています。
女は和泉式部その人をさします。
敦道親王は冷泉天皇の皇子です。
兄には花山天皇と為尊(ためたか)親王がいます。
本文は絶えようとしていた2人の関係が、回復に向かう場面です。
疑心と不安をめぐって、2人の心に動揺の多い時期から、宮廷入りの話が出てくるところへ向かいます。
手習いの文を送ることによって、それぞれの気持ちが次第に寄りそうようになっていきました。
この文章の後には、女が宮に送った文の全容と、それに対する宮の返歌が綴られています。
長保五年八月、女が石山寺へ参籠すると、文のやりとりが活発になりました。
男女の心の機微はいつも微妙なものです。
ほんのわずかな心の変化が次の新たなシーンを作り出します。
本文
九月二十日あまりばかりの有明の月に御目覚まして、いみじう久しうもなりにけるかな、あはれ、この月は見るらむかし、
人やあるらむ、と思おぼせど、例の童ばかりを御供にておはしまして、門かどをたたかせ給たまふに、女、目を覚まして、よろづ思ひ続け臥ふしたるほどなりけり。
すべてこのごろは、折からにや、もの心細く、常よりもあはれにおぼえて、ながめてぞありける。
あやし、誰たれならむと思ひて、前なる人を起こして問はせむとすれど、とみにも起きず。
からうじて起こしても、ここかしこの物に当たり騒ぐほどに、たたきやみぬ。
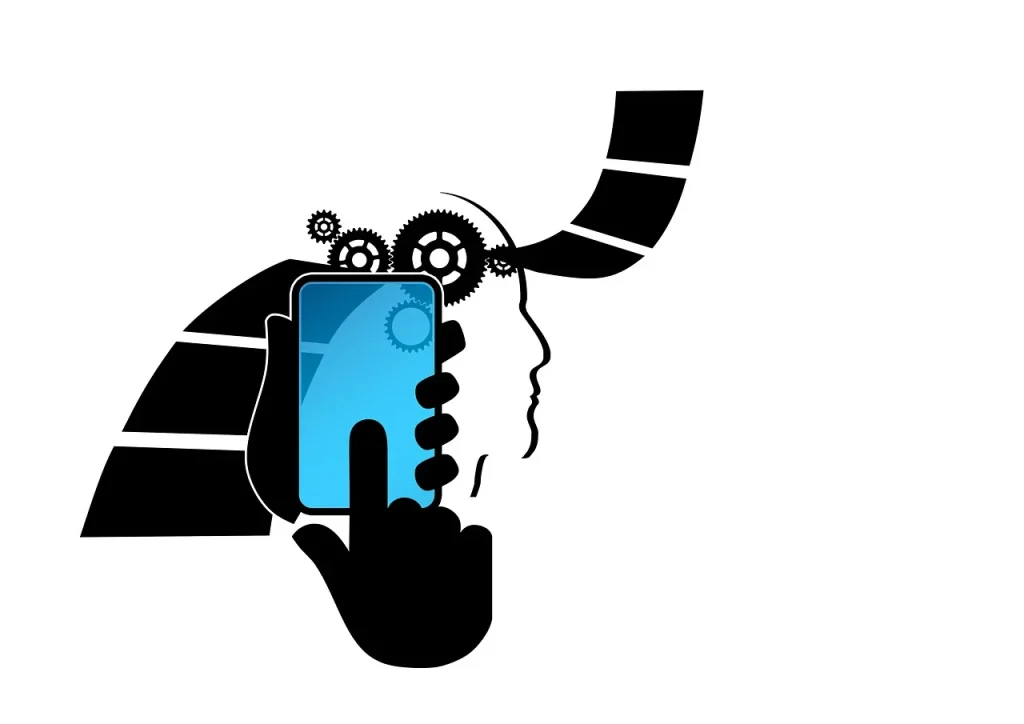
帰りぬるにやあらむ、いぎたなしと思されぬるにこそ、もの思はぬさまなれ、同じ心にまだ寝ざりける人かな、誰ならむ、と思ふ。
からうじて起きて、「人もなかりけり。そら耳をこそ聞きおはさうじて、夜のほどろに惑はかさるる。
騒がしの殿のおもとたちや。」とて、また寝ぬ。
女は寝で、やがて明かしつ。
いみじう霧きりたる空をながめつつ、明かくなりぬれば、この暁起きのほどのことどもを、ものに書きつくるほどにぞ、例の御文ある。
ただかくぞ。
秋の夜の有明の月の入るまでにやすらひかねて帰りにしかな
いでやげに、いかに口惜しきものに思しつらむ、と思ふよりも、なほ折ふしは過ぐし給はずかし、
げにあはれなりつる空の気色を見給ひける、と思ふに、
をかしうて、この手習ひのやうに書きゐたるを、
やがて引き結びて奉る。
現代語訳
九月二十日過ぎ頃の有明の月が残る夜明けの頃、宮はお目覚めになりました。
ひどく久しぶりになってしまったことだ、ああ、今頃はこの月を女も見ているだろうよ、誰かほかの訪問者が来ていたりするのだろうか。
宮はそうお思いになりながら、いつものように小舎人童(こどねりわらわ)だけをお供として女のところへおいでになられました。
童に門をたたかせなさると、女は、目を覚ましていて、さまざまのことを思い続けながら横になっていました。
この頃は、秋の終わりだからでしょうか、なんとなく心細く、いつもよりしみじみと思われて、物思いに沈んでいたのでありました。
今頃誰だろう、おかしいと思って、女は寝ている侍女を起こして尋ねさせようとするけれど、すぐには目を覚まさない。
やっとのことで起こしても、あちこちの物にぶつかり慌て騒ぐうちに、門をたたくのがやんでしまいました。
訪れてきた人はもう帰ってしまったのだろうか、もしかたしら私のことを寝坊だとお思いになってしまったのに違いない。
いかにも物思いのない女のようだけれども、私と同じ思いでまだ寝なかった人がいたのだなあ。
誰なのだろう、と女は思いました。
男の使用人がやっと起きて、「誰もいないことよ。幻聴をお聞きになって、夜中に混乱させなさる。人騒がせな屋敷の女房方だなあ。」と言って再び寝てしまったのです。
女は眠らずに、そのまま夜を明かしました。
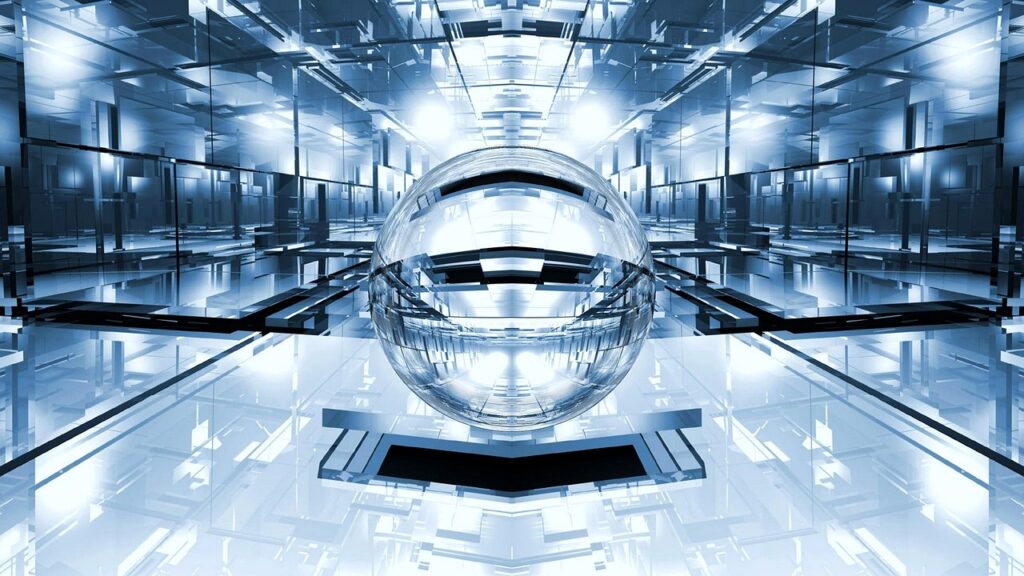
ひどく霧が立ち込めている空をぼんやりと眺めていると、明るくなってきたので、この夜明け前に起きた時のことなどを、紙に書き付けているところに、いつものようにお手紙がありました。
そこには、ただこのように書いてあったのです。
秋の夜の有明の月が沈んで朝になるまで、じっと外にたたずんでいることもできなくて、帰ってしまいましたよ。
女は宮様が私をどんなにつまらない女にお思いになったであろう、と思うと同時に、宮様はやはりその時々の情趣はお見逃しにならなかったのだよ。
本当にしみじみと風情のある空の情景をご覧になったのだなあ、と思いました。
うれしくて、先ほどの手習いのように思いつくまま書いておいたのを、そのまますぐ結び文にして宮に差し上げなさいました。
返歌の数々
その後、しばらく物思いに沈んでいると、すぐに宮から返歌がやってきました。
それも5首です。
あっという間に宮からの返事がきたので、きっと驚いたにちがいありません。
それがこれです。
秋のうちは朽ちけるものを人もさはわが袖とのみ思ひけるかな
消えぬべき露のいのちと思はずは久しき菊にかかりやはせぬ
まどろまで雲居の雁の音を聞くは心づからのわざにぞありける
われならぬ人も有明の空をのみおなじこころにながめけるかな
よそにても君ばかりこそ月見めと思ひて行きし今朝ぞくやしき
現代語訳は次の通りです。
袖が涙で朽ちたのは自分だけのことと思っておられるようですが、私の袖も涙でいっぱいなのです。
自分のことをはかない露とお思いですが、何故不老長寿の菊にあやかろうとしないのですか。

まどろみもしないで、雁の鳴き声を聞いているのは、他の男性との関係があるからではないでしょうか。
私だけではなく、誰かも有明の月を眺めているのですね。あなたもでしたか。
あなただけは月を見ていると思い、お訪ねしましたが門を開けてもらえなかったのは本当に残念なことでした。
この歌を手にしたときの彼女の気持ちはどんなものだったのでしょうか。
それを想像するのは楽しいですね。
女性としては、もっと心にしみるような歌を期待していたのかもしれません。
今風にいえば、歌は挨拶のひとつです。
気軽に自分の気持ちを伝えるチャットのようなものだと考えれば、いいのではないでしょうか。
そういう視点で読むと、かなり気軽にその意味がみえてくるものと思われます。
日記の文章と物語とのコラボと見立てれば、当時の読者はさぞやこころを揺らしたことでしょうね。
この作品が今にいたるまで、人気がある理由もよくわかるというものです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


