捨てない女
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はちょっと風変わりな小説を読みます。
作者は多和田葉子です。
1993年『犬婿入り』で芥川賞を受賞しました。
小説というのは、極端な話、何を書いてもいいのです。
そんなに大袈裟なストーリーでなくてもかまいません。
「小なる説」ですからね。
どんな嘘でも、そこにそれらしいことが起こりうる可能性がある限り、あらゆることが許されるのです。
「嘘」といってしまうと、ちょっと危険です。
問題は「リアリティ」です。
それが作品中に存在しているか否かが全てでしょう。
許されるのならば、地上の話でなくてもかまいません。
地下のトンネルの中でも、あるいは地球以外の天体でも、水中でもすべて可能なのです。
とはいえ、想像可能な世界であっては欲しいですけどね。
この『捨てない女』というのはそういう意味で、十分想定可能な範疇に入る作品です。
多和田葉子という小説家は不思議な人です。
日本語とドイツ語を駆使して、それぞれの言語環境を軽やかに行き来しています。
ある意味、実に羨ましい在り方です。
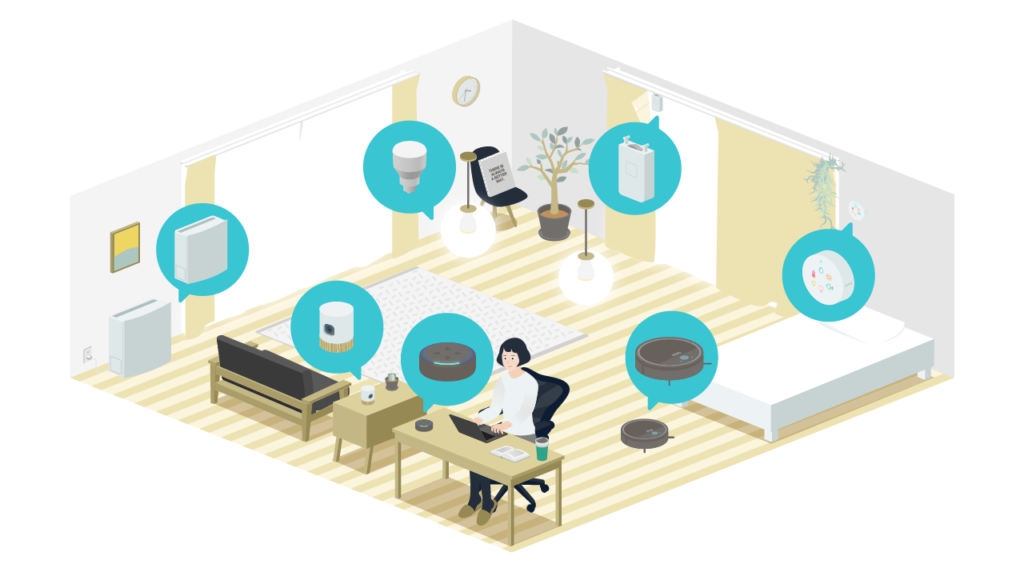
その意味からすれば、ややシュールなこの小説の内容も、十分に面白く飛んでいるといえます。
冒頭の部分を読んでいると、エッセイともフィクションともつかない、ごく日常的な書き出しであることに気づきます。
「生活廃棄物処理法」などというものがあったかとふと、考え込んでしまいました。
あるいは彼女が暮らしているドイツの話なのかな、と首をひねったのです。
ところが、次第に非現実的な要素とからんで、その世界に引きずられていきます。
この作品は2000年に刊行された短編集『光とゼラチンのライプチッヒ』に入っているものです。
その中で『捨てない女』には、彼女のエッセンスが凝縮されて入り込んでいます。
ごく短いので、すぐに読めます。
文章全体を掲載すると長いので、一部だけ取り上げましょう。
本文
生活廃棄物処理法が改正されてから、わたしの生活も随分変わった。
それまでは、書き損じた原稿用紙は束にして毎週月曜日に「もえるゴミ」として、近所のゴミ捨て場にもっていけばよかった。(中略)
ここ十年、ゴミが増え過ぎて、税金だけでは処理費が賄えなくなってきたため、粗大ゴミだけ
でなく、どんなに小さなゴミでも百グラム百円の処理費を払って引き取ってもらうことになっ
てからは、もう気軽に小説の筋を変えることもできなくなってしまった。
私は「処理」という言葉が好きになれない。
排泄物を処理し、性欲を処理し、人づきあいを処理し、中古品を処理しながら前へ進んでいく毎日では味気ない。
どうせなら、燃えるゴミとなって生命力を燃焼させ、火の玉となって死後も空中に漂い続けたい。
(中略)
先月からこんなことばかりしていて原稿料も入らずゴミの処理費が払えないので、これは法律違反だけれども、昨日、先週の書き損じを裏庭でこっそり燃やしてしまった。
ゴミはなくなったが、後味が悪かった。
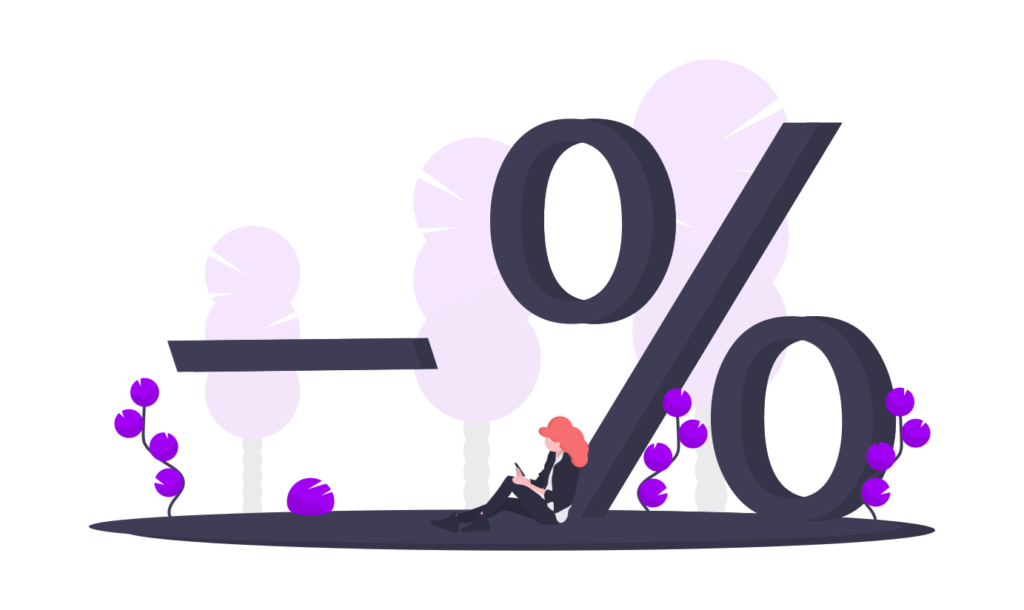
焼かれた紙はあの世に行くという話を沖縄で聞いたことがある。
だから、死者があの世でお金に困らないようにと、紙幣を燃やして届けるらしい。
すると死者たちは、わたしの書き損じた原稿を読んでいることになる。
死者にはそんな失敗作は読んでもらいたくない。
後から完成した本を一冊燃やして届けようか。
今朝、草木染めをやっている友人が電話で面白いことを教えてくれた。
書き損じた原稿用紙を塩と酢を入れた湯の中で15分ほど煮ていると文字が湯の中に溶け出して、原稿用紙はまた白くなる。
それを壁に貼り付けて乾かせば、また使えると言う。
確かに多少波うっているはいるが、字が書けないことはないし、波うっているからと言って原稿を受けつけない編集者もいないだろう。
もちろん万年筆に入れるインクは無農薬栽培の桑の実から作ったものやイカ墨などがよいが、普通のインクで書いたものでも消えないことはない。
ゴミ百グラム百円
設定が実に面白いですね。
いかにもありそうな話です。
登場人物は「生活廃棄物処理法」が改正されて、ゴミ百グラムにつき百円の処理費を払わねばいけなくなった作家です。
「わたし」はパソコンなどと縁がなく、ひたすら原稿用紙に向かって小説を書きます。
その結果、書き損じの原稿用紙やメモ類などたくさんのゴミが出るワケです。
ここで主人公の持つ言葉に対する基本的な態度が表現されています。
「処理」という表現が好きになれないとあります。
この言語感覚は多和田葉子の持つ、倫理観に根差したものかもしれません。
ここの部分の文章はかなり生な印象ですね。

なにもかもを処理し前へ進んでいく毎日が、味気ないと言っています。
むしろそれくらいなら、燃えるゴミとなって生命力を燃焼させ、火の玉となって死後も空中に漂い続けたいとあります。
この文章には彼女の根本にある考え方が宿っているような気もします。
「感性は思考なしにはありえないのに、考えないことが感じることだと思っている人がたくさんいる。」
これは彼女のエッセイの中にあった言葉です。
多和田葉子は考えることなしに感じることはないと言っています。
この例でいえば、「処理」という表現の中にある非人間的で効率優先の響きが、生理的に許せないのでしょう。
卑近な例でいえば、「処分」も似ていますね。
原稿用紙の増え方
その後にでてくる原稿用紙の増え方が実にユニークです。
1つの小説を書くために、30枚くらいの原稿用紙をまず使う。
着想のメモと図書館で調べた結果を書き散らすのです。
その後、ウォーミングアップにまた30枚書く。
さらに予防作品をまた30枚。
これは本番と同じ筋で、登場人物も同じではあるものの、説教、恨み、愚痴、文句などを書き込んだバージョンのものだそうです。
簡単にいえば、「毒」を吐いた結果ですね。
それらがすべて抜けてやっと本編に取りかかるのです。
しかしそれも1回目、2回目でうまくできるということではありません。
絶好調のコンデイションをキープし続けることはできず、その結果としてゴミの山が築かれていくことになるワケです。
そんなところへ隣の住人が和菓子の包み紙に入った四角い缶を持ってきたのです。
その中にあったのは、和紙をまねたビニールの小袋に入っているおせんべいでした。
とうとう、その包装紙に小説を書いたらどうかという、妄想までいだく羽目になります。
このあたりの表現は、かなりシュールでもあり、コメディタッチで軽く描かれています。
終盤には友人から教えられて、塩と酢を入れた湯の中で書き損じの原稿用紙を煮る場面が出てきます。

ここが1番、面白いです。
本当にそんなことがあるのだろうかとつい信じてしまいそうになります。
書き損じた原稿用紙を塩と酢を入れた湯の中に15分ほどつけて煮れば、文字が湯の中に溶け出すという話です。
やがて、文字が湯の中に溶け出して、原稿用紙はまた白くなるのです。
それを壁に貼り付けて乾かせば、また使えるとか。
ナンセンスで話ではありますが、いかにもそんなことが起こりそうなシチュエーションですね。
ひとつの想像が、次の現実を惹起していくという、言葉の推進力を感じます。
これが作家の世界なのかもしれません。
不条理といってしまえば、それまでのことですが、フィクションはこうして、本当の肉体性を帯びていくのではないのでしょうか。
推進力の勝利といってもいいかもしれません。
文字は一瞬ゆがんだかと思うと、ぶるぶるっとふるえて、ひらがなとカタカナが紙面を離れて浮かび上がってきたのです。
これを裏庭に捨て、春に種をまいたらどんな花が咲くのでしょうか。
本当に妙な小説です。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


