静縁のこけ歌
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は鴨長明の『無名抄』から和歌の批評についての部分を取り上げます。
高校の授業で習った人もいるに違いありません。
『無名抄』(むみょうしょう)は、鴨長明による鎌倉時代の歌論書です。
正確な成立年はわかっていません。
おそらく1211年から1216年までの間に成立したと考えられています。
歌論書は当時、多くの人が書きました。
長明のものは歌の技術についての内容だけではありません。
逸話なども載っていて、随筆風の味わいもあります。
とりわけ、歌というものに対する考えを正直に著しています。

彼の性格なども、文章の端々から判断することができるワケです。
今回の章は静縁法師の歌を題材にして、どこがダメなのかを論じている部分です。
タイトルの「こけ歌」というのは形容動詞の「こけなり」(虚仮なり)から来ています。
簡単にいえばあさはかで意味が浅いといったような意味です。
つまりあまり評価できないヘタな歌という意味です。
静縁法師というのは比叡山の高僧だったそうです。
しかし生没年がよくわかっていません。
この話のポイントはこの和歌の評価を、静縁自身がどのように考えていたのかというところにあります。
その変化を読み取ってください。
①長明のもとに最初に来た時
②俊恵のもとに行った時
③長明のもとに再び来た時
この3つの変化を明確に理解できればいいのではないでしょうか。
本文
静縁法師、自らが歌を語りていはく、
「鹿の音を聞くに我さへ泣かれぬる谷の庵は住み憂かりけり」とこそつかうまつりて侍れ。
これいかが侍る」といふ。
予、言はく、「よろしく侍り。ただし、『泣かれぬる』といふ詞こそ、あまりこけ過ぎて、
いかにぞや聞え侍れ」といふを、静縁、いはく、「その詞をこそ、
この歌の詮とは思う給ふるに、この難はことの外におぼえ侍り」とて、いみじうわろく難ずと思ひげにて去りぬ。
よしなく、おぼゆるままにものをいひて、心すべかりけることを、と悔しく思ふほどに、十日ばかりありて、また来たりていふやう、
「一日(ひとひ)の歌、難じ給ひしを、隠れ事なし、心得ず思う給へて、
いぶかしくおぼえ侍りしままに、さはいへども、大夫公の許に行きてこそ、
我が僻事を思ふか、人のあしく難じ給ふか、ことをば切らめ、と思ひて、行きて語り侍りしかど、『なんでふ御房のかかるこけ歌詠まんぞとよ。

「泣かれぬる」とは何事ぞ。
まさなの心根や』となん、はしためられて侍りし。
されば、よく難じ給ひけり。
我あしく心得たりけるぞと、おこたり申しにまうでたるなり」といひて帰り侍りにき。
心の清さこそ有り難く侍れ。
現代語訳
静縁法師が、自身の歌を(私に)語って、
「(牝鹿を恋い慕う)牡鹿の鳴き声を聞くと、私までも(寂しくなり)泣かずにはいられません。
谷の庵は本当に寂しくて住むのがつらいのです。と詠んでみました。
この歌はいかがでしょうか」と言います。
私が、「まあまあです。ただし、『泣かずにはいられない』という言葉は、あまりも浅薄過ぎて、あまり評価ができません」と言うと、
静縁法師は、「ほかならぬその言葉こそ、この歌の眼目だと思っております。
この批判は残念に感じられます」と、私がひどくとんでもない非難をしていると思っている様子で去っていきました。
「不満に感じた気持ちにまかせて意見を言って悪いことをしたな、
もう少し柔らかく注意すべきだった」と、その後しばらく後悔しておりました。
すると10日ほどして、再び法師がやってきたのです。
「先日の歌を、あなたは批判なさいましたが、それをいまさら隠し事をしても
しかたない納得いかないと思いまして、気が晴れないでいました。
『どういっても、俊恵殿の許にいって、私がろくでもないことを考えているのか、
長明さまが見当はずれに非難していらっしゃるか、決着を付けよう』と思って、行って話してきました。
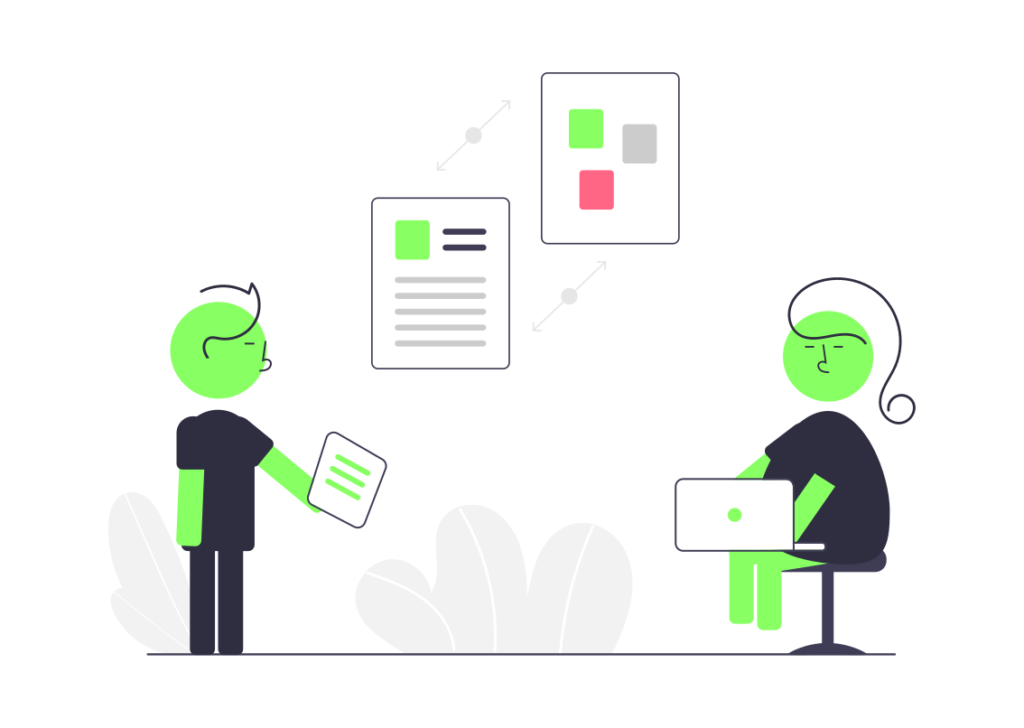
その結果、『どうしてあなたがこんな浅薄な歌を詠もうとするのでしょうか。
「泣かずにはいられない」という表現はどういうつもりですか。
(こんなひどい歌を詠むなんて)とんでもない心の持ちようです』と言われ、恥ずかしい思いをさせられてしまいました。
そういうわけで、あなたの批判は全く当を得たものだと感じたのです。
私の方が間違って理解して逆恨みをしていたのだと、おわびを申し上げに参上したのです」といって帰ったのでした。
静縁法師の心のすがすがしさは、今どき、珍しいぐらいのものでした。
3つのポイント
静縁の態度が微妙に変化していった様子が読み取れたでしょうか。
最初に、長明のもとにやってきた時には自信満々でした。
ところがあまりよくないと言われ、ショックを受けます。
そこで源俊恵のところへ持っていきました。
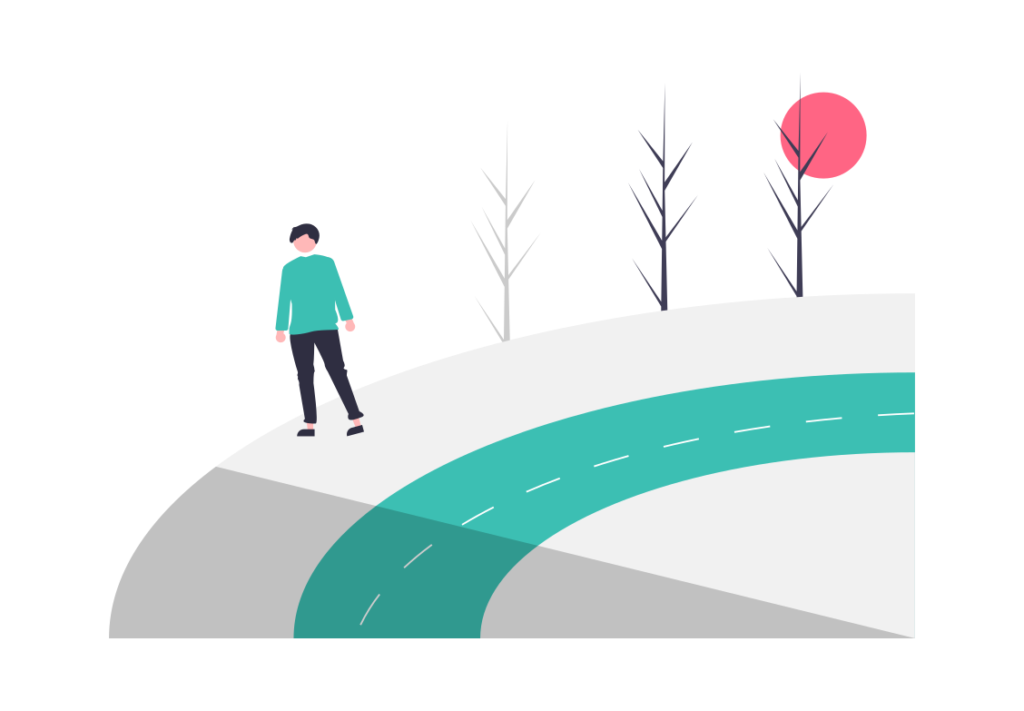
俊恵は鴨長明の師にあたります。
『無名抄』などにも歌に対する厳しい態度が載っています。
余情を重んじる姿が、中世の静かさを尊重する気分によくあっていたのでしょう。
俗に幽玄と呼ばれる境地を生み出したと歌人と言われています。
そこで表現の細部のまずさを指摘されたのです。
大きな失点は「泣かれぬる」という言葉でした。
素直に謝る心
最後に静縁法師は再び、長明のもとを訪れます。
その時長明に向かって、謝ります。
あまりにも無駄な言葉が多かったことを再認識したというのです。
その態度があまりにも潔かったので、長明も感じいったのでしょう。
わざわざその時の様子を書き取りました。
ではなぜ、「泣かれぬる」と詠んだことが「こけ歌」、つまり、考えが足りない浅薄な歌にあたるのでしょうか。
それは、「さへ」という言葉の使い方にあります。
「さへ」は文法的に言うと、添加の副助詞と呼ばれます。
この表現を使うと「泣かれぬる」と言葉と重なってしまうのです。
つまりくどいのです。
「泣かれぬる」は自然と泣けてしまったという意味です。
文法的に解説をすると、「れ」は「自発」の助動詞「る」です。
自ずとなにもしないのに自然と涙が出てきたという意味です。
そのため、「我さへ」という言葉、つまり「私までも」という表現と、涙が自然に溢れ出てくるという内容が重なってしまうのです。
「我さへ」があれば言外に「泣かれぬる」の表現がそこにあるのです。
さらにいえば「泣かれぬる」は心情をことばで「説明」しています。
悲しいという言葉は不必要なのです。
もちろん、泣きましたも不要です。

鹿の声がするというだけで、そこまでの情感を表現せずにあらわさなくてはいけません。
それが中世の「幽玄」の世界そのものでした。
殊に歌の世界では、言い過ぎてはいけません。
余情を大切にするのが基本です。
この段落の後に歌に対する美意識の文言もあります。
一言で言えば、ことばで心情を表現しすぎてはいけないということです。
いみじくいひもてゆきて、歌の詮とすべき節を、さはといひあらはしたれば、無下(むげ)にこと浅くなりぬる。
この文章の意味は具体的な景色をさらりと詠み表わして、
ただ余情として身にしみただろうなと読者に感じさせるほうが、奥ゆかしくも優美でもありますということです。
たった1つの表現に命をかけていた歌人たちの姿が髣髴としてきますね。
今回も最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。


