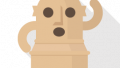伊豆の踊子
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はノーベル文学賞受賞者、川端康成の話をさせてください。
高校では『伊豆の踊子』を何度も扱いました。
他の作品を手がけた記憶はありません。
理由は簡単です。
あまりにも難解だからです。
高校生には理解できないと編集委員が考えたのでしょう。
ぼくに言わせれば、病的なのです。

あまりに繊細で、その感覚についてこられる生徒が少なくなってしまったものと思われます。
彼の作品の中でも『伊豆の踊子』には救いがあります。
この短編は一人旅の学生と旅芸人一座の若い踊り子とのほのかな恋と別れを描いたものにすぎません。
文庫本でわずか30ページほどです。
孤児根性に曲がったと自己分析する旧制の高校生を救ったのは、明るい伊豆の海と踊り子一行の屈託のなさでした。
先を歩く踊り子の声が彼の耳に届きます。
仲間の一人に「いい人はいいね」と呟くのです。
自分がいい人などといわれた記憶もない彼は、そこですっと救われるのです。
それが全く気負わずに出たまっすぐな言葉だっただけに、なおいっそう嬉しかったのでしょう。
この場面が最大のクライマックスです。
川端康成に1度もチャレンジしたことのない人は、これだけは読んで欲しいですね。
今の小説のように突然事件が起こるというようなストーリーの展開は何もありません。
ただ伊豆の道を歩く旧制の高校生と踊り子一行の物語です。
しかしそこにはじんわりとした温かさが流れています。
ひたすら人間を信じたかった川端康成の祈りを感じるのです。
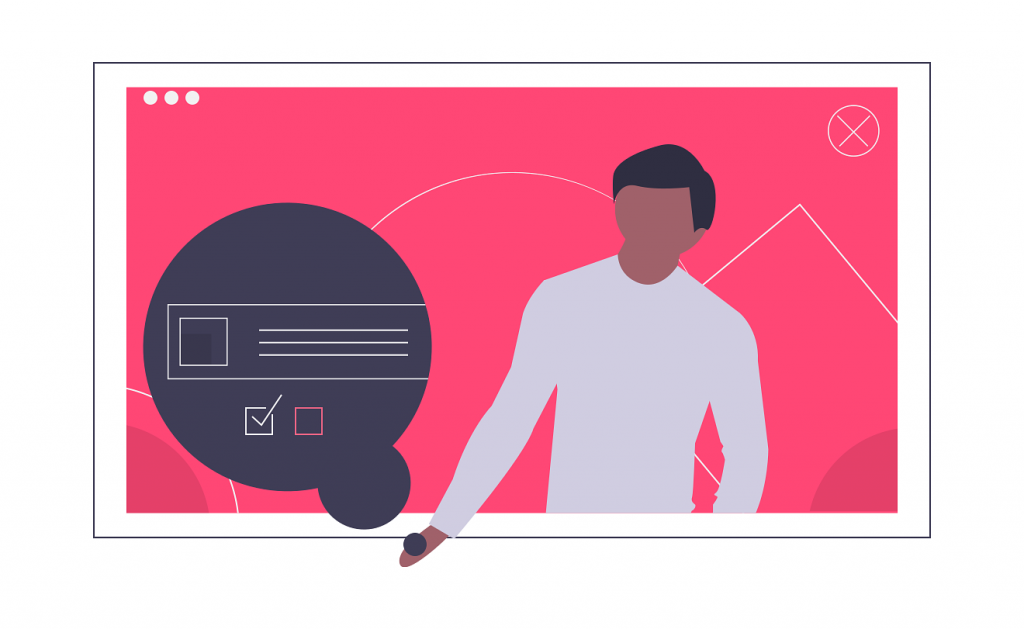
心を打ちます。
名作だと思います。
孤児の感覚
川端康成は1899年、大阪市に生まれました。
父母が早くに亡くなり、祖父母に引き取られました。
肉親の愛情に恵まれず、その感覚を生涯ひきずって生きたのです。
新感覚派の代表作家として活躍。
1968年、日本人として初めてノーベル文学賞に輝きました。
授賞理由は「日本人の心の精髄を、すぐれた感受性をもって表現するその叙述の巧みさ」ということでした。
そのインタビューで何度も弟子にあたる三島由紀夫の名前を挙げています。
三島ほど川端康成を慕った作家はいませんでした。
病的な感性がどこかで繋がっていたのでしょう。
死に対する感受性といったらいいのかもしれません。
その後、三島由紀夫は割腹自殺を遂げます。
川端にとっても余程の衝撃だったに違いありません。
1972年、72歳の川端康成は鎌倉の海に近いマンションの一室で、ガス管をくわえ自殺しました。
遺書はありませんでした。

ノーベル文学賞を受賞した文豪が、ガス管をくわえて自死するという衝撃的な事件は日本中を騒然とさせました。
三島由紀夫が割腹自殺した2年後の出来事だったのです。
雪国再読・心の襞
どうしても『雪国』が読みたくなって続けて2度読みました。
こういう経験はあまりありません。
かなり昔の記憶しかなく、温泉旅館での駒子と島村の関係だけを覚えていたにすぎないのです。
今度読み直してみて、いろいろな意味で非常に新鮮でした。
細かい描写は川端の独壇場かもしれません。
特に音や色に対する感覚が実に鋭いのです。
ちょっとした物音や、色彩で登場人物の感情をあらわすのがみごとですね。
なるほど、新感覚派と名付けられた理由はここにあるのだと感じました。
彼は女性の心の襞を描くのが巧みです。

島村という男はいわば影であると川端自身が述べているように、駒子という女性の心を写し取るためのスクリーンそのものです。
誰かがそこにいることで、彼女の心の内側が透けて見えるのです。
奥深い山に降る雪もここでは一つの装置なのでしょう。
何度も出てくる「徒労」という表現は川端の命の言葉だったのかもしれません。
生きることが全て徒労に見えるところから彼の人生は始まったのでしょうか。
幼い頃に肉親の全てを失ってしまった作家にとって、死は実に親しいものであったと思われます。
ここにも結核で亡くなっていく、かつての師匠の息子が登場します。
その人となかば許嫁の関係にあると周囲から見られていたというだけで、駒子という女性の輪郭が仄見えてくるのです。
酒に酔って島村の部屋を訪れる駒子のいじらしさをこれでもかという風に川端は表現します。
男に惚れる、情がうつるということの意味を、彼は心の底から知っていたに違いありません。
そうでなければ、淡い描写の中に苦しみ抜く人の感情は表現できないのです。
これは年をとってから読む小説ですね。
若い時に読んでも何が書いてあるか理解できないでしょう。
描写は実にそっけないのです。
しかし雪国に生きる人間を正面から見つめています。

最初から登場する葉子がもう一つの要です。
島村の関心が駒子から葉子にうつっていく予感を駒子がどう受け止めたのかということも淡く、しかしくっきりと描かれています。
終わりがはっきりしないのが私の小説だと川端はよく言っていたといいます。
まさに始めもなく、終わりもない。
それこそが人生なのかもしれません。
山の音・人の世のいとなみ
これも川端康成の名作です。
深夜ふと山の音を死の予告のようにして主人公は聞きます。
小説はまさにどうでもいい些事を積み木細工のように重ねてつくるものなのでしょう。
ほんのわずかな気配を言葉に乗せて、人の世のいとなみを映すのです。
菊子という息子の妻に、老年にさしかかる主人公が仄かな愛情を持ちます。
戦争未亡人にうつつを抜かして自分の妻を振り向こうとしない息子を見ると、菊子が不憫に感じられてならないのです。
義父としての立場もあります。

節度も当然そこにはあるのです。
しかし菊子がいることで、老年が輝いても見えます。
そこへ実の娘が婚家から子供を連れて戻ってきます。
夫は出奔したまま、行方不明らしいのです。
後に麻薬中毒になっていたことが明らかにされます。
あんな家に嫁がせて、と親をなじる娘。
菊子の立場は微妙です。
やがて菊子の妊娠。
しかし彼女はあえて自分から堕胎の手術を受けます。
このシーンは圧巻です。
戦争未亡人といつまでも傍を離れようとしない夫との間に、子は不必要と自ら断じたからでもあります。
それを知った義父の心の痛みも強く描かれます。
死を背後に背負って、最後の輝きを得た主人公は、菊子との時間の中にしか、生の実感を持てません。
山の音がひたひたと寄せる死への誘いにも似て、不気味な通奏低音を奏でています。
小説とはまさにどこにでもあることを、ただ感性だけを下敷きにして描いた、もう一つの人生ということになるのかもしれません。
川端康成の持つ病的な感情のふるえが伝わってくる作品です。
もうこうしたものを書く人はほとんど出てこないでしょう。
いても誰にも読まれないかもしれないのです。
そういう時代になっている気もどこかでするから不思議です。
最後までお読みいただきありがとうございました。