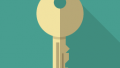なぜ書けないのか
みなさん、こんにちは。
小論文添削歴20年の元高校国語科教師、すい喬です。
今回はなぜ書けないのかという問題を深掘りします。
一番の敵は「苦手意識」です。
これはあくまでも自分がそう思っているということです。
本当はすごくいい文章が書けるのに、ヘタだと自分で決めつけている人も多いのです。
その最大の理由は義務感です。
試験だからしょうがない。
出題されるからしょうがないといった後ろ向きの気分でいる人が多いのです。
できるなら避けたかったというのが本音かもしれません。
小論文を出す出題者の側にまわって少し考えてみてください。
とにかく準備が大変なのです。

889520 / Pixabay
課題文型にせよ、テーマ型にせよ、候補となる問題を持ち寄ってあれこれと議論するワケです。
つまり出題者たちは、この試験で受験生の力を見抜きたいと思っているということです。
もっとわかりやすく言えば、次の2点を知りたいのです。
表現したいことを他者に十分伝えられる能力を持っているのか。
採点は想像以上に大変です。
正解がないのですから、採点者の能力も試されるのです。
すごく疲れます。
ポイントは受験生の思考力と表現力です。
この2つが十分にある生徒は大学に入った後も伸びます。
少人数のゼミなどでの発表も大いに期待できます。
つまり書きたいという主体性を持った生徒が欲しいのです。
それならばいっそ義務感から一歩抜け出ようではありませんか。
自己アピール
苦手意識をなくせということは、つまり試験を自己アピールの場にしようということです。
マイナスだと考えていたことをプラスの場にかえてしまうのです。

3D_Maennchen / Pixabay
通常自分の書いたものを人に読んでもらうということは、なかなか大変なことです。
しかし入試に関していえば、必ず採点者は読んでくれます。
ということは、何が言いたいのかが明確になっていれば、間違いなく伝わるということです。
何を伝えたいのかという気持ちが基本です。
そこがかたまっていれば、自分に素直に問いかけながら文章を綴ってください。
必ず筋道をたどっていくこと。
そうでなければただの作文になってしまいます。
論文は自分の考えを述べるものです。
思考の出発点は何でしょうか。
それは疑う力です。
課題文がある問題の場合、じっくりと読んでみましょう。
なにかヘンだな、しっくりこないなというところはありませんか。
そこが思考の始まりなのです。
課題文の内容を鵜呑みにしてはいけません。
本当にその主張は正しいのか。
説明はポイントをついているのか。
じっくり考えてください。
自分の中でどうもおかしいと感じることを大切にするのです。
それが突破口です。
出題者の意図がみえてきたらもう合格一直線です。
なぜこういう問題を出題したのか。
その意図は何か。
逆に探っていくのです。
広い関心
小論文は書いた人の主張が人間の生や、現代の社会とどのように関わっているのかが大切です。
そのために必ず自分の問題として捉える視点が必要なのです。
どんな問題が出ても、他人のこととして捉えたのでは、いい文章になりません。
課題文を読んだら、その中に自分のことが書いてないかを探ってください。

geralt / Pixabay
何か、関連したことはないかを見つけるのです。
一般論の紋切り型は絶対にダメ。
自分のテーマとリンクさせられないような人の文章は読んでいてもアピールしません。
たとえ小さなことでもいいのです。
その中に自分と関係のあることがらを探してください。
それが疑問であり、共感です。
なんかヘンだなと思うことはありませんでしたか。
その通りだと思う箇所はありませんでしたか。
そこがポイントです。
あなたにとってはそこが糸口なのです。
どうしても書けない時は自分の中を掘ってください。
そうすれば必ず鉱脈にぶちあたります。
しかしただ闇雲に書いただけではダメですよ。
何が言いたいのかわからないものは、主題が明らかでないということです。
必ず人間や社会に対しての分析的考察を加えながら書いてください。

geralt / Pixabay
理解力、応用力、思考力をフルに回転させていかなければいけません。
独りよがりはNG。
出題者が何を見たがっているのかを常に意識してください。
テーマ型の場合
今までの人生の中で一番深く感動したことはなんですか。
といったような問題が推薦入試などでテーマ型の典型例としてよく出題されることがあります。
そんな時も慌ててはダメです。
書けることはきっとたくさんあるでしょう。
しかしいくら具体例を書けばいいといっても、「自分に引きつける」「自分から出発する」という2つの基本を忘れてはいけません。
小論文には本当に難しい課題にあわせて論じさせる問題がある一方で、いかにも書きやすそうなこうした問題が出ることもあります。
実はかなり多くの大学や専門学校ではこのタイプの問題が出るのです。
受験生の特性が明確になる。
以上の点で好まれるタイプの問題なのです。
何に感動したのかというのは、その個人にとって大きな問題です。
いわば価値観の根本を相手にみせるという作業です。
これなら楽だと思って侮ってはいけません。
採点者はその文章の背後にあるあなたという人間の特性をみようとしているのです。
どんな人間なのかが一目でわかる恰好の問題なのです。
どうしたらいいのか。
繰り返します。
具体例を出すというのは、「私から出発する」「自分にひきつける」最良の方法です。
しかし危険なワナもそこにはたくさんあります。
独自性というのは奇抜さを意味するワケではありません。

geralt / Pixabay
書き手の中でよく確かめられ、考えられているという感覚を相手にきちんと与えられるか。
常識的な言い方や考え方で、相手を説得しようとしていないか。
この2点に注意してください。
体験したことは特別なことでなくていいのです。
ありふれたことに対して、あなたがどんなふうに対応したか。
何を感じたかが特別のものであり、かけがえのないものであればいいのです。
自分はなんにも特別なところへ行ったこともないし、したこともない。
それでいいのです。
むしろその方がいいのです。
その中にじっと考える自分がいたことをアピールしてください。
どう語れば相手に伝わるのか。
そこが最大のポイントです。
絶対に苦手意識を持ってはいけません。
試験の答案は必ず採点者が読んでくれます。
その人に向かって、自分を最大限にアピールする機会だと思ってください。
チャンスが来た。
いまこそ、自分の感覚のありかを知ってもらおうという前向きの気持ちで答案用紙に向かってください。
難しい言葉を使う必要はありません。
自分の言葉でこのように考えたというプロセスを綴ってください。
難しいことを易しく言い換えられる能力は誰にもあるものではありません。
それこそが国語力です。
感情におぼれず、冷静に結論まで導くこと。
これを約束してください。
あなたの合格の吉報をお待ちしています。
最後までお読みいただきありがとうございました。