結論を支えるもの
みなさん、こんにちは。
小論文添削20年の経験を持つ元都立高校国語科教師、すい喬です。
勉強はすすんでいますか。
いろんな科目があって、どれをやったらいいのか。
焦っている人も多いことでしょうね。
気持ちはとてもよくわかります。
勉強の成果はすぐには出ません。
らせん状にあがっていくのです。
後になってみると、どうしてこんなことがわからなかったのだろうと思ったりするものです。
少しずつしか成績は伸びませんよ。
慌ててはいけません。
以前わからなかったことが、少しでも理解できるようになっていれば、それは前に進んだということになるのです。
続けてください。
必ず結果がついてきます。
今日は小論文の書き方をもう少しだけ突っ込んでお教えしましょう。
小論文の構成要素は簡単に言うと、結論、理由、事実です。

その中で一番大切なものは何か。
それは結論を支えるものとしての事実です。
理由です。
この論理構造をまずきちんと把握してください。
どんな結論であっても、それを支える論理に筋道が通っていれば、それは論文になり得ます。
逆にいえば、そこに独自性を出そうとすれば、他の人と違う結論になることも十分に考えられます。
強い言葉
けっして弁解してはいけません。
よく謙虚さを示そうとして、私にはよくわからないが…などという断りを書く人がいます。
これは日本の文化の特徴です。
日本人のする挨拶の最初の文句はまずこれです。
「お口にあうかよくわかりませんけど、つまらないものですが…」といっておみやげを渡すシーンを見かけたことはありませんか。
こういうのが一番小論文では嫌われるのです。
弁解じみた文章をいっさい書く必要はありません。
強くぐいぐいと自分の意見を書き込んでください。
特に理由説明の部分こそが、小論文のポイントです。

ここで点数を稼ぐのです。
絶対にこれくらいのことはわかるだろうと推測し、内容を省略してはいけません。
欠落した部分を相手が補いながら読むというパターンは最悪です。
どんどん評価が下がります。
暗示ではダメだということです。
誰が読んでもなるほど、その通りだと納得できるものでなくてはなりません。
論理に脱落のある文章はNGです。
論点をきちんと追いかけていくと、必ずこの結論以外にはないと思わせる文章でないと、高い評価は得られないのです。
だから難しい。
日本人はそういう訓練を日常的に行っていないのです。
だいたい日本語の構造があまり論理的にできていません。
どうしたらいいのか。
ここが一番小論文の難しいところです。
これだけはダメという例をあげます。
あなたはこんなことしていませんか。
自分勝手な論理の文章に過ぎないもの。
具体例や自分の経験ばかりを羅列したもの。
事前に準備した通りの文章に無理に内容をあてはめたもの。
この4つのパターンは最悪です。
残念ですが、ほとんど評価の対象になりません。
どの内容が出ても、「それは事実に違いないが」などと言って自分の用意した文章をそこに差し挟んでいくといったものを見受けることがたまにあります。
それはあくまでもパターンを使えということで、内容まで流用しろというものではありません。
たとえば、環境問題や少子高齢化、グローバル化などといったテーマに移行させて、いい気持ちで文を書き終わるパターンです。
これは絶対にやめること。
ムダなあがきにしか見えません。
必ず課題文の内容に沿ったキーワードを読み込んで文章を書く練習をしましょう。
新聞の文体
書き方は新聞の文体を真似してください。
私の家では新聞をとっていないからというのは理由になりません。
どこでも読めます。
学校の図書館でもいいでしょう。
最近はヤフーニュースなどを見るチャンスも多いことと思います。
掲載されている記事の半数は新聞からのものです。
だから読んだことがないというなどということはあり得ません。

ReadyElements / Pixabay
みんなよく読んでいるのです。
どこの新聞かということを気にする必要はありません。
紙媒体でないということは理由にならないのです。
どんな文体かわかりますか。
である調の文章です。
読みやすい短文が積み重ねられています。
あの文体が目標です。
逆にいえば、新聞の文体から離れていたら、評価は低くなります。
特に口語の日常的な表現を使うと即アウト。
くどい冗漫な書き方はダメです。
例
火をみるより明らか → 明白である。
重大な問題 → 課題になる
経験の少ない者 → 初心者
言葉を重ねてはいけません。
形容詞を多用することは避けましょう。
期待するほどの効果は出ません。
目標は新聞記事です。
必要なことは全て短い言葉の中に入れ込むという練習をしてください。
課題文を読んで、わざと自分の意見と反対の結論を出す練習をするのも、実力をつけるにはいい方法です。
実際にやってみると、すごく難しいです。
しかし予想に反して、ものすごく力がつきますよ。
投書欄の活用
論理的な理由をきちんと書けと言いました。
しかし何も考えたことのないテーマを読まされて、さあ書けと言われても…。
意味のある事実を探し出すことはすごく難しいのです。
だから新聞を読めと書きました。
しかし新聞も難しいのは事実です。
たくさんある記事の中で一番小論文の役にたつところはどこか。
それはズバリ、投書欄です。
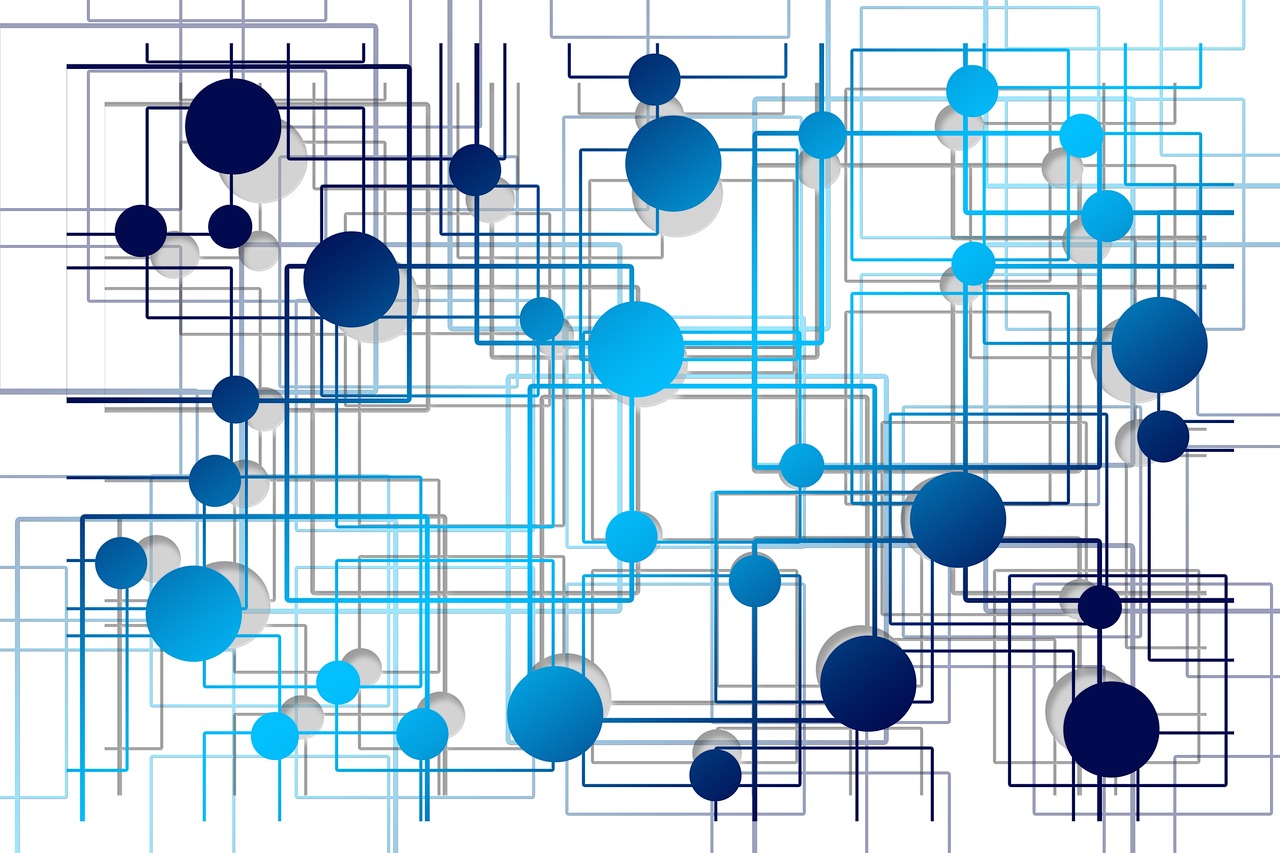
geralt / Pixabay
ここが一番読みやすいです。
そして時事的なトピックスにあふれています。
新聞社は記事にできない内容を投書で補おうとします。
記事にしてしまうと、やや偏りが出そうな意見も投書なら載せられるのです。
ここを重点的に読んでください。
何が今世間で一番語られている内容なのか、よくわかります。
キーワードの宝庫です。
ネタを探すという気分で、読んでみてください。
必ず役に立ちます。
もう1つは新書です。
新書ってなあにと言っている人はちょっとここで立ち止まってください。
文庫本は知ってますね。
あの縦の部分の長さを少し伸ばした大きさの本です。
小説はありません。

mohamed_hassan / Pixabay
経済、歴史、社会学、哲学、文化人類学、高齢化問題、生きがい…。
テーマは様々です。
本屋さんへ行くと、新書のコーナーにズラリと並んでいます。
ここのタイトルだけでも眺めること。
まさにキーワードのオンパレードです。
中・高校生向けの新書には岩波ジュニア新書、ちくまプリマー新書などがあります。
ぼくが高校生になった時、先生は岩波新書を100冊読めば、本当の高校生になれるとよく教壇で話していました。
今の高校生で100冊新書を読んでいる生徒はまずいないと思います。
難しくてとても読めません。
自分の興味ある内容のものでいいです。
図書館で借りてください。
スキマ時間を使って読みましょう。
科学的根拠、偉人の言葉、専門家の見解、データ、調査結果などあらゆる資料が新書にはあります。
どうでしょうか。
まず3冊。
面白かったら5冊。
自分のデータベースを着々と増やしてくざい。
そうすることで、小論文の論述に説得力が増していくはずです。
論理的な構成力がつきます。
信じてやってみてください。
合格の2文字を手にする日を信じて、頑張ってくださいね。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。


