 ノート
ノート 国際語としての英語の役割はグローバル社会の中でどう変質してきたのか
今日、英語は完全な国際語の地位を保っています。しかしその内実はそれぞれの宗教や文化の中で変質を余儀なくされています。柔軟性を持つことばとはどのようなものなのかについて、考えてみましょう。
 ノート
ノート  ノート
ノート  小論文
小論文  本
本  小論文
小論文  小論文
小論文  小論文
小論文  小論文
小論文  本
本  本
本  本
本  ノート
ノート  本
本  本
本  本
本 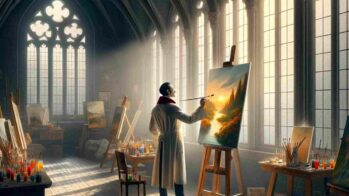 小論文
小論文