中宮定子のサロン
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
『枕草子』は高校で隋分勉強しますね。
中学校でも「春はあけぼの」などの段は暗唱するようです。
文章がきれいだし、彼女の鋭い感性が随所に滲み出ています。
言葉の選び方のセンスが抜群です。
彼女は漢文の知識もあったので、内容に広がりがあります。
さらにいえば、一条天皇の中宮定子に対する愛情の深さが実によく出ています。
道長の娘、中宮彰子に比べて、次第に没落していく家系にあったということも趣きの1つです。
日が昇るように一族が繁栄していくのに比べると、道長の兄、中関白家・藤原道隆の系譜には陰りがあります。

それをなんとか自分の力で盛り立てようとした清少納言の心意気が心地よいのです。
定子が宮中でどのように振る舞っているのかなどを見るにつけ、その志の高さや教養に惹かれていったものと思われます。
『枕草子』は西暦1001年頃にはほぼ完成していたと言われています。
学校では「ものづくし」の段を学ぶことが多いです。
代表的なのは「虫は」「木の花は」「すさまじきもの」「うつくしきもの」などでしょうか。
彼女の目の確かさがこれでもかというくらい綴られています。
女性ならではの細やかな観察眼にも舌をまきますね。
ものづくしが終わると、次に習うのが日記の章段です。
中宮定子周辺の宮廷社会を振り返った部分です。
西暦1000年、定子は23歳で亡くなります。
出産時のことでした。
その後すぐに清少納言は宮仕えを辞めました。
およそ6年間くらい定子のそばにいたことになります。
中宮のサロンはそれはみごとなものだったようです。
その中で一際異彩を放っていたのが女房の清少納言です。

身の回りの世話をする以上に話し相手、家庭教師などの役割も果たしていました。
サロンを訪れる多くの貴族たちと対等に渡り合えるだけの教養を持っていたのです。
清少納言の父親は「梨壷の五人」として名高い清原元輔です。
「梨壷」とは天皇の命によりおかれた和歌所のことで、元輔はその中で『後撰和歌集』の編纂等をおこなっていました。
天皇直属の歌人だったのです。
清少納言は幼い頃から和歌や漢文に親しんでいました。
それだけの背景がなければ、とても当時としては最上級クラスの中宮のサロンに出仕することなどはできなかったでしょう。
過度の緊張
そんな彼女でも初宮仕えの時の緊張は相当なものでした。
それまで他人と顔を合わせることにあまり慣れていなかったのです。
彼女は、顔を人に見られることがとても恥ずかしかったようです。
中流貴族の生活から、関白家、宮廷という雲の上の世界に足を踏み入れたのです。

未知の上流社会への憧れが清少納言の感覚を麻痺させてしまったに違いありません。
その時の日記が「宮に初めて参りたるころ」の章段です。
とても素直に書かれていて、後の清少納言とは全く雰囲気が違うのに驚かされます。
全文は長いので、少しだけご紹介しましょう。
「宮に初めて参りたるころ」の原文
宮に初めて参りたるころ、ものの恥づかしきことの数知らず、涙も落ちぬべければ、夜々参りて、三尺の御几帳の後ろに候ふに、絵など取り出て見せさせ給ふを、手にてもえさし出づまじう、わりなし。
「これは、とあり、かかり。それが、かれが。」
などのたまはす。
高杯に参らせたる大殿油なれば、髪の筋なども、なかなか昼よりも顕証に見えてまばゆけれど、念じて見などす。
いと冷たきころなれば、さし出でさせ給へる御手のはつかに見ゆるが、いみじうにほひたる薄紅梅なるは、限りなくめでたしと、見知らぬ里人心地には、かかる人こそは世におはしましけれと、おどろかるるまでぞ、まもり参らする。

暁には疾く下りなむといそがるる。
「葛城の神もしばし。」
など仰せらるるを、いかでかは筋かひ御覧ぜられむとて、なほ伏したれば、御格子も参らず。
女官ども参りて、「これ、放たせ給へ。」など言ふを聞きて、女房の放つを、「まな。」と仰せらるれば、笑ひて帰りぬ。
ものなど問はせ給ひ、のたまはするに、久しうなりぬれば、
「下りまほしうなりにたらむ。さらば、はや。夜さりは、とく。」
と仰せらる。
ゐざり隠るるや遅きと、上げちらしたるに、雪降りにけり。
登花殿の御前は、立蔀近くてせばし。
雪いとをかし。
現代語訳
中宮定子様の御所に初めて参内した頃、気が引けることが数知れずありました。
涙がこぼれ落ちてしまいそうなほどだったのです。
毎夜参内しては、三尺の御几帳の後ろに控えていると、定子様が絵などを取り出してお見せくださるのを、私は手さえも差し出すことができず、どうしようもありません。
「この絵は、こうであり、それが、あれが…」などと定子様が説明してくださる。
高坏に灯し申し上げた大殿油なので、定子様の髪の筋などが、かえって昼間よりもはっきり見えるのでした。
恥ずかしいのですが、それを我慢して定子様を時々見たりします。
とても冷える頃なので、定子様の差し出されるお手がかすかに見えます。
非常に美しく、薄紅梅色でした。
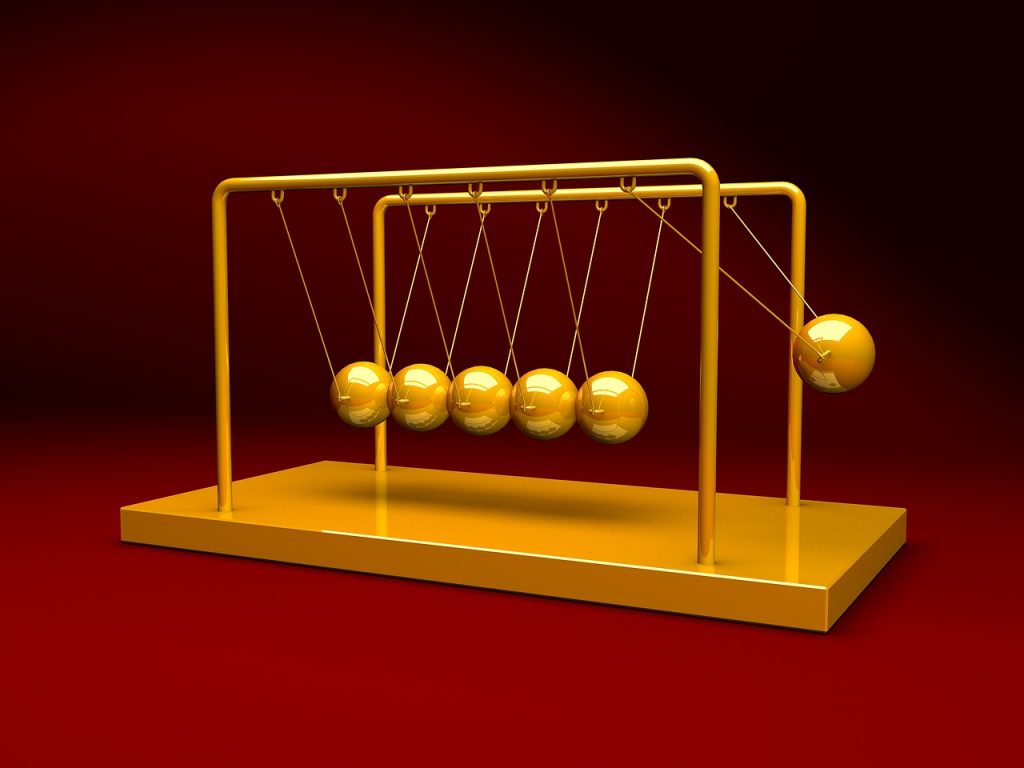
それがこの上なく美しいのです。
こうした世界を見知らぬ私には、このような人が本当にいらっしゃるのだなあと、びっくりするほどで、じっと見つめ申し上げました。
夜明け前には、早く退出したいと気がせかれます。
「いくらあなたが明かりを嫌う葛城の神だといっても、もうしばらくいてくださいね」と定子様はおっしゃいます
どうして斜めから御覧に入れられようかと、やはりうつむいているので、御格子もお上げしません。
女房たちがやってきて、「この格子を、お上げください」などと言うのを聞いて、他の人が上げようとします。
定子様は「上げては駄目です」とおっしゃるので、女房たちは笑って帰っていきました。
中宮様があれこれお尋ねになり、お話される間に、時間がたってしまったこともありました。
「下がりたくなったことでしょう。それでは、早く行きなさい。夜には、すぐにいらっしゃいね。」と定子様がおっしゃいます。
退出して姿を隠すやいなや、女房たちが無造作に格子を上げたところ、外には雪が降っていました。
登花殿の御前は、立蔀が近くにあって狭いのです。
その日の雪はとても趣きがありました。
素直な喜び
清少納言が本当に10歳位の乙女のような振る舞いをするのが新鮮です。
この章段の文章は、『枕草子』の中では抜きんでて初々しいですね。
いくら歌人の娘だとはいっても、彼女は中流貴族の暮らししか知りません。
それがまばゆいばかりの宮中のサロンに突然引っ張り出されたのです。
目が眩んだばかりでなく、極度の緊張にさらされたと思います。
中宮定子が、その不安を1つ1つ、薄皮をはぐようにしていく様子も見事です。
初出仕の時の様子が、目に見えるようです。

怖いし不安だけれど、嬉しかったでしょうね。
この中宮のためならば、どんなことでもしてさしあげようと思ったに違いありません。
そういう心の一途さが清少納言にはあるのです。
そこを味わうには是非、この章段の全文を読んでみて下さい。
ふと格子をあげると雪が降っていたなどという描写は、作家の視線です。
並々の女性ではなかったことが、よくわかります。
緊張の中にも、風景を自分のものにしていこうとする意志の強さを感じます。
是非、味わってください。
『枕草子』がなぜ今の時代にまで残っているかがよく理解できるはずです。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。


