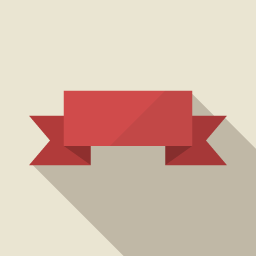正岡子規
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は正岡子規の生涯について考えてみましょう。
あなたは彼がどんな人か知っていますか。
名前ぐらいは聞いたことがありますよね。
学校でもほんの少しだけ学びます。
しかしその生き方をきちんと勉強するチャンスはなかなかありません。
今回は俳人、長谷川櫂氏の著書『平気』から子規臨終の時の様子を探ります。
3年生用の『現代文』の教科書に所収されていました。
ちなみに「平気」というタイトルは、子規の著書にある語句からとったものです。
子規の言葉は次の通りです。
余は今まで禅宗のいわゆる悟りという事を誤解していた。
悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きる事であった。
いろいろなことを考えさせる、いい文章だと思います。
子規は俳句、短歌、詩、小説、評論、随筆など多方面にわたって創作活動を行った人です。
夏目漱石をはじめ、日本の近代文学に大きな影響を及ぼしました。
明治を代表する文学者の一人といっていいでしょう。
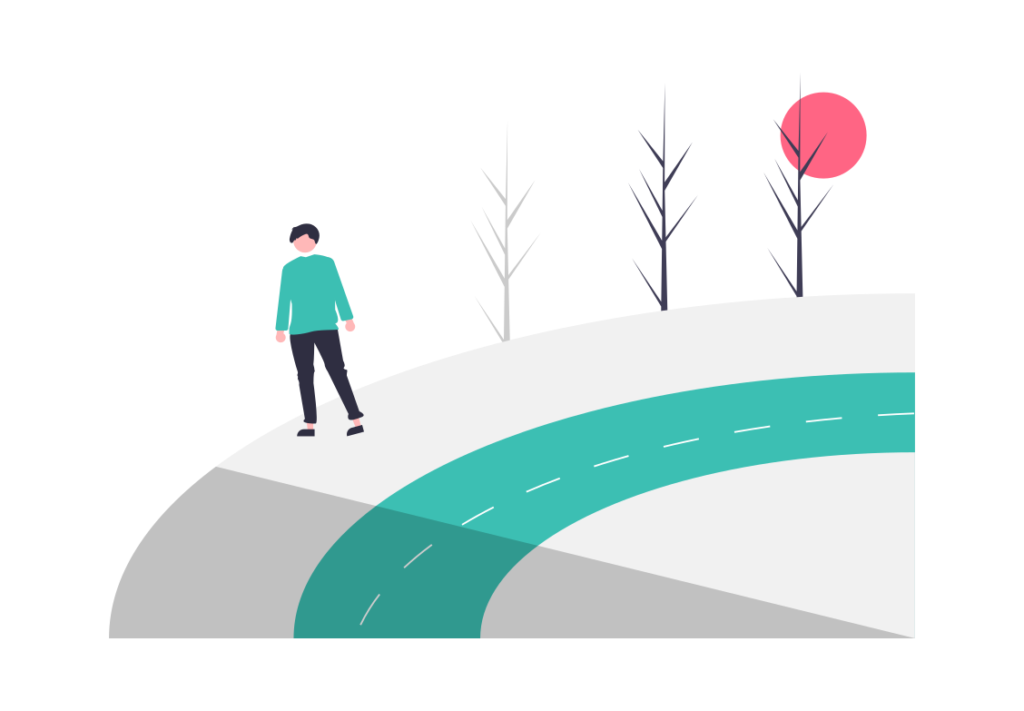
1890年(明治23年)、東京帝国大学哲学科に進学した後、文学に俄然興味を持ち始めます。
翌年には国文科に転科しました。
この頃から「子規」と号して句作を行うようにもなりました。
東大予備門では夏目漱石、南方熊楠、山田美妙らと同窓でした。
短歌では、代表的な著作『歌よみに与ふる書』を著しました。
この本の中で『万葉集』や源実朝の『金槐和歌集』などを高く評価しました。
「万葉への回帰」と「写生による短歌」を提唱したのです。
その後、「根岸短歌会」を主催して短歌の革新に努めます。
この会は後に短歌結社『アララギ』へと発展していきました。
日ごとに結核の症状が重くなり、臥したままで『病牀六尺』を書いています。
彼は死に臨んだ自身の肉体と精神を、冷静に客観視したのです。
まさに写生句が生まれる原点そのものともいえますね。
日記『仰臥漫録』は現在でも多くの人に読まれています。
「平気」本文
子規が滑稽家としての面目を遺憾なく発揮したのはその臨終の場面だった。
子規は明治35年9月19日未明に亡くなる。
その前日18日の朝、碧梧桐は容態悪化の知らせを受けて子規の根岸の家に駆けつけた。
午前11時頃、子規は寝たまま画板を妹の律に支えさせ、自分は左手でその下を持ち、板に貼った唐紙に絶筆となる糸瓜の3句を墨で書いた。
その場に居合わせて絶筆の介添え役を果たすことになった碧梧桐の回想録によると、子規はまずいきなり紙の真ん中に、「糸瓜咲いて」
と書きつけたが、「咲いて」の三字がかすれて書きにくそうだったので、碧梧桐が墨をついで筆を渡すと、子規は少し下げて、「痰のつまりし」まで書いた。

碧梧桐は「次は何と出るかと、暗に好奇心に駈られて板面を注視して居る」
すると、子規は同じくらいの高さに、「仏かな」と書いたので、碧梧桐は「覚えず胸を刺されるように感じた」
ここで子規は投げるように筆を置いた。
咳をして痰をとる。
やがて再び画板を引き寄せて筆をとると、「糸瓜咲いて」の句の左に、「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」と書いて筆を置くと、またしばらく休んで今度は右の余白に、「をととひのへちまの水も取らざりき」と書いた。
子規は筆を置くことさえ大儀そうに持ったままでいる。
穂先がシーツに落ちて、墨の痕がついた。
この三句をしたためてから14時間後に子規は亡くなる。
明治の文人らしい壮絶な最期だった。
妹、律
ここで子規の妹、律のことも少し書いておきましょう。
1870年(明治3年)、律は正岡子規の妹として誕生しました。
彼女が幼かった頃、子規が他の子供たちにいじめられると、律は勇敢に小石を両手に持ち、いじめっ子たちを追いかけたと言われています。
兄思いの妹だったのです。
15歳の時、律は陸軍の軍人と結婚しましたが、後に離婚しています。
その後、松山中学校で地理を教えていた先生と結婚したものの、再び離縁しました。
その後は上京し、病床の子規をひたすら看護したのです。
正岡子規は著書『仰臥漫録』の中で、妹のことを木石の如き女だと形容しています。
強情だの冷淡だのと書きつらねてもいるのです。
しかし一方では、「一日にても彼女なくば一家の車は其運転を止めると同時に、余は殆ど生きて居られざるなり」とも素直に自分の気持ちを述べています。
律は兄の病気と短歌の世界を少しでもいいものにしてあげようとする心から、一身を犠牲にしました。

彼女の看護は念の入ったものだったようです。
子規はいくつも妹を題材にした句を詠んでいます。
井戸端に妹が撫し子あれにけり
梶の葉を戀のはじめや兄妹
吾妹子と二人ならんで年わすれ
妹の朝顔赤を咲きにけり
妹なくて向ひ淋しき巨燵哉
恋かあらぬ妹かあらぬ春深み
春の夜の妹が手枕更けにけり
滑稽の精神
長谷川氏の文章は実にさっぱりとしていて読みやすいですね。
子規に対する愛情が垣間見えます。
もう少し読みましょう。
——————————-
この絶筆三句も従来は悲劇的側面のみが強調されてきたきらいがある。
しかし、よくよく眺めると、どれもおかしな句である。
特に最初の「糸瓜咲いて」の句は糸瓜の花陰で今にも絶命しようとしている自分を「痰のつまりし仏」などと笑っている。
そこには病苦にあえぐ自分自身をただの物体であるかのように冷静に眺め、しかもそれを戯画にしておかしがる筋金入りの滑稽の精神が存在している。
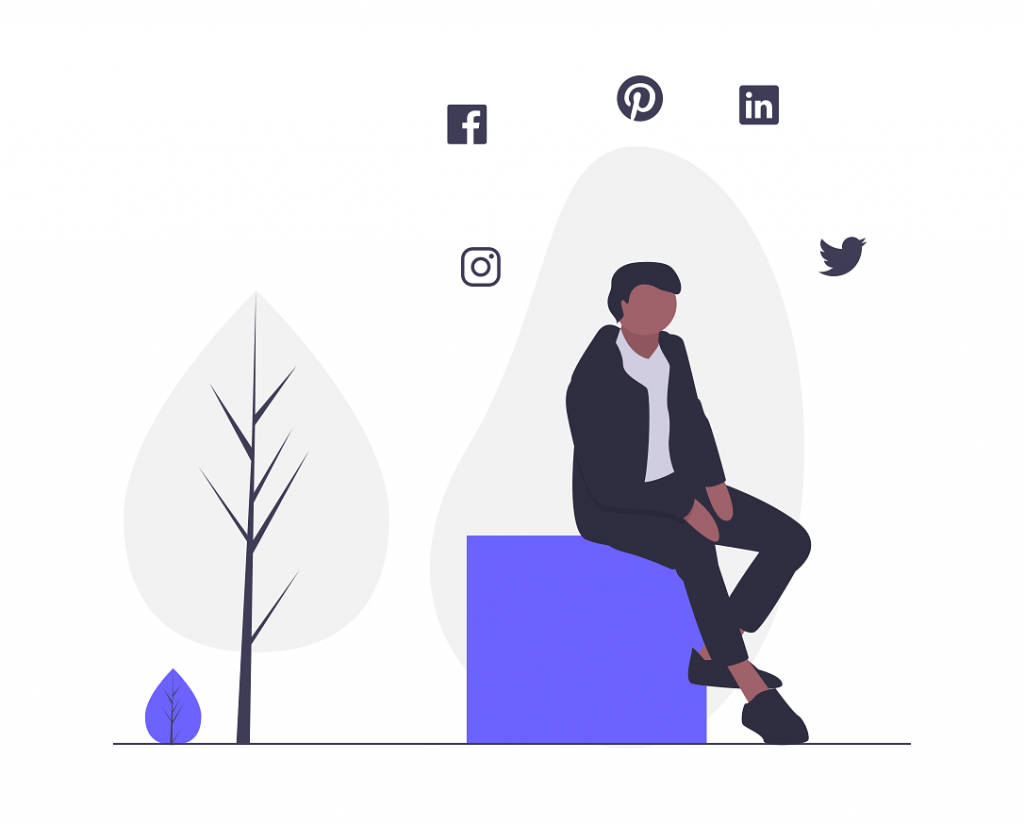
二句目、三句目にある「糸瓜の水」とは糸瓜のつるを切って根につながっている方の切り口を一升瓶などに差し込んでおくと、一夜にして水がたまる。
この糸瓜の上げる水が「糸瓜の水」であり、古来、痰切りの薬とされてきた。
「痰一斗」もをとといの句も妙薬の糸瓜の水もかいなく、こうして自分はあっけなく死んでゆくと言っている。
この二句にも糸瓜の水さながらにさらりとした滑稽の精神がはたらいている。
それまでは身辺のものに向けられていた子規の旺盛な滑稽の精神はいよいよ自分が臨終を迎えた時、子規自身に向けられることになった。
そうして詠まれた絶筆三句は子規という滑稽家の最後の燃焼だった。
臨終の子規にとって人生は一幕の笑劇にほかならなかった。
————————————
自分自身の詩を冷静に見て取る写生の精神が、この文章の中にはよく見て取れます。
ここまで自分というものを客観的に見る力を持つことでしか、歌が詠めないのだとしたら、それは半ば酷なことなのかもしれません。
しかしそれがまさに詩人の業とでも呼ぶべきものなのでしょう。
そんな気がしてなりません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。